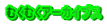
最新更新日 2012.8.27
写真への手紙 覚書
中川繁夫:著
写真への手紙 覚書
自写像の論/試論-2-
<ピエール・モリニエへ>
私がこの論を記述していくことに至った直接のインパクトは、自らの姿を恍惚感覚とともに写真に撮り、自らの存在感を残してピストル自殺した、ピエール・モリニエ(Pierre Molinier 1900-1976)の写真を観たことに拠っている。私設の簡易スタジオで、女装下着ストッキングを着けて撮ったカラー写真。コラージュ写真とそれに先立つ絵画の群。それらの作品の存在を知るにつれ、しだいに私の内部で、その作品が私に突きつけてくる狂気とも云うべき「意味」を問い始めなければならなかった。
最初、モリニエの写真の存在を知ったのは、もう7、8年前のこと、渋谷のギャラリーで開催された写真展を観る機会を得たことに始まる。そのときには特に強烈なインパクトを与えられたという訳ではなかった。それは流行写真の一種といったような軽い知覚であった。しかし、その後、次第にモリニエの自ら写した写真が、なぜか気になってきて、その「気になる」在処を探ってみたい衝動にかられ始めた。
それは私が単身生活を送っていた日々、自分が自分の内面とダイレクトに直面していたときであった。密室と化した家での寝つかれない夜中、イメージがイメージを呼ぶなかで気がつくと、見動かぬ私の身体があった。またそれらのイメージが拡大し、昇華していくとき、自分が自分の内面の欲求を見つめると、そこには私の身体があった。
あるいは身体の一部である精神が病み、石を抱いたような重さに身体がこのまま蝕まれ、消滅していくように想像したとき、私は身体があることを意識した。自分の精神と身体を弄ぶことは、そのままタブーの内側に這入ることを自覚した。興味のイメージが具象物として模造男根の制作に及んだときには、私の愛玩物に恍惚感を覚えた。この感覚は、遠い昔、少年時代の他愛もない工作物を作っていたときの感覚と、同質のもののように感じられた。しかし私は、その精神の飛翔していく恍惚感覚を、イメージの内に認めただけで、再び数年が経過した。
これら密室の体験を思い起こすとき、私は私自身の少年時代の出来事、一人で熱心不乱に工作していた光景とそのときの感情の流れを、連想させるのだ。小学生の上級だったか中学生の初めごろだったか、不用になった真空管ラジオやゼンマイ仕掛の置時計を、まるで八重の花びらのディテールを一枚一枚丹念に、観察しながら剥がしていくように、徹底的に分解し、それらを構成する物資、石に巻かれた抵抗器のエナメル線やコイル巻のトランス、噛み合わされた時計の歯車の、内部まで細分化して壊した記憶。
公園や道端から拾い集めた木片や小枝、石や砂、木の葉や枯れ草などを組み立てて、オブジェとして構築していた記憶。中学生になったころには身体に着付ける装飾品に興味を見いだしていたようで、布、細い飴ゴム、紐といったような材料で、そういった類を制作するようになった。それらは多分に性交の場におけるイメージを暗示するものであったと、最近思うようになった記憶。
身体そのものの成長に伴なっていつのころからか精液放出が認められるようになっていたが、装飾品の工作物が多分に性そのものと関連していたようにも思われるのだ。そしてこれらの時間は、常に熱中しており、唯一、目の前にある工作物と私の内部に醸造されるイメージだけに、熱いまなざしが向けられていた。
そうしておぼろげながら、性の目覚めと同時に愛の目覚めを知覚した。おそらくこの少年時代の行動とそこから生じてきた感覚は、自分意識の起立、自我と呼ばれる認知、その初原のものとしてあるのだろう。
<欲求>
作家が作品を制作するとは、どのような契機から始まるのだろうか。まず私はこのような疑問を、私に向けて発した。ここで「作家」という言葉を冒頭に記したが、これは個人が作品を制作する意思を持ってする状態を想定している。
勿論、それは人間が意識(すること)を持ち、イメージ喚起を連携させることで別個のイメージを生み出すことができる唯一の動物であるという前提から始まっている。
「作家」というからには私はすでに教養文化に立脚したインテリジェンスが備わったレベルを想定しているが、論の行方は動物から人間へという考察及び本能として内在するものを抜きにしては展開できないようである。
動物は種の保存と生存のために行動する。この生存のための行動には「行動する」という意思が伴っているが、動物一般にはその行動によりイメージ喚起の内に結果を想定するということはない。
動物の行動は、本能及び経験による反射反応であるとされている。人間はこの動物としての反射反応を基盤として意識することを持ち、イメージ喚起と喚起されたイメージを認識する意識を個体内部で生成することができる動物である。
本能の範疇に由来する行動は、おおむね種の保存と生存のための行動であり、それはいくつかの欲求の、(生理的なもので行動欲求が起こる)カテゴリーに分類されるが、基本的には性欲と食欲のふたつであるようだ。
私は写真に特化した表現の領域に、本能の範疇がどのように係わってくるか、ということについて興味を持っている。これは自分をみつめる私自身の考察過程で明らかになってきた意識である。
おそらく意識化するイメージの連携により、かって見たものの像が脳裏に現われることは、本能的欲求が未分化であった人間生成期の太古、非文明の世界から、本能的欲求が「芸術」表現にまで高めることができるようになった現在まで、人間の作品創出過程には常にその背景に、あるいは根底で本能として認めうるものが、作用しているのであろう。
その人間の置かれた体制、その時代の同軸上の文化の総体に制約されながら、作品の質が形成されてきたものではなかったか、と考えている。体制の制約とは、その時々の権力構造から発生するものであり、許容と禁句との紙一重の狭間で、芸術行為は成立してきた。
あるいは人間の欲求は、この枠を超えて逸脱してきた。そしてパブリックに発表され、芸術として認知されてきた作品は、この限定された許容の枠内で、作家自身の生の在り方が問われてきたのだった。そうして、許容枠は絶えざる変質と拡大・縮小を繰り返し、拡大を成してきた。
人間あるいは私が、一個の肉体と感性を持った対存在としてあるとき、本能の根底から教養文化をふまえた感性と行動することの高みまで、さまざまな感情の流れとともに「行動すること」をとるが、この行動の範囲は、常に教養文化に密着しているようだ。しかし私自身には、おおむね人間には共通のものと思われるが、この許容の枠を突き崩す衝動または逸脱していくイメージを認めざるを得ないのだ。
私は、常にこのモラルを突き崩しにやってくる衝動の根底は何か、と問わねばならない。ここに未定形の宇宙の広さのような、暗闇の中の精神の混沌を認めるならば、この感覚は無限の深淵からの生理の本質、性的なるものとともにやってきているのだと云うしかない。
私の内側でのこの衝動は、直接に文化内部での既成の価値体系の解体欲求と、新たなる価値への組み直しを希求する衝動そのものである。
人間が知の集積の結果として形成してきた文明と、そこに内在する文化諸相の縁をみてみると、集団規範(社会制度内の慣習)に対して個の内部における集団規範逸脱部分を認めることができるだろう。当然、個の意識構造からくるイメージ喚起力は、文化が持つ諸道具を介在して、無限に拡張していくものであり、規範はこの無限の拡張に対して規制し、範疇化し、整列化させる。
規範はいつも、正常と異常あるいは異端、通常にはノーマルとアブノーマル、モラールとアンモラール、といった区分けを行ってきた(モラールとは、風土と解釈してよい)。文化が在るところでは、異常あるいは異端は、常にそのモラールの容態変化に対して、カウンターメロディーとして存在する。
また、モラールとアンモラールの関係は、権力によってつくられ、基本的に権力に抗する反権力の構造関係である。アンモラールは時として反権力としての様相を露呈させるので、そのつど弾圧される。モラールに内在するアンモラールは抑圧される。
私自身を振り返ってみるなかで、生い立ちの詳細を丹念に内省してみると、巷でそう呼ばれる思春期のころ、14歳前後から、芽生えはもっと以前に、それは母親の類似物としての意識であるが、同年代の異性を意識しはじめた。おとこは男らしく、おんなは女らしく、育てられる文化風土の中にあって、なぜ男と女が一緒にいることが特殊なことなのか。ことの最初の巷の囁き言葉を意識しはじめたころには、理解できなかった。
このころ私自身の感覚には、大人性と幼児性、男感覚と女感覚が混在し、それが未分化のまま、私自身のなかに混在していたように思われる。しかしその数年後には、私という「個」に対して巷の言葉と私へのまなざしとして、私に突きつけてくるモラール、風土の慣習に従順し、大人性そして男性としての巷にある外容をそなえてくるのだった。モラールの仕組みそのものから、私自身の制度として、そのように振る舞う生活実績を集積させていくようになった。
一方、連続する内面の過程を振り返ってみると、それは必ずしも外容どうりに枠づけられるものではなかった。いつも精神の在り様、あるいは感情の起伏は性的なもの(大人性と幼児性、おとこ性とおんな性、と対比したときの幼児性とおんな性)が未分化のまま、今日に至っているように思える。確かに大人(他者との関係における場の占め方)としてある在り方や、男性(社会制度の気候における場の占め方)としてある在り方により、他者のまえに存在するとしても・・・・だ。私の注目は、この性的なものが未分化のままある、と認めるその内容である。
<自分の発見>
本能としての性欲が私の身体を支配していることは、おそらく動物的なものとして万人に備わった感性と肉体の在りようと同様のものであろう。また「自分の発見」は最初、鏡に反映する姿をみて自分であることを自覚する習慣により、自覚されるものである。ここでいう鏡とは、肉体そのものの実体を映し出すガラス面の「鏡」であり、内面的には言葉をもって自分を映し出す「日記」あるいは記憶に刻み込まれたイメージとしての「像」である。
自己保身を身上としている人間にとって、自分が自分に抱く興味は、日常会話のレベルで言葉を交わす時においても、自分自身を深く意識することがないように、日常的には無意識の領域に属している。自分自身を内省する態度をあらわにするのは、イメージ喚起力を主体とする知的生産そのものである。自らを分析しえる能力は、社会の諸相を分析しえるトレーニングされた能力よりもなお、上層能力であるのかも知れない。
自分を自ら分析することは、一個の人間がその生の長さのなかで経験(直接体験と疑似体験があり、ここから派生する類推体験)したことによる自己の内部への記録と、そこから生じる「記憶」の呼び覚ましにより、断定を下していく過程である。こうして自分を客体化させることによって、自分のイメージ像に自分を置くのである。
ここに立ち現われてくる自分の姿、自分の顔、自分の肉体、あのとき着ていた服装、等々を認めるのは、自分の姿を鏡のまえで見た記憶と、それが自分だという認識の結果に他ならない。自分はたった一人では生きられない。自分の生の長さよりも長い以前に、母があった。そして父がいた。これは私の宿命である。人間が動物である限り、この種としての起源を乗り越えることはできない。そして自分を保守するという本能を持つ。自殺は教養文化の成せる高度な技のひとつである。
教養文化は生まれて育った風土と対関係にあるが、人間はこの風土が培ってきた文化と呼ぶモードのなかで、その文化を纏いつかせる。また自分を傷つけ殺しにやってくるもの、物理的には凶器として、精神的には狂気として、立ち現われてくるものには、身構えてしまう。
たとえばピストルを突きつけられ、肉体を傷つけられる。死へ一直線に向かう不治の病を宣告される。そして不意打ちをくらったように起こる恋愛。人間がみずからの記憶をとどめておく為に持った手段として、芸術そして写真。
写真とは、自分にとって、何なのだろう。現代の写真を手段に選ぶ作家及び批評家は、常にこの命題を内含させている。写真を現実コピーの手段として、あるいは遠い景色を身近なところへの移送手段として、というように、かって捉えられた写真制作過程と批評の歴史的過程における捉え方から評論する限り、「写真とは。自分にとって、何なのだろう」という疑問符はつけようがないが、現代の作家構造の在り様を問う作家態度にしてみれば、これは基本的命題である。
写真を撮ることは、自分の存在理由を問うことであり、存在の在処を求める行為である。セルフポートレイトという自分にカメラを向ける行為は、自分自身を相対化させる行為である。近代における個の自立が捜し求めてきたのは、つまり自分とは何か、という問いかけそのものであったと云える。
「自分は社会的存在である」という認知は。「自分にとって社会とは何か」という分析に立ち入る。社会とは目の前にある現実。そこは権力そのものの構造であった。
<内世界>
自分の内部は、この権力関係のない世界。ここでは自分が自分を観る構造と自分が社会を観る構造とは、相反する関係にあることに気づくのだ。この地平から、自分を取り巻く社会構造を引き合いに出して検証を加える。そこには自分を抑圧する権力関係と、それに従属するイメージの認知。
また目の前に現われる写真、あるいは私が撮った写真が、マス・メディアの従属物として、つまり抑圧する権力関係の権力そのものとして認知されるとき、写真家は自分の内部で、この権力構造との葛藤あるいは戦いを意識せざるを得ないのだ。
この葛藤は個を抑圧するものを洗い出し、問い直し、関係そのものを解体し、そこから新たなる関係を模索しはじめるであろう。権力関係を持った視点を告発する視点。そして自分における自分像の検証。既成の価値観によって歪められてきた自分像の発見。このイメージを問い直す作業が、自分に課せられた命題として、自分の内部に立ち現われてくる。
新たなる自分を、そこにイメージとして見いだすとき、被写体は自分自身となる。すでに「私」の価値基準は、これまであった価値基準とは相入れないものとなる。支配し支配される関係を断ち切り告発する手段として、それは存在する。
(shigeo nakagawa 1993.12.31)