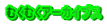
最新更新日 2015.10.16
物語る物語り
中川繁夫:著
物語る物語り
1~4 2015.8.16~2015.10.3

なんだか、へんな気持ちが湧いてきて、何がへんかといえば、まるで恋心のような初々しい気持ちだと思えるのです。古希って、こんなに瑞々しくて、若々しくて、ふくよかな感情なのだと、われながら、感心してしまいます。「物語る物語」なんてタイトルにしてしまったこのブログ。もう潰してしまおうかと思いながら、過去に連ねた文章が残っているので潰せずに放置していたわけ。直前の革命ノートは、まだまだ続くのですが、図表が多くなってきて、まとめきれなくて、一旦終えて、次に書ければ書くということにしたい。というのは半分嘘で、思い出、記憶がよみがえってくるからです。
記憶ってゆうのは、いけませんね、自分を苦しめたり、楽しくさせたり、でも楽しくさせてくれなくて、そこは反省と失笑と羞恥に満ち満ちているわけです。生きてきて、生きてるのが、もう恥ずかしくって仕方がない、素面の顔を世間様に向けていることが恥ずかしい。というのも、ひとり密かに鏡を見るじゃないですか。そこにはまぎれもなくわたしという自分が映っているわけです。どう見たって年寄りじゃないか、古希丸出し、もう生殖機能なんて1%も残っているのかどうかも不明瞭なのに、初々しい気持ちになっていることが、自分にとって恥ずかしいのです。
認知症ってのは、この記憶の連続性が壊れる、と思えばよろしいんでしょうか。古希を迎えたぼくは、いま、どのような位置にいるのでしょうね。なんだか、ちょっと、へんな感じ。ほれ、古事記だったか、この世の初め、ぶよぶよ、明暗が区分けされ始める頃のぶよぶよ感。いや、ぶよぶよ、なんてそんなイメージじゃないかも知れない。混沌、混沌としている霧の中、無我夢中、夢の中ではなくて霧の中。古希なんて、想像力、イマージネーション、もう際限なく拡がっていく気がしてます。こんな、ちょっとへんな感じで、物語を物語たいと思って、書きはじめました。
(2)
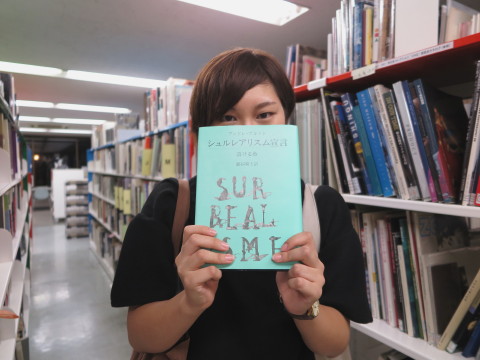
シュールリアリズム宣言なるものがアンドレ・ブルトンの手によって書かれ、出版されたのが1924年10月だと書かれています。シュールリアリズムとは、超自然主義と書けばいいのでしょうか。ぼくの心の中身は、シュールリアリズム、妄想に満ち溢れているといっても言い過ぎではないと思います。20世紀の美術や文学や映像、及び21世紀を15年も過ぎてしまった現在点。この100年というのは、表現の方法の対極にあるリアリズムとシュールリアリズムが、心の中でひしめきあっていると思ってしまいます。ぼくらの世代というか、20世紀の後半から21世紀の前半を生きる者にとって、その心に創られるイメージの連鎖は、このリアリズムとシュールとのあいだを行ったり来たりしている感があります。
まあまあ、リアリズムの定義からはじめないと、意味をなさないわけだから、ここでリアリズムとは、なんてことを定義してみようと思います。リアリズムとは、ありのままに、なんてあるがままにを、そのまま表出させることかなぁ。それに対してのシュールリアリズムとは、ありえないこと、ありえないことをあるかのように表出させる。どちらにしても人間の仕業だから、そこにはその人の意識が介在し、表出するためのスキルがあるというわけです。まったく正当な論にはならないんですけど、想起できるイメージとして、リアリズムは社会問題を直接の契機として成立させる表現の方法であって、シュールリアリズムは人間の内面を表出する方法、であるかのようにふるまっていると思えます。
性表現、セックス表現のことは、シュールリアリズムがお手のものとする領域のように感じています。男女の性関係、性交渉、それにまつわる外形のことを、文章にしたりイメージ画にしたり、イメージ画はカメラで撮られて作られることによって、リアルさを増す。こういうことでいうと、シュールリアリズムは、人間の内面を表出させることだと云えるのかもしれません。内面のことといえばセクシュアルなこと、肉体があって、この肉体にこだわる。肉体が欲するところは性欲の発散、ということなのでしょう。フロイトやユングといった心理学者さんの言説を引き合いにだして、そこに性をテーマにする表現の領域があると思えるのです。ぼくの思考は、そのシュールリアリズムに準拠して、とらえているように思えるのです。
(3)

極論すれば、この日本に革命なんて起こせないのに、革命を起こそうとした連中がいたというお話です。1970年前後の数年間、それは本気で語られ、本気で行動した連中がいたわけです。それはこの日本では犯罪だったし、逃亡のすえに警察に捕まった連中がいたわけです。それから40年以上が経ったいま、2015年なわけですが、戦争放棄を唱えていた日本国が、戦争放棄を放棄した年となったわけです。革命を起こそうとして起こせなくて監獄につながれた連中がいる一方で、革命ではないが戦争放棄を放棄した連中が、監獄につながれることはないのか、と思う次第です。
この日本国には枠組みがあって、その枠を定める枠組みは憲法です。憲法のもとに民法や刑法といった法律があり、特別法があります。この法律に違反しない限り、つまり適法である限り、なんのお咎めもないわけですが、その枠から外れると違法になるというものです。戦争放棄を放棄したと書きましたが、これは確定したわけではなくて、いまのばあい、ぼくが勝手にそう考えているだけです。このことが違法であると判断するのは、三権のうちの司法、裁判所、ということになります。今後、訴えがあって、裁判所が違法か合法か、違憲立法審査権でしたか、これは最高裁の特権でしたか、それに委ねられるのかどうかです。
独裁者は、立法も司法も無視して、暴走する。想像力を働かそう。この100年間を見ても、暴走した事例が散見できます。日本においても、70年前までは、そういう事態ではなかったのか、と問います。そうならないための歯止めが「憲法」であり、戦争放棄の規定ではなかったか。その歯止めが、潰え去った日が、2015年9月19日という日、なんと言おうかこの記念日のことを。戦争放棄放棄記念日、とでもしておきましょう。この記事につかった写真は、内容とは関係していませんが、なんとなく緊張関係が伝わってくるように思えるのです。
<『アナバシス』は古代ギリシアの軍人・著述家であるクセノポンの著作。アナバシスとは、ギリシア語で「上り」という意味。クセノポンがペルシア王の子キュロスが雇ったギリシア傭兵に参加した時の顛末を記した書物である。Wikipedia>
(4)

かって読んだ小説のストーリーが、映画のシーンのようによみがえってきます。ドストエフスキーの罪と罰でしたか、金貸しだったか老婆殺しをしてしまう内容。イメージとしてはかなり暗い、暗いイメージがしてなりません。思い出しては心が欝になる感じで、いたたまれない気持ちです。といいながら、罪と罰の内容が老婆殺しだったかどうかということも、定かではありません。
小説のなかのイメージではないけれど、現実のイメージとして恋した相手に対して、その気持ちを打ち明けられないまま、終えてしまうという場合の心の処理の仕方です。ぐっと我慢をすれば、時間とともに忘れていく。文学的に、喜劇的にいえば、忘却の彼方へ、ということでしょうか。その時間という長さが、たとえば一ヶ月なのか、一年なのか、それとも三年、千日、なのか。
虫たちにも恋する気持ちがあるのだろうか。なんて問うても、あるわけないじゃないですか。子孫を残すために交合するというのは自然の摂理であって、人間がいう恋心なんかじゃなくて、愛のフレームでもなくて、ただの本能、ということなのでしょう。人間ったら、それを言葉のうえで、あれやこれやと云うからややこしくなるだけなんでしょう。
ロラン・バルトに「恋愛のディスクール・断章」という名著があって、小生の目の前の書棚に背表紙が見えているけれど、なんだかこれは、かっこぶっている人間の思い入れみたいな感じがして、実際にはその心は穏やかではなくて、死に物狂いで求めているイメージのところです。いやはや、犯罪となるケースも多々あるのは、恋する心が異変を表わすからでしょう。