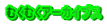
最新更新日 2012.5.26
現代写真の視座・1984
-ドキュメンタリー写真のゆくえ-
中川繁夫:著
写真における「記録」論(2)
5-1
私の手元に、いま三葉の写真が広げられている。これらは、ともに1944年に撮影されたと記された写真の印刷物、厳密には写真集として編集された書籍の中にである。
その第一番目は、ユージン・スミス(W Eugene Smith)の撮った、戦争続行中の空母バンカー・ヒルの艦上から海に沈められる戦死者の写真である。また第二番目は、ロバート・キャパ(Robert Capa)の撮った、ナチに協力したため髪を剃られ町から追放されるフランス女性と群衆の写真である。そしてその愛三番目は、アンリ・カルチェ・ブレッソン(Henri Cartier Bresson)の撮った、パリ解放、路上で機関銃を放つ兵士の傍らでパリ市民が相手方をじっと見入っている写真である。
1944年といえば、第二次世界大戦の末期にあたる時期である。これら写真に定着させられた光景が、異様なまでに私の感性を噛んで離さないのは、まずこの光景そのものが平和時にはみられない異常な光景であるからだ。死者を弔う方法としての水葬。戦争という私の抱くイメージのなかで、しんしんと迫りくる静かさ。また髪の毛を剃られて追放される赤子を抱いた女性と、この彼女を遠巻きにして、いまにも歓声をあげそうにこの母子の追放劇を見送る群衆。これが戦争という総体のなかでの個別の現象なのだ。またパリの路上での市街戦。これを平服のパリ市民が興味深く見守っている。もし仮に私の生活空間の中に、これと類似した事象が出現したとするならば、と連想せずにはおれない。
<日付>と<場所>が、これほど決定的な意味を持ち得る写真群が、他にあるだろうか。また一枚の写真が、私をしてこのように様々な言葉を語りださせるのは、写真そのものだけではない。私がこれらの写真を見ることによって、私がすでに持ち得ているイメージからの連想。1944年という時代をとりまく背景のカテゴリーが呼び起こさせてくるのだ。戦争という背景。異常であっただろうと想像する私。それらマス・ヒステリーの状況を各々の写真が、克明にとらえているのだ。
私はその時代を知らない世代だ。それらの時代からすでに何十年という歳月が経ってから書物や映像によって知りえたものだ。
記録とは、その時代の内部に起こった事象の、人為による定着の行為の結果である。それらの写真が、私に或る種の感動を与えてくれるのは、いま見てきた三人の写真家の視点が、私がまだ存在しなかった時代に生き、明確な現状把握のもとに彼らの遭遇した光景に対してシャッターを切ったという事実においてである。そして彼らの行為によって残された写真を観ることができるという幸運によってである。
そして何よりも感動するのは、ここに明らかに「私」という存在の視点が介在していることだ。
5-2
これらの写真が、先に観たアッジェの写真群と明らかに異質な点は、明確な私性の介在ということであろう。とはいえ、ここでいう私性とは、写真家がカメラを向ける対象と、シャッター・チャンスについて、作家の価値観に裏打ちされた視点が確立されていることであろう。
これらは三人の写真家、ユージン・スミス、ロバート・キャパ、アンリー・カルチェ・ブレッソンが、その時代を生きたフォト・ジャーナリストとして、報道を主眼とした写真家にとっての視点である。いずれも戦争状態の下に、という大前提を背景に、同時代人として生きたなかでの証言として、記録している。
ブレッソンは彼自身の、写真に対する見解について、次のように言っている。
<写真を撮るということは、移ろい易い現実の表面にすべての力が凝集した瞬間の呼吸をとらえることである。>
また次のようにも言っている。
<写真を撮るということは、認識することである。事実と、その事実に意味を与える視覚に知覚された形の厳密な構成を、同時に認識することである。>
事実をどのようにとらえるか。また、とらえた事実の意味を視覚としてどのように置き換えるか。社会性に根拠を置いた自己の内面の投影と自己が認知した事実の意味づけを、どのような回路で繋げるか。そして第一の意義に、「事実」という社会的客観性が優先されるのだった。
報道(事実をより多くの人々に知らせる)を前面に押し出したルポルタージュやドキュメンタリーのひとつの方法論は、言うまでもなく「事実の記録」という社会的な客観的視点というものを、いかに内含するかという問題であった。西欧リアリズムの系譜の中で、常にそのテーマとされてきた、社会性をもつ自己、社会にむけて開かれた自己、社会化された「私」の具現として、写真の方法もまた、これの主張であった。
「記録」とは、その時代の典型を描きだすことであり、それの社会への定着であった。しかしこの典型を描くことにおいては、その作家自身の極めて個人的な解釈から出発しなければならないのだ。そこでまず、認識する、ということが個の自立につながり、すべてはここからはじまるのだ。
6-1
写真は、その時、まず私が持つカメラの前に存在した事象がフィルム等に定着される。そこで注目すべき点は、そこには<私>という存在の視点がまず介在することである。その人間の感性と意志が介在するのである。
風景を私の側に引き寄せる。私の知りえた光景を私の内側にとりこみ、私の視点によって現実を変質せしめる。しかしこの変質させられた現実こそ、ここでは唯一の<現実>となるのだ。カメラとしては、<私>の意志や視点がなくてもシャッターを切れば写る。
単純に考えれば文章を書くという作業には、必ず書く人の意志や視点が介在しなければならないけれども、写真にはそれがなくても写るという事実がある。しかし写真行為とは、単純にこれだけのことではありえない。写真における記録とは、単にシャッターを切れば定着させるそれではないのだ。
再びアッジェの写真に戻ろう。彼の撮影したパリの街角がある。アッジェの存在が、この同時代にあったピクトリアルな写真家たちと一線を画されるのは、まずアッジェの写真が、街へ出向いていることである。このことがまず第一に記録、つまりドキュメントとなりうる要素であることだ。
写真はもちろん芸術の一角を占有してよいはずだが、写真としてのその際立った特質は、その記録性(ドキュメント)にある。アッジェは自分が苦労して撮った写真を、「絵画のための資料」として位置づけ、画家に売ることによって生計を立てていたという。しかし彼の撮ったパリの街角は、彼であったからこそたたずむことができた世界であった。
アッジェが撮ったパリの街角、それはみずからが生活する場所、生活の周辺であったのだ。アッジェがとらえた街角の風景は、彼が日常、いつでも目にふれることができる光景であり、彼にとっての撮影行為は、芸術でもなければ記録でもなかったのであろう。彼の生活上の欲望そのものがシャッターを切らせたといえるようにもみえるのだ。
写真の描き出す世界。アッジェにとらえられた事物は、彼の行動範囲を超えることはない。彼が撮った写真の現場は、彼が立ち振る舞った世界の一部である。アッジェの目の前に広がったパリの風景が、単に街角のたたずまいであり、パリという都市の構築物であるにもかかわらず、見る側にシュールな感覚をほうふつさせ、そのうちに静かなる感覚を呼び起こさせる。
写真は余りにも静寂すぎるし、余りにも克明に写されすぎている。記録(ドキュメント)というなれば、これほど明確な記録(ドキュメント)はない。また見る側に何かを予見させ、都市の様々な現実をほうふつとさせるのは、まさにこれは芸術以外の何ものでもない。
7-1
アッジェがとらえた写真の世界がある。その写真の向こうには写真に写された現実があり、そのとき存在したモノがある。その写真のこちらにはアッジェの事物に対する視線がある。写真として定着されたもの、及びその現場は、アッジェ自身の内部と、外部に広がる世界との唯一の接触点であり、葛藤の現場なのである。
<私>はそこにこそ存在する。そこにはアッジェをとりまいた複雑な現実の制度、社会構造がある。彼はいわゆる都市生活者ではあるが、当時の上流と呼ばれる階層には所属していなかったという。しかしその時代の諸制度や、社会構造を構成する一員として存在する以上、意識するしないにかかわらず、その社会構造をふまえたうえでなければ、写真の撮影行為は成立しないのだ。
アッジェは、その時代のパリという都市、その文化内部の諸相をも持った時代の内在的存在者として、写真行為を持った。こうした時代背景の中で写真行為を持つということは、まず諸制度にからめられた被写体に立ち向かうということであり、被写体はアッジェに対する世界の唯一の切り口となる。アッジェは、彼の前に現われた事物を、写真として定着した。まさに内部に広がる世界と外部に広がる世界との唯一の接触点としてである。
写真行為とは、このように見てくるかぎり、個的な作業であり、そこにはパーソナルな意志が介在する。またパーソナルな意志は、時代の諸制度の意志によって創られるという関係を持つ。
世界は常に第一人称の<私>と<私をとりまく世界>との関係の中に存在する。そしてこの世界は、<私>にとっての第二人称的な意味を持ち、関係性を持つ。<私>の存在なくして<私>が認知する世界はありえない。たとえ<私>が存在しなくても世界はたしかに存在しうるとしても、だ。しかし<私>が存在しない限り、<私>が表出せしめようとする世界はありえない。
表現と記録は、常に一対のものだ。この表現を<芸術>と置き舞えてもいい。<私>がこの世界内存在である限り、<私>の意志が表出を試みることによって、表現すなわち記録行為は成立し、存在する。
8-1
ここではアッジェの写真と、時代を下って第二次世界大戦末期1944年に撮られた、三人の写真家、ユージン・スミス、ロバート・キャパ、アンリー・カルチェ・ブレッソンの写真を対置し考察してみた。
ともに時代の記録として現在に残された貴重な光景である。
またアッジェの時代から1944年までお歳月は、1944年から現在までの歳月と、(1984年現在)ほぼ同じ長さだ。この時間差が物理的には同一であったとしても、科学的進歩の速度や社会状況の変化においては、同一のパターンではないだろう。が、時間軸に限って見てみると、一つの連続した過程としてとらえることができる。ここから私は、<記録>の本質とは何かを探ろうとしているのだ。
アッジェの時代における写真とは何だったのか。アッジェという写真家が撮った写真を、私たちには、写真におけるドキュメンタリーの源流としてとらえることができる。そして約半世紀後の第二次世界大戦末期のドキュメンタリーの展開。もちろん私は、現在の写真におけるドキュメンタリーというものの位相が、どこまでやって来ているのかを把握するための筋道として、その両者の時代を仮定し、対置するのである。
「記録」写真家たちがとらえた時代、スミス、キャパ、ブレッソンの時代。このころ写真は、すでに時代の寵児として、そこに様々な意味を与えられ、様々な方法論を展開し、そして様々な構造を持つに至るのであった。
(この章おわり)