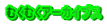
最新更新日 2016.12.27
写真への手紙/風景論
写真への覚書
中川繁夫:著
seesaa blogに連載の文章
写真への覚書
1~11 2016.9.27~2016.12.13

-1-
最初の記事は、このブログでなにがなされるのか、ということです。芸術、あるいは自己表現のツールにおいて、<写真>と呼ばれているモノについて、考察していくことが目的です。幾筋もの方向から、それは捉えられるべきだし、この時期、2016年という現在において、書き記されたものとして、この論を残していきたいと考えるところです。語り口は雑多に、いくつものテーマと角度から書き記されることで、論が重層的に組み上がっていくのではないかと思います。写真の歴史、とくに日本、特に大阪を中心とした関西の写真歴史、それから現在の状況、私自身の記憶に基づく記録、などなど、書き記していきたいと思います。
主には、私が体験してきたことを中心に、思い出しながら記述していこうと思っています。ということで言えば1970年代から現在までの、写真をめぐる動向を記述することになるから、ある種の個人的な歴史となるのだとも思います。かなり躊躇していました。それは、今更、という気持ちと思いが先にあって、書く気にはならなかったのです。過去を掘り返したところで、それはノスタルジーにしか過ぎなくて、現在から未来においての制作の邪魔になる、と思っていたわけです。ところが、最近、写真論、写真史、とくに関西の写真史を作っておくのがよいのではないか、と言われたこともあって、その気になったというのが現在です。
すでに写真論や関西写真史については、私観ながらホームページ上に載せているので、その追録、あるいは拮抗する場面もあろうかと思う。自分のなかでも曖昧な記憶があります。また書き記して、別の方の体験とは違うこともあるかも知れない。それらは相互に修正し合うことで、進められればいいかと思います。たとえば、1984年4月25日夜に、京都写真壁において東松照明さんをゲストに、春爛漫浪漫宴会を開催した記録が残っているんですが、この会に高校生のときに参加した記憶を鮮明に覚えている、という、今は京都丹平で二科会の会友という肩書きを持った人に会いました。その企画は私です、と答えましたが、彼の記憶のなかにそのことが鮮明だった、といいます。そうかも知れないと思って、書き進めていこうと思います。
-2-
-写真史-
いま、ぼくは、ぼくが、かかわったところから、ぼく自身のあった行動を跡づけながら、この「写真への覚書」を書いてみようと思います。
関西の写真史、1980年代を俯瞰していますが、顕著になってくるのは、1980年代の半ばに、学びの場があちこちにできてくることでしょうか。既存の大学や専門学校以外に、学齢期を過ぎた大人が学ぶ写真の学校、といえばいいのでしょうか。ぼくが関わるのは、フォトハウス京都が主宰する「写真ワークショップ京都」、その後大阪には「写真塾」、大阪造形センターなどで開催される「写真ワークショップ」等々。アメリカからの輸入で、東京の写真シーンを中心に、1980年代になると、オリジナルプリントという概念が語られ出します。写真プリントを販売するという、ファインプリント制作の方へ、作家の意識が傾いていきます。ファインプリントというからには、美しいプリントをいかにして仕上げるか、ということになります。
関西では、そのような動向を、どこがどのようにして受け入れ、啓蒙してきたのか、ということですが、1980年の初めといえば、伝統的写真クラブが主体でした。全国規模の朝日新聞社がバックの全日本写真連盟、美術団体二科会の写真部など、その関西支部といった組織に集合していく写真愛好家たちが目立っていました。そういった組織には属さない、個人主体の写真愛好者が、点在しはじめ、存在の名乗りをあげてくるのがこのころだと思います。ここではまだ表していませんが、東京の潮流にはメディアがバックになっていたが、関西では潮流があったとしても、それはなく、顕在化してくるのが1980年代、というふうに見ています。
-3-
体験的写真史-1-
1979年12月、ぼくは京都の聖家族というパブの壁面を使って、釜ヶ崎写真展を開催しました。その年の夏には、釜ヶ崎現地で青空写真展を開催したところでしたが、その流れで個展を開催することになったのです。この写真展が話題になったといえばいいのか、当時の情報誌「プレイガイドジャーナル」俗にプガジャと呼んでいた冊子に、その写真展案内をしてもらったところ、それなりに反応があったのでしょう。当時、釜ヶ崎日雇労組の委員長稲垣浩氏を囲んでの座談会を設定し、何十人かの参加者がありました。ぼくにとっては、この個展以前と、個展後で、写真をとりまく状況が変わってきます。
ぼくはいったい何者ぞ、という問いを発するのは、いまに始まったことではなく、1970年代の初め頃、いやはや1960年代の後半から、「自分とは何か」という問いかけですね、これがあったと思っています。二十歳前後当初は、文学に、小説書きに、興味があって、高校三年頃からですが文章を書き出します。ぼくを取り巻いていた外界を書き上げると、高校卒業が1965年、大学進学をあきらめ就職したところです。三年の社会人体験を経て大学生になったのが1968年です。学生運動が意識のなかに色濃くあって、必然的にそこへ入っていった、とはいってもセクトといわれる組織に入るということではなく、ただの取り巻きの一人にしか、過ぎないわけでした。後にはノンセクトラジカルと呼ばれる若者のなかの一人です。ともだちは、学友、クラスの仲間、とはいえぼくが最年長で、22歳になっていました。
若干、学生運動の知識があって、学友たちと話し合っていたと思うんですが、ぼくが影響を与えたのか、後に気がつくと学友たち数名が、後に民青系でない全共闘につながるほうへ、行っていたのです。1968年から1969年2月にいたる学生運動の動向を、京都にいて見聞しておりました。いまにして、ぼく自身が運動の主体を担ったなんてとんでもないことで、取り巻きに過ぎなかったわけです。あやうく警察官による逮捕されそうになったことが数回ありました。が、それを免れ、言葉表現的には無傷で、その後の日々を、送ることになるのでした。1979年12月というのは、それから10年が過ぎている、という意識が強くあったと記憶しています。十年目の証、釜ヶ崎写真展、そのように捉えていたようにも思えます。
-4-
体験的写真史-2-
聖家族の壁面を使って釜ヶ崎写真展を開催しましたと書きましたが、そのときのポスターを複写してあるので掲載します。1979年12月に行なったこの写真展で、その後につながる人たちと知り合うようになります。プレイガイドジャーナルに告知され、座談会への参加申し込みが多々あったなかで、当時テレビモアというビデオ制作グループの取材申し込みがありました。ビデオアートという領域があることは知っていましたが、そのことを志向するグループでした。グループとはいっても岡崎純さん、瀬川恵美さん、この男女二人が中心でした。12月1日からはじまった釜ヶ崎写真展でしたが、座談会は12月9日、続々と参加者が集まる中、テレビモアの二人もやってきました。
パブ聖家族は夜だけの営業で、昼間が空いているというので、ぼくはこの場所の空間で「フリースペース聖家族」という自主ギャラリーを提案し、1980年2月から開設・運営し始めました。いくつかの写真展、演劇パフォーマンス、フィルム上映、ビデオ作品上映、が行なわれましたが、それほど注目されるスペースではありませんでした。当時、自主ギャラリ-が欲しいという若い写真家たちが、かなり、うようよといたように思われていたけれど、この自主ギャラリーに参入するひとはいませんでした。フリースペース聖家族通信を月刊で発行しているんですが、1980年7月に5号を発行しておわりとなります。というのも、このパブ聖家族は、賃貸の場所でしたが、運営者石山昭氏の方で、更新契約の保証金が都合できないうことで、7月末をもっておわりとなったのです。
聖家族通信の延長線上で、ぼくは「映像情報」という月刊雑誌らしき情報誌を発刊します。何人かのグループで始めたのではなく、ひとりで発行し始めたら、人が集まり、グループ化していくのではないか、との思惑があったのです。情報誌の必要性はわかるけれど、中川が単独でやりだしたことだから、いまさら参加なんてできないや、というような心情があったのかもしれません。映像情報発刊と同時期に、ぼくは釜ヶ崎の地で「季刊釜ヶ崎」という雑誌を発行する編集主体となっていました。1979年12月、ぼくの聖家族での釜ヶ崎写真展開催にかさなっていました。この雑誌の反応は、けっこうあったようで、初版3000部はなくなり、総計で1万部ほど増刷したと聞いています。

-5-
体験的写真史-3-
今日のこの記事を書くにあたって、ぼくの体験のどの辺を書こうかと吟味し、そうだ、二科会、関西二科会、京都シュピーゲル・光影会、全日本写真連盟、それらに参加していたころの話を、書こうと思って、写真は、1976年でしょうか1月15日三十三間堂での通し矢行事の一枚を、選んでしまいました。先日、資料を整理していたなかに、関西二科会写真部会員名簿(1977)なるものが見つかって、同時に関西二科展77&79の出品目録もありました。二科会というのは言うまでもないが、全国組織の美術団体です。当時の区分で、絵画部、彫塑部、商業美術部、写真部とあって、写真出展82人の内のひとりでした。2016年現在でもそうらしいが、ここに名を連ねることが地位のひとつだと言うことらしいです。二科会の写真部は1953年創設とあります。林忠彦、秋山庄太郎、早田雄二、大竹省二、の四名が創立会員。そういえば25周年記念の写真集が発刊され、購入して、図書館に置いてあります。
文学系から写真系へ1975年ごろから移動してきたなかで、写真をとりまく環境は全くの無知、情報を得るのはカメラ雑誌で、アサヒカメラ、日本カメラ、カメラ毎日、の新刊本や古書店に並んだバックナンバーからの写真群と解説でした。朝日新聞を読んでいて、社告として全日本写真連盟の会員募集が載って、そこへ個人会員として登録したわけです。職場にカメラクラブなるものがあって、そこへはいって、懇意になった写真屋さんがいて、暗室作業などを頼んでいた記憶があります。最初の展覧会出品は「京都写真サロン」個人会員のコーナーで展示でした。このときはおぼろげながら、写真クラブという集団が多々あって、技術はそこで磨くというような情報を得ていました。オーソドックスに、そういう道を模索して入っていきました。当時は光影会と言っていましたが京都シュピーゲル、これはシュピーゲル写真家協会の京都グループで、主宰者木村勝正氏が亡くなり、その後、名称が変わったということでした。
関西二科会写真部会員名簿(1977)を開くと、関西地区委員長のページがあって、府県の支部長名が住所と電話番号と共に載っています。委員長に岩宮武二氏、大阪支部長古沢和子氏、京都支部長浅野喜市氏、滋賀支部長西岡伸太氏、兵庫支部長堀内初太郎氏、等々の名前があります。先に関西二科展に出展者82名と記しましたが、会員数は200名くらいいらしたのではないでしょうか。ヒエラルキーといえばヒエラルキーで、その頂点に大阪芸大写真学科の岩宮氏がおられた。シュピーゲル写真家協会の会員名簿が手元にないので具体化できないが、棚橋紫水氏や木村勝正氏など、それらの人たちがそれぞれに写真クラブの代表でもあったわけです。朝日新聞社の全日本写真連盟に参加する団体会員は、それらの写真クラブ単位でした。ぼくに即していうと、1977年には関西二科会会員、全日本写真連盟会員、光影会会員、シュピーゲル写真家協会会員にはなれていなくて、二科の本選には合格していませんでした。
-6-
体験的写真史-4-
1977年ごろに撮った写真をスキャンしてるなかから選んで載せますが、これは、信州へ撮影会旅行に連れて行ってもらった時の、霧ヶ峰?高原だったかで撮れた一枚です。ぼくは、いま、特別に、この写真に価値を見出しているわけではないけれど、単写真として、それなりにセンスよい光景かもしれないと思うわけです。所属していた京都シュピーゲル改め光影会には、それなりに関西写壇では名の知れた人たちがおられたようで、新米のぼくは、月に一回の撮影会に連れて行ってもらって、写真を撮るトレーニングを受けたものです。内容は、というと、思想的なとか、内面的なとか、そういう視点で話するということは、ほとんどありませんでした。技術的なこと、露出とかアングルとか、作画といえばいいのでしょう、外面的絵作りのノウハウ、といえばいいのでしょうか。ぼくは、べつに、このことをなんの不信もなく、写真を作るとはそういうことだ、文学じゃないのだから、と蔑視した感覚で対処していたように思います。
写真クラブの人たちから得る情報とは別に、ぼくはカメラ雑誌を読み漁ったと思います。新刊のカメラ雑誌ばかりか古書店の店頭に積まれた古雑誌から、主にはカメラ毎日でしたが、バックナンバーを見て読んで、東京に集中した情報を見ていた。ちがう、違う、写真が違う。写真学校写真ワークショップの話は知っていました。自主ギャラリーがあることも知っていました。後になって詳しく知ることになる「今日の写真・展77」のニュースには、わけのわからない興味がわいてきて、違う写真群を意識しだします。でも、それが、なになのか、どういうことなのか、違和感を覚えるだけで、気分的にはそちらの方に動いているのに、京都では、写真サロン展、関西二科展、日本写真連盟京都支部の選抜展、光影展、美術館や芸術文化会館でのグループ展に出展しておりました。
ぼく自身に転機が訪れるのがそのころです。北井一夫さんのアサヒカメラ誌上で「村へ」の連載があったころでした。自分のテーマを持たないといけないよ、と言われていて、テーマを見いだせなかったぼくは「街へ」をテーマに掲げました。取材の現場は「大阪」、漠然と「大阪」、大阪は都会です。1977年当時、大阪駅の前は再開発がはじまっていて、闇市のあと「丼池」<どぶいけ>と呼んでしたあたりを撮り始めました。その後には天王寺の方へと変わってきますが、思い起こせば記憶をたどっていったみたいに思います。1950年代かもしれない、テレビで大阪が舞台の、けっこうじ地べたのささくれたドラマがあって、そのイメージを求めていったように思えます。その地べたのささくれたドラマに現わされたような、京都の或る場所に、ぼくは育っていたように思えます。無意識に、記憶のイメージを求めていたのかもしれません。
-7-
体験的写真史-5-
京都河原町四条に京都書院があって、二階に芸術書を扱う書棚があって、そこを物色していて見つけた写真関係の本は、名取洋之助の「写真の読み方」、中平卓馬の「なぜ植物図鑑なのか」、東松照明の「朱もどろの華」の三冊でした。二十歳を過ぎたころに、小説家になるには東京にいなきゃいけない、なんていう思いで東京の出版社の社員にならせてもらったものです。1968年の秋から1969年の10月21日まで、有信堂という法律書を出版する会社でした。京都で採用されて東京勤務にしてもらって、東大の安田講堂が陥落した直後に赴任しました。そういった経験をもって、負け組として京都に帰ってきて、放っておいた大学に復学し、結婚して子供ができて、郵便局に勤めていて、遠いイメージの東京の出来事を雑誌で知る日々でした。写真の読み方は貪り読みました。植物図鑑も同様、なんども読み返した記憶があります。のちに東松照明さんと知り合いになるなんて夢にも思っていなかったころでしたが、書店にあった「太陽の鉛筆」は高くて買わなかった本でした。
京都の写真現場と、情報を得る東京からの話題が、ぼくのなかでは混在して、わけのわからない迷いのなかにいたと思います。達栄作さんはぼくが所属した光影会の会長で二科会の会友で、写連の委員でした。知り合って、入会させてもらって、懇意になって、伏見は藤ノ森の自宅へ入り浸ることになります。写真の枠組みといえばよろしいか、写真とは何か、という問題について議論というより会話をしました。達さんが一方的に話されるのでしたが、それは土門のリアリズム、がベースになっていく感じでした。達さんもぼくも写真については模索中。技術的には大ベテランの達栄作さんでしたが、写真論においては、ほぼ、ぼくと同じ立場であったように思います。達さんの後期の写真集「天使のほほえみ」やフォトフォリオ「難民」作品は、そのなかから得られてこられた作品だし、ぼくの「釜ヶ崎」も気持ちの上で達さんの支援があったからだと思います。
1970年代後半といえば、まだビデオカメラで撮るということはなくて、フィルムで映画をつくる。写真制作でいえば、カラーはポジ、リバーサルフィルムでした。家族の記録なんかにはネガカラーを使いましたが、カラーで作品つくりとなるとポジフィルムでした。これは経費がかかるから、いきおいモノクロフィルムを使うことになるのですが、これもまた2016年現在のデジタル環境からいえば、信じられないような現像処理、プリント仕上げ、というプロセスを自分のモノにしなければならない必然がありました。ぼちぼち自宅の一室を暗室にして、モノクロ写真の処理をはじめたころ、名取や中平や東松、そのほかにもカメラ雑誌で知る写真関係者をメディアを通じて知り、京都大阪のぼくの現場では、由緒ある写真クラブ、高嶺の花的存在の全国組織の関西支部などで写真というものを学ぶのでした。

-8-
体験的写真史-6-
この前、1977年の関西二科会会員名簿と展覧会の出品目録を見ていたんですが、その頃のこと、いろいろと思い出すんです。1977年に至る数年間前の出来事の記憶、その後の記憶といったことです。ぼくが得る情報といえば、写真の全体的な状況では、東京発のカメラ雑誌を通じてでした。京都で写真を撮りだしたぼくが、対面でカメラクラブの人たちと交流するほかは、月刊のカメラ雑誌「カメラ毎日」「アサヒカメラ」「日本カメラ」この三誌をかなり詳細に見ていました。月例というのがあったし、撮り方の技術指導みたいなのがあったし、プロのひとたちの写真、アマチュアといわれるひとの写真、写真のことに熱中していく自分への勉強材料ですね。でも、それらの内容について話をする機会は全くありませんでした。そういえばそのころ山本宗男さんがカメラ毎日の「アルバム」の話をされていたのを思い出します。
東京で「ワークショップ・写真学校」が始まったのが1975年、この学校は2年で終わったようですが、その後、受講していたメンバーらが自主ギャラリーを運営しはじめます。1976年3月に「プリズム」、同年6月に「CAMP」同年年8月に「PUT]、それから沖縄でも「あ~まん」という自主ギャラリーが開設された、という情報をカメラ雑誌から得ていました。興味ありました。ワークショップ・写真学校へは、なにかしら行きたいという思いがありましたが、すでに妻子ある身で、それには踏ん切りようもなかったんです。というのも1969年に東京住まいして、気持ち的には挫折して、京都に帰り所帯をもった、ということから数年しか経っていなかったからだと思います。この頃って、写真の表現方法、写真の発表媒体、写真というモノのとらえ方、などが大きく変化してきたのだと思います。変化というより、断絶で、それまであった写真の形と、新しく生まれ来る写真の形、だと思うんです。
カメラにフィルムを入れて、何を撮るか、ということが問題であって、これが本題であって、それ以外のことはその周辺知識でしかない、と思うようになるのは、かなり後になってのこと、たぶん1984年ごろですが、1977年頃って、未分化のまま混沌としていたように思います。誘われるままに、クラブの撮影会に連れて行ってもらって、達さんに選んでもらって、展覧会に出品する。全日写連の月例に行くようになり、入選していきます。巷のコンテストに応募して、トロフィーや賞状や賞品、賞金をもらうこともありました。京都や大阪の大きな写真展には出品するようになっていたから、それなりに知名度があがっていたかも知れません。うんうん、こうして、有名になっていって、センセイと呼ばれるようになっていくんだな、とひそかに思っていました。ホテルの宴会場で開かれる二科会のパーティーに出席して、末席ではあるけれど、偉い先生方と同席することに面はゆい気持ちを抱いたものでした。こんなの、違う、と思うのはそれから一年ほど後、1978年になってからでした。
-9-
体験的写真史-7-
1978年の夏、写真撮影はひとまず置いて、自分のテーマを導くべく、文章を書く作業に入ります。<私風景論-写真以前の写真論->と題された文章です。たわいもない思考の片鱗がここに伺えるかと思いますが、かって文章書きを目指して頓挫してから5年目、久々の文章書きでした。完結はしておりませんが私風景論の一章を1980年に創刊の映像情報に連載させています。大阪は西成区の通称<釜ヶ崎>を取材しようと思い立つのは、私風景論を書き進めているさなかでした。1978年になっていたと思いますが、ぼくは<街へ>をテーマに、大阪を取材しはじめます。大阪駅前の再開発地域から天王寺界隈へと向かったカメラは、飛田経由で釜ヶ崎に遭遇していきます。釜ヶ崎の光景に遭遇して、カメラは出せないまま、撮影を中断させて、夏、文章を書きだしたのでした。
1978年9月2日から始まる大阪日記と題される取材記録を書きはじめます。写真を通じて知り合った人たちが、もう遠くの方にいってしまわれたような感覚を抱いたのを思い出します。写真仲間といえばいいのか、写真クラブの人たちと疎遠になっていく感じでした。恩師であった達栄作さんの家を訪問することもなくなり、それでも月に一回の例会には参じていたようにも思います。というのも、釜ヶ崎の路上をノーファインダー手法でシャッターを切って印画紙に焼いた写真を、例会の床に並べた記憶があるからです。たった一人の反乱、なんてことをどこかに書いたような記憶がありますが、当時、孤立無援、といった感覚に見舞われて、拠って立っている基盤がぐらぐらと崩れていく感覚に見舞われていたように思えます。
写真表現とは何か、という問いかけはその当時から、今に至って、ぼくの中では問い続けている命題のようなものです。どうも時代感覚からして、少しどころかかなりずれているようにも思ってしまいます。この<ずれ>は断層というよりシームレス感覚なんですが、断層のように思えることもあります。感覚優先で、先進的だと思えることも多々あるんですが、時代を切り開くなんてことには及ばないけれど、時代の感覚と密着している、むしろ先行していると錯覚するのも、不確定な要素ばかりだからです。感覚は思想を純化させると思っているところですが、それを具体的にどうなのか、と問われると、タジタジになってしまうんです。状況論ではなくて原理論に傾いていかないと、ぼく自身の思うところが表せられないんじゃないか。そう思ったところで原理を深めていくなんて、時代が要請してないのかも知れないとも思うところだけど。

-10-
体験的自分史-1-
ランダムに、年月の連続を無視して、思いつくままに、自分史というものを作り上げていきたいと思います。ここでの方法はこうだ。一枚の写真を選び出し、その写真から思い当たる出来事などを、自分というフィルターにかけて記述していこうとするものです。1975年の春ではなかったか、大学を卒業して、まだわだかまりを抱いていたメンバーが、文学研究会での文学研究を試みたものでした。
大学闘争が終焉し、内ゲバの時代が表面には見えなくなって、卒業したやつで学校の先生になっていったり、会社員になったり、それぞれの人生を歩みだしたわけだけど、ここにいる三人は、気分的に、まだ物足りなさを感じていたようで、原点に戻って、なんていいながら夏目漱石の研究をするつもりで、週に一遍、北白川の銀閣寺に近い処のアパートの一室で三人だけの研究会が開催されていました。そのうちのひとりがぼく、この写真でいえば真ん中、年齢的にも年長だったと思います。ぼくは27歳になっていたのではなかったかと思う。
白けた時代、白けた感覚、何に価値があって、何に価値がないのか、その判断基準がわからなくなって、まだ戦っているやつはなんだかんだといってもラッキーだったと思います。ノンセクトラジカルなんて総称されていた一人ひとりは、それなりに思い悩み、それなりに人生を歩もうとしていた。のちに団塊世代といわれる男たち女たち。そのころすでにアラブの方へ飛んでいて様々な事件を起こしたりするメンバー、重信とかいった女子が気になっていて、それから40年近くたって、日本へ戻っていて、逮捕されたということとか、その後につながる物語が、今もって浮上してきたりします。田舎町の掲示板に指名手配書が貼られていて、まだ終わっていないことを露わにされて、それらを見た時には、自分のその後の何十年かを一気に早回しして思ってしまう。
-11-
体験的自分史-2-
いつ頃からものつくりすることに興味を覚えたのか、具体的には17歳になっていた高校二年生の秋だったかに詩集を作ろうと思ったのです。吹奏楽部を立ち上げ、文化祭を終えた後だったかも知れない。かなり寒い日々の記憶が甦ってくるから、きっとそれは秋、そのころではなかったでしょうか。時制を合わせるために記しておけば、この年の11月23日だったか、ぼくは早朝に嵐山の嵐電駅前に立っていたとき、ケネディ大統領の暗殺を告知する新聞の号外が配られていきました。この年は1963年、ぼくの詩集の名は「そなちね」、その第一号でした。詩を書き出していて、それをまとめたものです。ガリ版刷り、たしか一枚一枚、謄写版刷り、まだ輪転機ではなかったと記憶しています。高校の生徒会室にあった謄写版です。
文章を書きたい、詩から始まって散文を書こうと思いだしたのが、高校三年生の時ではなかったかと思う。祇王の物語を、小説として書きたい、そう思っていたのを思い出します。というのも嵯峨野の祇王寺を訪れて、詩を読み、そうして清盛に寵愛されたという白拍子祇王の運命を知って、かなり感動したように思うのです。ええ、そのときには、好きな女子がいて、強烈に思いつめる恋心でしたが、成熟しないことに苦しみ悩んだ、若きウエルテル、プラトニックラブなんて言葉を知ったころです。たぶん、深い意味での初恋だったと思っています。高校生活を通じて、その女子だけに惚れて、何度か話をしたりして、ぼくの思いを知ってくれているのに、交際にまでは至らせてくれませんでした。
詩を書くことが、それから50数年経った今、ブログに分散させながらフィクションしているわけですが、原点はそのあたりにあったんだと思うようになっています。文章を書くことは、まったく苦にはならなくて、書き流しばかりだけれど、かなり流暢に書いているなあと、われながら思うところです。そうですね、読書遍歴を記しておかないといけないな。高校2年ごろまでは詩集が多かった。アポリネール、リルケ、日本では朔太郎、藤村、啄木、宮沢賢治は読まなかったです。小説は、といえば白樺派、高踏派、外国モノではゲーテでした。日本の作家が多かったように思います。高校生のころ、まだそれほど多くは読まなかったけれど、衝撃だったのは「されどわれらが日々」、この年の芥川賞作品で、夏休みの日、文芸春秋を買って、一気に読みました。衝撃でした。同時代の現代文学に触れた最初だったと思います。



