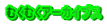
最新更新日 2016.12.28
写真への手紙/風景論
風景論
中川繁夫:著
seesaa blogに連載の文章
風景論
1~12 2016.9.1~2016.11.5
-1-

遠い遠い昔、人類が誕生する前から、この地球が存在している、ということを我らは知っています。我らというより私が知っている。どうして知っているかと言うと、それはひとえに教えられたから、あるいは学んだから、に他ならないわけです。ここで私が風景というとき、その風景の範疇は、なにもいまめのまえに存在する物の組み合わせだけではなく、空想の、あるいは想像の、光景も含めて、イメージとして存在させることにあります、と仮にそのように言っておこうと思います。
生きている人の頭脳の中といえばいいと思うけれど、そこにあるイメージ像は、実は冩眞として存在させることができるほか、冩眞ではなくて、絵で描く、コンピューターで描く、等々、現実に存在しないものまで、イメージ像として見せられるのが現在だと思います。でも、ここで私が使うイメージ像は、カメラで撮られた外界の光景をもって、イメージ像、つまり冩眞として呼ぶところの物なのです。実写の静止がといえばいいのか、基本にはカメラで撮ったイメージ像をもって、冩眞。その表されたものを風景と言おうと思います。
ここに使った冩眞は、食べ物です。ある宴席で出てきた食物です。風景論と名付けた写真集の冒頭群の一枚です。野菜サラダ。このイメージ像がどうして風景なのかということから、始めなければならないと思う。俗に風景といったら、自然の風景、それをアレンジして、芸術風といったようなテクニックを駆使して、作者は見る人に感動の気持ちを起こさせるのだと思います。としたら、野菜サラダをもってして、風景、だなんて当てはまらない。このように固定概念では、そうなのだけど、ここで、翻って、あらためて風景とは何か、問うところです。
-2-

大阪市西成区、あるいは西成といえば、ひとはなにを思うのだろうか。1978年の9月はじめ、このときから1979年8月まで、私は、このときの取材の模様を「大阪日記・釜ヶ崎取材メモ」として書き残しています。その前の段階で、私風景論、という覚え書きのような試論を書いていて、その後に発行する個人誌「映像情報」にその一章を連載しました。風景論というタイトルで写真集を編みだしたところですが、当時から「風景」という二文字に惹かれていた、というより論の中心テーマであったように思えます。
日本の社会風景のなかで、その地の心象イメージは、遠い昔の、たとえば万葉集が編まれたころの、人々の心象に繋がるように感じられたのです。原野、といえばいいか、心のなかの深~いところにある混沌。むずむずするうごめきのような呻き声、とでもいえばイメージしやすいかも知れない、そんな感じ。地理的には大阪から堺へ通じる街道の出入り口。いまでいうなら都市と田舎を区切る境界点のような場所。逃散してきて、都市へ流入できなかった人民が留め置かれた場所。私には、日本の原風景が、この地の磁場であるように思えたのです。
ここに掲載した写真の建物が、いま、取り壊し議論がなされていると聞きます。大阪社会医療センター、あいりん労働公共職業安定所、その奥には高層の市営住宅がある建物です。老巧化、耐震構造になっていない、などの理由かと思いますが、昭和の時代から象徴的な視覚イメージとして存在してきた建物が壊される。このことは記憶の喪失を招いていくものだと思います。風景を見て、その風景に心象をかさねるとき、その人の記憶に、その心象がかさなります。風景と記憶の関係です。
-3-

切り取るイメージには、私の記憶に基づく思い入れがあります。この思い入れの程度を計るなら、かなり重たい思い、あるいはどうしても忘れられない事があったという記憶。私の内面、その深いところで感じる場面、とでもいえばいいのか。内面を構造的に捉えるとしたら、それは球体のボックス、ブラックボックスなのかも知れない。なにか事あるごとに思い浮かび、そうして私の内面を揺すってくる感情の源泉であるように思えます。近年は、この「心」というものの解明を、様々なジャンルで行なわれてきていると察しています。「心とは何か」吉本隆明がこんなタイトルの本を書いていたのではなかったか。吉本隆明といえば「言語にとって美とは何か」1950年代ごろの著作ではなかったと思うが、私の内面には、その言葉、文字列が深く刻まれています。
ここに掲載の写真は、釘抜地蔵境内、この釘抜きを人に見立て、自分が病む身体の箇所を撫でさすり、その手で自分の身体の箇所を撫でさする。ぶつぶつ呪文のような言葉を紡ぎながら、身体の健康を願い御利益を求める。この釘抜きの向こうにあるのが本堂で、このまわりをぐるぐると回る。願掛けと言っている行為で、最初に握った竹のへら棒を一回まわるごとに一本を戻していく。私は、信心深くないから、そのことを少年時代からやったことはないのですが、願掛けしているご婦人をまま見かけます。信仰心という心のあり方、いつのころからここでその行為が行なわれてきたのか、場所は京都、千本、今出川を上がったところにあります。石像寺という浄土宗の寺です。
私が生まれ育ったのは、京都の北西部、西陣と呼ばれている地域ですが、その端の端、御土居に接した処で、洛中洛外に分けると洛中側です。見慣れた風景。たぶん自分をつくる精神風土を、この場所で培ったと、言葉のうえで言えます。問題は、この精神風土ということの、つくられた人の内面、そこにある感情というもの、です。人という構造のなかの「情」というものと、この内面の情と視覚として得るイメージ「像」との関係といえばよろしいか。写真表現のイメージ作業は、個人としての情、心の揺すられ方、に関連しそうな気がします。私と私を取り巻いている風景。たまたま私は、生まれ育った地域に、いま現在生活を営んでいます。風景論は、ここからはじまっていくわけです。
-4-

大阪はミナミの法善寺、西向不動明王の像、苔むしています。三十数年ぶりに立ち寄り写真にしたモノです。こんな苔をまとっていたかなぁ、私は、その姿に、驚くばかりでした。というのも、ここを訪れたのは1982年か1983年、夏の頃だったかと記憶しているが、それ以来ですから。夜で、善哉のの店で善哉を食べました。彼女の告白は、私とは別の男と関係しているということでした。私は、終わった、と思った。それ以来、彼女とは会わないまま30年ほどが過ぎて、再会したのです。そのときの別の男の子供ではないが、二人の母親になっていて、女子二人は成人でした。
夫婦善哉は織田作之助の小説です。太宰、安吾とともに無頼派の作家として区分されている小説家です。森繁と淡島千景が演じた映画を見た。小説は案外短編であった記憶で、読みました。夫婦ってゆうのか、男と女というのか、人情っていうのか、男と女のどうしようもない関係です。男にとって女は、魔物であり、人生を狂わせてしまう。魔物と見るか普通とみるか、狂気と思うか普通と思うか。生きることのなかで、この関係というのが主題であって、それが生きることの底辺を形成する感情だと思う。私は、なによりもこのことを優先させる生き方が、今の時代の生き方ではないのか、と思うところです。
男と女がいる風景。こころのうちがわの感情を、イメージにして表現できないか。これがテーマですが、なかなか、言葉で概念するのはできるけど、具体的なイメージとしての像を結ばせることは、難しい。いまのところ難しい、との思いが立ちのぼってきます。願掛け不動さん。拝み倒せば願いを聞いてくれる。私は、その心を信じるわけではないけれど、これは、そのことを信じようとしなければ生きていけないほどには切羽詰まっていないからかも知れません。こころの風景。それは行為によってそのこころが見えるのだろうか。他者に伝わるのであろうか。共有できるのであろうか。
-5-

2016.7.31、この場所は阪急電車の梅田駅の改札口へあがる前の広場の一角です。なにやらのイベントが行なわれていて、女子がならんで作業をしているところです。人が集まり、その人を見る人がいて、その光景を記録する人がいます。その記録した人がいたから、ここに、こうして、画像を載せることができている。ここは、ブログというネット上のツールのなかです。パソコンやスマホの画面で、この静止画を見ることができる。もうあたりまえになってしまって、考えることなく使いこなしている道具のなかに置かれる画像です。私はここにこの画像を表したけれど、こういう行為はいまやおびただしい人がおびただしく行なっている行為の一つに過ぎないわけです。
あっ、とおもう人がいるなら、それはここに写った自分がいるとか、知合いが写っているとか、そうでなければ、あっ、と思うことの原因は何なのか。この提示された写真の価値をいうなら、いま、意味づけるほどのことがない、無価値、ということになろうか。私は、私が撮って、私が選んで、私が発表したこの写真について、風景論と名付けた枠組みの中の一枚として提示しているから、風景論を構成するパーツであるわけです。写真イメージの作り方、道具はiPhone6のprocameraというアプリケーションで撮っています。撮ってその場で編集をして、この画像のような色画面に処理して保存していたものです。このiPhone6で撮った写真は、パソコンにアップされてきて保存されていきます。写真はこうしてつくられ、人の目に触れさせることができるのです。
こうして人の目に触れさせること、このことが何を意味するのか、ということが問われなければならない事だと思います。写真イメージを言葉でなぞっていくことへの良否ですが、私は、この言葉でなぞることは、余り感心していません。写真イメージは、それ自体として、存在すべきものであって、そこに言葉を付け加えることではない。言葉によって語られるべきモノではなくて、それイメージ単独で、見る側の言葉ではない処で情動を起こさせるべきもの、という基本概念を敷いています。言語と対置する言語ではないイメージ像としてのパッションといえばよろしいか。言葉に従属しないイメージのモノであるべきだと考えているところ、ですが、このことじたい言葉に従属しているといえる矛盾をはらみます。
-6-

2016年9月のある日の午後に撮った街角の風景です。具体的にいうと、この場所は阪急電車茨木市駅の前の風景です。見る人には、だからそれがなんだっていうんだ、との声が帰ってきそうです。また、たぶん、ここに載せられた意味がわからない、とか、ここから意味を読み取れって、独りよがりだよなぁ、なんて声もあると思います。つまり、たぶん、私は、この写真で他者とコミュニケーションしようと思っても、その真意が伝わらない、と思われるのです。にもかかわらず私は、風景論というタイトルの写真集の、12枚中の一枚として選んだということなのです。私が、私への記録として、この光景を顕著にした意味は、私の古い記憶に基づいていて、そこに私自身の回顧録的な意味がある、それだけです。次には、これから誘発される記憶を書き記してみようと思います。
私には暗い夜道の光景が記憶としてよみがえってくるのですが、道ばたの屋台で、とん平焼なるものを食べたこと。ああ、冬だったかな、寒かったな、先輩の小林さんと一緒だったな、1966年の出来事です。高校を卒業して十字屋楽器店に就職して、私は、ピアノを習いだします。バイエルの最初からでしたが、週にいっぺん、茨木駅近くに十字屋の支店があって、そこでレッスンを受けていたのです。19歳のころ、二年間、毎週のように通ったと思います。音大へ行こうと受験のためのピアノレッスン、音大の入学試験の必須科目でした。作曲とか指揮とかやりたい夢物語ですね。ただ、音大受験という無謀な試みは、受験するに至らないまま、興味は文学の方へと移ってきました。
思い起こせば、その当時に買ったレコード全集と文学全集があります。現在、大阪国際メディア図書館に置かせてもらっていますが、レコード全集は、シュナーベルが弾くベートーベンのピアノソナタ全集、エンジェルレコード赤盤というやつ、二つの箱入り。これは、十字屋楽器店に勤めた最初の給料をはたいて買った、つまり社会人となってもらった給与の最初、その記念品です。文学全集は、谷崎潤一郎全集、最初にもらったボーナスをはたいて前払いで買った文学全集です。ここまでの記念品を図書館に預けて、世話になっている図書館を辞めるという思いで、シャッターを切った、記録されたイメージが風景論の一枚に使わせてもらった。ここに、こうして書き記せば、なるほど、そういうことか、と納得されるのかもしれないけれど、これは写真表現という観点からいえば、失格です。現在の処、失敗作だけれど、風景論を書き終えるころには、意味を持って浮かび上がってくるかも知れない。
-7-

金沢2016.9.22。彼女の実家の仏壇をiPhoneで撮りました。この仏壇は、浄土真宗の檀家のものです。仏間があって、仏壇があって、それはそれは立派なつくりです。この風景、ぼくには、ここに、日本というイメージを構成する典型的な風景があるように思えるのです。風景とは何か、といったような問いかけをして、内面イメージを表出する手立てとしていきたいと思っているところですが、言葉よりも画像イメージを優先させ、画像イメージを羅列するだけで、そのイメージを構築できないか、との思いもあるのですが、こうして、そのことを定着させるために、このような論を書いているわけです。
書くこと、書かれることから独立させようとして、文章を書く。なんと矛盾に満ちたことだろうか、と思うのです。画像イメージが言葉から解き放されることが可能かどうかを探るためのディスクールだけれど、結局、言葉に服従してしまうようにも思えます。最初に言葉ありき、なんてことが言われますが、この定理を覆したいと思っているわけです。どうして、こんな作業をするのか、といえば、画像イメージを言葉から解き放つため。なんのことはない、ふたたび、元に戻ってしまいます。ということは、このような論建てが不毛なのかもしれません。画像イメージと言葉は、切り離せないものだというところから始まって、つけられる言葉の中身を吟味すればよいのだ、と結論を導けば、これまで通り、それでいいのかもしれない。
たぶん、このような発想、つまり、画像だけで風景が独立していて、言語の代わりというか、新しい言語の体系になる可能性の問題です。あの、来たるべき言葉のために、なんて言った中平の真意は何だったのか、言葉に対置されるべく画像イメージを想定したのではなかったか、と今更ながら思うわけです。文章で連ねられたものを文学というなら、画像で連ねられたものをなんと呼べばいいのか。像学、うんうん、二文字なら、文に対置して像、ということでいいのかも知れない。文書学といってくれれば映像学という名称で、すんなり対置できるんですけど、ね。来たるべき言葉の代わりになる映像のために、と置き換えて、考察を進めていくのがいいのかも知れません。
-8-

京都 2016.9.25。いや、風景とは何か、なにを意味するのか、という問いかけを発して、何をしようとしているのか。なんだか徒労のような気がして、空しい気持ちになってしまうんですが、かって写真とは何か、と問われて、写真は写真だ、なんて笑い話のような回答を導いていた写真作家がいたように記憶しています。この写真は写真だということで封じ込めていたその内面を、解明していこうとしているのが、いま、ここでいう風景論、なのではないか、と思ったりするのです。そんなこと考えたって無駄だよ、写真は写真だ、でいいのではないか、と執拗にその内面へ降りていこうとすることを拒まれてしまいます。
静止画である写真を含め、映像は目で見て感じるモノだ、と思う。じつはこれで結論だといえば結論でしょう。つまり、言葉ではない、文章を解析してイメージ化する代わりに、直接イメージなのです。だから、映像は理屈じゃないのかも知れない。理屈ではないインパクト、ある種の衝撃を与えるものであれば、成立する。言葉を介在させないで、観たときも、観たあとも、言葉を介在させないで、それだけで終わる。そういう文脈でいいのかも知れない。でも、言葉を介在させない、前意識にも、後意識にも、言葉を介在させないで、画像だけでいい、ほんとにこれでいいのか、未来人よ。つまり、現在人は、言葉を必要としているけれど、次第に映像が独立していき、現在の言語を崩していくようになるのではないか。
人間が、言語でもってコミュニケーションするようになって、どれくらいの年月、時間が経っているのだろうか。意思を疎通させるための言語ですが、何万年かを経ているのでしょうか。その末裔のいま現在、言語の発展系で映像によるコミュニケーションが可能になっていく、という仮説は立てられないものでしょうか。幼児性といえばよろしいか、言語をまだ使わないけれど、感情がある。猿や犬猫なんて、感情があるじゃないですか。人間は犬猫レベルになって、言語を使わなくて、生活が成り立たせられるようになるかも知れない。なんだか、奇想天外な発想をしているように思えて、これをブログ記事として発表する自分は、発狂したのではなかろうかと、心配されるむきも在るかも知れませんね。なんせ、脳みそがとろけだしてくる年齢でもあるようだから。
-9-

写真は、なか卯の卵焼き定食の、卵焼きをご飯にのせ醤油をかけた図。今時流といえばよろしいか、街中で食事をする場所があって、近年では24時間営業していて、何時でも食事ができるという体制になっています。これって、実は、そんなに以前にはなかったことで、現代の食生活のひとこま、象徴的風景、と言えるのだろうと考えるわけです。とくに牛丼チェーン店では、朝の定食メニューを用意していて、いくつものメニューがあります。ぼくは、朝早くに集合がかかる日に、ここ数年、このメニューを食べる、一番安いセットです。安いとはいっても、お金がないと食せないわけだから、貨幣経済のなかの食文化の一端、といえます。
写真のテーマに食をあげ、具体的な撮影として、まま自分が食べるときの食を記録し、羅列する、ということを写真家の仕事としてやっています。家庭料理のこともあれば、そこそこ高級料亭での会食内容であったりします。日本における現代食文化の考察、なんて仰々しくは言いたくないけれど、目論見はそういうことです。風景のなかに、自然風景と社会風景が区分けられるとしたら、食の風景は社会風景の範疇です。できあがっているモノ、そのまま人が食する直前の姿が、そこに記録され、羅列され、その背景を彷彿とさせる。食の領域はとっても複雑です。生産者、捕獲者、原料となる食材の在処が話題になります。それら食材が組み合わされ、経済活動の真っ只中で、それらは存在します。生きることの社会風景が、そこに現れてきます。
ぼくの写真集<風景論>に表すいくつかの系を説明しておこうと思います。一つの系は神社仏閣での光景があります。一つの系は街角の光景があります。一つの系は人そのものの光景があります。また一つの系は食です。一つの系は日時、年月日や文化状況などが確認できるポスター類です。それからここでいう、風景と光景の使い分けは、風景とは広い範囲、光景とはピンポイントな範囲、とイメージとして分けています。その根底のところには、人という存在、人と書けば二人が支え合うといったイメージなので、ひと、とひらがなで記述する、単体としての<ひと>の内面、外面、感性、理性、それらを揺らがせながら構成できないか、という写真表現の試みです。ある特定の出来事を背景にして、その出来事を表出させる、といった構成はとりません。一つの系にまとめていくという手法はとりません。それから撮影機材はiPhoneのカメラ機能です。撮影とエフェクトといえばよろしいか、色、明暗、それをイージーに変換できる現在のスマートフォーン、アイフォーンで撮っていきます。
-10-

京都から大阪へ行くときには、ぼくは阪急電車を使います。阪急電車よりも京阪電車に乗ることが多かったので、いつのころからか阪急電車に乗って大阪へ行くことを、都会へいくときのスタイルにしたいと思っていました。こだわりといえばこだわりで、別に京都から大阪へいくのに、どちでもいいようなものですが、妙にこだわりがあるんです。そのこだわりですが、ぼくのどこに起因しているのか、思い起こしてみることが多々あります。都市の風景論でいうと、京阪電車の路線から見る風景は、どちらかといえば庶民的な感じがしているのです。そういうことでいえば阪急電車の路線から見る風景は、どことなくかっこいい、素敵な生活を思わせるような感じがするのです。
1970年、大阪万博が開催されます。この年はぼくにとっては記憶に残ることが多々あった年です。なにより結婚した年、24歳の誕生日を結婚記念日としたぼくは、郵便局に勤め始めたところでした。当時、国家公務員だった郵便局で、前年の秋、東京暮らしから京都に戻ってきて、新聞の求人広告で伏見郵便局の臨時補充員となったのです。郵便配達、運転免許をもっていたからスクーターに乗って速達とかポスト開箱とかの作業に従事、郵便内務のしごとから、貯金課の窓口担当となったのです。定職にありついたぼくは、結婚する名目が立ったという思いでした。通勤は京阪電車に三条から乗って丹波橋で降りる、帰りは丹波橋から乗って三条で降りる。このことの繰り返しが、日常の流れを形成することになるのでした。
京阪電車ではじまるぼくの、およそ20年間の記憶は、国家公務員という立場で、後半5年間は管理職として転勤族になりますが、あまり思い出したくない記憶のことでした。淀川をはさんで対岸にある阪急電車への、憧れ的な感覚は、閉鎖された感覚が、阪急電車なら神戸や宝塚へとつながっているという、ぼくのイメージ上でのかっこよさ、万博の会場につながっていたイメージの阪急電車へのあこがれになっていたのかもしれません。たぶん、ぼくの屈折した内面が、すばらしい生活を具体化するような団地生活イメージにつながっていて、目をあげて見るあこがれの気持ちにつながっていたのでしょう。
-11-

写真は地蔵院(椿寺)の鍬形地蔵尊です。この地蔵尊は、京都の一条通り紙屋川の橋を渡ったところにある椿寺の境内にあります。地蔵さんは庶民の信仰対象です。いまでこそ科学の世の中、医学においても西洋医学がそれなりに発達し、病に対しては信仰で治すということも行われなくなったと思います。でも、この傾向は、そんなに古くからあったわけではなく、たぶん、ぼくの祖母なんかは、地蔵尊を拝んでそのご利益をいただくといった類だと思うから、まだ半世紀前には、ごく日常の中にそういう信仰があったと思われるのです。失われた精神とはいわないが、戦争が終わって71年。戦後の教育からは宗教色が消えていて、それはそれでいいことだったとも思います。ところが、はたして、それでよかったのだろうか、と思うことが最近多々あります。心の風景から信仰が消えているように思われてならないのです。
ここの表題は「風景論」としていて、風景についてあれこれ詮索しようと思っているところです。とはいうものの切り口が見出せなくて、のらりくらりの文章になっている感じで、読む人にはわかりずらいだろうな、と思っているところです。ひとりよがりといえばひとりよがりで、独断と偏見なんて言い方しますが、まさにこれにも当てはまらなほどのレベルなのかも知れません。まあいい、かって1970年代の後半、ぼくは「私風景論」というタイトルで、サブタイトルに「写真以前の写真論」とつけた文章を書いた記憶があります。その文章も「映像情報」に第一章だけを連載しています。第一章だけしか書けていない中途半端なものです。これを今もって引きずっているわけで、結局、内面の問題だから、まだまだ論及されるべき未来の領域なのかとも思うのです。
近代、モダニズムという時代になって、個人のなかで、外面と内面、という区別ができるようになってきた、と言われている。自我という問題、我思うゆえに我ありの我、この問題がようやく一般に語られだすのは、ぼくにとっては1970年代になってからではないかと思うのです。先人、哲学者のパスカルが言ったとしても、それが大衆一般レベル、つまりぼくのレベルにまで流れてくるのは、漱石を経て、坂口安吾とか太宰治とか、あるいは高橋和巳とかを経て、その末端としてのぼくではなかったか、といま思うところです。実は、内面問題について、ぼくは誰とも会話・議論したことがありません。本を読んで、たとえば柄谷行人氏の文学評論なんかを読んで、そのように思っているところなのです。でも、前述私風景論は、文学批評上での展開を知る前でした。そうですね、サルトルとかカミュとか、実存主義って言われていた哲学潮流の末端だったのかも知れません。
-12-

紫式部といえば源氏物語を書いたという作家・小説家さんですね。その方のお墓があるんです。墓石はあるけれど、まさか、骨壺が埋まっているわけではないと思うんですけど、ここが墓であると書かれていれば、お墓だと思うわけです。謡曲に雲林院というのがあるらしくって、そのなかに紫式部のことが書かれている、というのです。そうそう、雲林院というのは、千年ほど前のそのころ、大きな敷地をもった寺院であったとか。現在の大徳寺の敷地は、もともと雲林院の敷地だったとか。大徳寺の東側、南北の道があります。雲林院は北大路とその道の角っこにあります。そのまえの通りを紫式部通りというんだといっていた人がありました。
話は変わりますが、牛若丸と弁慶の話しですが、京の五条の橋の上、とかいって牛若丸が弁慶とたたかう場所、じつは、この五条というのは御所のことで、紫式部通りには大きくはないけど川があって、そこに橋が架かっていて、牛若丸と弁慶がたたかったのは、ここ、この界隈だ、という人がいるんです。このご近所の普通のおじさんが、そういう離しをしてくれました。そういえば、大徳寺の北に牛若町という地名がって、牛若丸が育った場所だそうです。風景論、目に見える光景だけではなにも語らなくて、過去に書かれた文字、文、文章によって想像力が逞しくなるようです。文字とイメージ像が一体化することで大きな膨らみとなって、そこに感動する心が生じてきたりするのでしょうか。
数年前に源氏物語千年紀という行事があったのを思い出します。千年なんや、とその時間の長さを思います。100年が10回、50年なら20回、繰り返してきた時間です。で、平安京、794年に遷都だから、それから200年ほど経って、紫式部の源氏物語が生まれる。この墓の右横に小野篁の墓があるんです。詳しいことはわからないけど、夫婦やったんかなぁ。千本焔魔堂には紫式部供養塔なるものがあって、小野篁の像もあったように思う。小野篁ってあの世とこの世を行き来したと言い伝えられてる人ですよね。あの世とこの世を行き来する。そんなことはありえない、ありえないけど夢の中ではありえて、イメージとしてあの世とこの世があるかぎり、心象のなかで行ったり来たりという感覚はありえると思えます。











