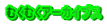
最新更新日 2012.5.26
現代写真の視座・1984
-ドキュメンタリー写真のゆくえ-
中川繁夫:著
私性の解体 追録
<私性の解体>1
「Provoke」の破産は、中平卓馬みずからの言葉によって、総括されました。
すでに見てきたように、「Provoke」は1960年代の後半、
あの政治的季節に、写真手段をもって自己解体を希求しました。
まさに時代そのもののなかで呼吸する写真家たち。
中平卓馬や森山大道や高梨豊らの写真行為は、「VIVO」の写真家たちとは異質な、
表現の方法と領域をもってその時代に存在しました。
「Provoke」が創刊される1968年は、フランス、パリの五月があった年。
日本においては、学生の意識が高揚し、制度解体、自己解体を叫んていた年。
反体制という言葉が飛び交い、それまでの制度のいっさいを葬り去ろうとしました。
既存文化、思考方法の変革、革命的要素をも帯びていました。
そのような高揚の時期に発刊され、1970年を越えることによって、
自己批判しなければならなかった写真家たち。
中平卓馬は「記録という幻影」のなかで、次のように書きます。
「実は一枚一枚の写真は、私が生きた生の痕跡であるにすぎないという断定には、
見ることを生の体験のすべてか、すくなくともその主要部分だという思い込みがあった。
だがわれわれの生の体験ははるかに全的なものであり、
むしろ身体的なものであることは自明である。
むしろ写真家にとって残された一枚の写真は、
みずからの生の疎外形態だと言ったほうがはるかに適切だろう。」
<私性の解体>2
中平卓馬の文を引用します。
「写真は記録であるという断定には、
記録であるからにはどうであれ、
それを見る他者との間に不確定ながらも、
あるコミュニケーションが成立するはずだ
という信仰があったに違いないのである。」と、
また次のようにも言います。
「Provokeのめざしたものは、写真家の肉声ということであった。
それは既存する美学や価値観による制度的に整序された視覚に対する
肉声による切り込みであったはずだ。」
(中平卓馬・記録という幻影)
「Provoke」の写真家たちがまき起こしたセンセーションは、
確かに写真制作の流れを大きく変えてしまう素地を持っていたと思います。
森山大道の写真集「にっぽん劇場写真帖」の時代。
反米闘争、大学闘争、新宿騒乱があった時代。
吉本隆明の「共同幻想論」が読まれた時代。
それまで持ち得ていた写真の美学や価値観を、
みずからの肉声によって切り込んだ中平卓馬らの作家たち。
そのことによって写真は、その時代の、写真の肉声を獲得したのです。
もちろん、その時代、写真だけが揺れ動いたのではありません。
既成の価値軸上のあらゆるものが、根底から問われていたのです。
1960年代後半の時代は、戦後民主主義といわれていた形態が、
理想から形骸化してきたなかで、既成の平和運動や民主運動が、
問い直され、見直され、行動化されたのでした。
その一環として、写真もまた、行動化された、といえるのではないでしょうか。
<私性の解体>3
カメラのブレとボケ、俗にブレボケ写真の手法によって、
引き起こされる写真メカニズムの解体は、
それ自体写真史上に特質されるべき質を有していたと考えます。
まさに1960年代、その時代、既成価値へのアンチ・テーゼは、
荒々しくも写真をとりまく世界に吹き込んできました。
自己解体の行動様式は、まず内なる風景の解体をめざします。
自分の中の価値観を、自分によって浮き彫りにさせる作業です。
政治の諸政党・党派が打ち出す戦略戦術を越えて、
若い世代のパワーが爆発しました。
そうした状況を背景として、
写真は写真独自の視覚を獲得しようとしたのでした。
でも、しかし、その後の認識からいえば、そのこと自体が破産したといいます。
写真の新しい価値軸の中心としては、成熟しなかったのです。
たとえ、その表現方法において、根強い支持があったとしてもです。
心情的には、それらの写真群が放つイメージを共有できるとしても、
それは私性の露呈の極みです。
写真による表現は、より社会性を獲得しようと模索されてきます。
それらの写真が写真として、それ自体がインパクトを放つとしてもです。
社会性と私性という範囲、それを包括する枠を想定して、
その範囲で写真を語るとすれば、既存写真の意味が解体された結果として、
私性が前面に出たのだといえます。
<肉声の獲得>1
写真が「見る」という主体を獲得するのが、
東松照明の1960年代の作品群であるとみるならば、
写真の現代は、ここから始まります。
写真が肉声を獲得することとは、そこに写真家としての作家主体、
「見る」ひと(作家)の生きざまが、明確に刻み込まれるということです。
そしてそれは少なくとも、社会的関係の中において、
という限定つきでなければならないのです。
「Provoke」の作家たちに贈られた絶賛が、
私性の露呈という極論においてであったとするなら、
写真行為する形態は社会性を帯びていたとしても、
繁栄する時代を撮るとか、人間ドラマを撮るとか、
写真自体の中には、社会的を持っていたのではありません。
写真が、外へ向けてのテーマ性を持ち得なくなったとき、
感性の世界の中にのみ、コミュニケーションを成立させようとしました。
彼らが成したことは、内的風景を顕著にさせていくということ。
これは、あらたなる風景の発見、ともいえる写真群であったのです。
写真におけるテーマ性の欠落は、
論理的方法よりも感性に訴える日本の私小説的な気風、
つまり感性にゆだねる世界表現となってくると思われます。
日本の自然主義文学は、西欧からの移入によってその方法を学んできました。
その結果として来ついた場が、論理構造を希薄にした私小説の系譜となりました。
写真もまた、日本の特質として、私写真へとたどりついたのだと、いえるかも知れません。
<肉声の獲得>2
写真同人誌「Provoke」の写真家たち、
中平卓馬や森山大道がめざしたものが、何だったのか。
ともあれ、既存の方法を打ち破って、独特の画面を作りだしました。
あたかも内面の叫びとでもいうようなイメージです。
ぶれてぼけて、アレブレなモノクローム写真です。
としても、花鳥風月のバリエーションのようにも見えます。
写真とは、作家内面の感性が作り出す代物です。
視覚による記号です。
直観的です。
だから、私的なまなざしを、私的に提示すること、それでいいのか。
写真が本質的に持ちうる指示性、記録性、これをどう扱うか。
いまいちど、振り出しに戻して、写真表現とは何か。
写真が写真家自身の肉声を獲得するには、
写真家の行動様式の組み替えを必要としました。
1960年代は、これら写真家自身の行動様式が組み替えられてきた時代。
東松照明に始まり、森山大道に終わる1960年代です。
写真を背景とする世界観は、絵画の文脈から、文学の文脈へ。
日本の写真表現が、旦那芸から大衆のものへ。
そこには、写真を支える文脈が、必要とされます。
写真と文学との交差点、これが「provoke」ではなかったか。
<肉声の獲得>3
1960年の日米安保条約改定から東京オリンピック開催を経て、大阪万博に至る十年。
日本、1970年以降、世の中は、
高度経済成長の名のもとに、物質的に豊かになります。
この高度経済成長の波に乗って、コマーシャル系写真が拡大してきます。
ものを売るための、無秩序な、それ自体意味を持たないような世界を拡大してきます。
見方を変えれば、新しい波は続々と表出してくる時期でもありました。
いつの時代や時期においても、表現の諸相は、
他のジャンルのそれと密接な関係を持っています。
それらの総体として、その時代の精神を具現化します。
写真における私性の獲得は、おおむね東松照明によってなされたと記しました。
そこには私性と同軸に、社会性、テーマ主義といった内容もはらんでいました。
ところで東松照明のあとに続く作家たち。
ここの論でいえば「Provoke」の作家たちとその後の作家たち。
私性の突出を試みるそれら作家には、
むしろ社会性やテーマ主義の排除が見られます。
これは写真それ自体の中に、
被写体が持つ社会性やテーマによる制作を、
より私の側に引き受けて、
そこから出発するということに由来します。
<肉声の獲得>4
1960年代から70年代、その時代、サロン写真といわれた写真からの解放、
ルポルタージュや報道写真といわれた解説的写真からの解放は、
その時代が何よりも自己表出の時代であったことによります。
かってあった大きな装置としてのカメラが、軽量化され、オート化されてきます。
そのことによる、カメラが写真家自身の身体の部分と化したかのような方法論です。
こころゆさぶる表現の方法は、あたかも身体的揺れを実感させます。
社会における写真の使われ方は、商品説明とか旅行地とか、多岐にわたります。
それら写真の総体のなかから、読者を獲得しだす写真表現、つまり作品制作にこだわります。
「Provoke」が提起した写真群は、まさにそれら写真制作の発端となるものでした。
「記録」という写真の特性を、世界に対する私的イメージ化の範疇に組み替えていく。
あるいは、写真の中に現われる被写体それ自体が持つ指示性を、指示性の解体へ向かわせる。
つまり、自己表出性の拡大ということでしょうか。
現代写真が、1960年代以降、
年代とともに、より時間的、空間的な拡がりを、持ちえてきたきたことも、
その特質としてあげることができます。
一枚の写真があります。
この写真には、撮影した人が存在します。
この人を写真家と呼ぶとしましょう。
この写真家は、この社会的環境にあって、
その内に生活を営み、自己を創りなし、
他の同時代の人(他者)と共通項を持ちながら、
他社とは違った独自の視点を持ちます。
個性といわれるものは、だから、たったひとつしか存在しないのです。
しかし同時代の他者と共通項を持ち、
共通のカテゴリーを持ち、
共通の世界を持ちます。
写真家とは、本来的にそのような存在です。
個性と共通性、この両者のはざまで、
写真家は独自の視点をもち、
独自のストーリーを展開してきたのです。
<見ること>1
写真を「見せる」ことから「見る」ことへ。
この写真家自身の視点の移行をなした最初の具現者が.、東松照明だと思うのです。
東松照明は、長崎、沖縄を経て、記録者として、
そこに住む人の生活意識や心理採集といったレベルにまでも、
踏み込んでいく最初の写真家のように思えます。
写真が写真自体の肉声を獲得するのは、
「Provoke」の中平卓馬や森山大道だと思います。
彼らは、写真家としての行動様式そのもののうちに、展開してきます。
1960年代の後半の社会状況にあって、
彼らの行為(既成の写真概念解体)そのものは、
社会的有効性をそなえていたとしても、内容的には、
それは余りにも私的なカテゴリーの中での、
既成の価値をもった私性の、解体であったように思います。
写真が社会性を持ちえてなおかつ、写真家の肉声を獲得すること。
これが現在においても、私たち写真を制作する人の、
唯一の視座となりうるキーワードではないでしょうか。
<見ること>2
写真行為とは、時代を記録する行為です。
この行為は、どのような場合であれ、時代を超越することはありえません。
写真行為および表現行為は、常にこの時代と密着しています。
制作主体である私と私を取り巻く制度。
この二者は常に対立し対峙する関係にあります。
また、この対立・対峙から、私のなかで融合へ向かわせる関係です。
たとえば国家。
これは私が内在者である制度的な典型です。
規範としてそこに内在する私を常に抑圧します。
個の内部のより自由な発想も、一定の枠にはめ込んでしまいます。
もちろん「自由な発想」すら内存在を超えることはできません。
そしてこれを底辺から支える文化の形態は、
それ自体が規範の最たる具体的制度として、
私をことごとく規制してしまうのです。
「見る」こととは、決してこうした規制されてしまった視点で見ることではありません。
すでに出来上がってしまった価値観で、および感覚で、見るのではありません。
<見ること>3
写真は、写真家の目の前にあったものを撮ります。
目に見えるモノが複合して集まった現場を撮ります。
写真は見える現象の表面しか定着させることができません。
写真家が生きる時代に現われる現象しか撮ることができないのです。
写真家の作業は、常に個別に文化の総体、文明に内在する突出した現象に接触します。
そして接触した事を組み入れた視座のもとによって、作業が成立します。
「見ること」とは、背景となる主体の思想レベルが反映します。
その主体の思想レベルは、どれだけ制度から裸眼でありえるか。
写真家の視点、見たもの。
裸眼でもって見て思想化する。
写真はイメージだから、イメージからの逆提起でもあると思います。
この時代をどのように捉えるのか。
この捉え方こそが問題とされるのです。
裸眼の視座の獲得。
これを持って、はじめて現在において有効性を放ちます。
旧態の意味内容を継承のままでは、裸眼の視座は獲得できません。
現代写真の置かれた位相は、「ドキュメンタリー」イコール「記録」です。
そうして「記録」イコール「虚構」でもあるのです。
「記録」は「記憶」と結ばれており、「記憶」は「虚構」なのだと考えます。
<見ること>4
写真は、直接「事物」の形を定着させます。
以前なら印画紙、今ならモニター画面へと定着の方法が変わっています。
フィルムからデジタル信号へと、記録媒体が変化しています。
としても、事物の形を定着させることは、同じです。
この定着させられた「事物」には、その事物自体が指示する意味があります。
と同時に、その事物の背後が持つイメージの世界へと広がります。
このイメージの世界こそ、この時代にあって、
イメージとしてとらえられる文明や物価の質、
そのものに向かっているようにも思われます。
写真が素材とするものは現実です。
写真に写るのは形のあるモノです。
形のないモノは写りません。
私たちが、しかし、抽象的な概念を持つ言葉を使ったとしても、
実際にその概念を理解するのは、具体的な現象の羅列によっています。
写真は、この具体的な現象をこそ写し撮るのです。
そうして、そのことによって、イメージを拡げていくのです。
写真は、何を表現しようとしているのか。
現代社会にあって、不透明な価値軸をどのような位相として見るのか。
見えた価値軸をどのような位相に変えようとするのか。
この行為そのものが、いま求められる表現行為の原点ではないでしょうか。
<見ること>5
様々な、雑多な現象が、カオスのごとく提出されてくる、現在の文化状況。
都市があり人間があります。
一人一人の人間には、生活があります。
この生活の価値軸をこそ、明確にしなければなりません。
写真家は、明確にする価値軸へ、写真によって挑発しなければなりません。
この時代に内在的に起立させるべき問題を、はらまなければならないのです。
つまり、この時代のイデオローグを踏まえ、
その内容を写真に置き換えていかなければならないのです。
1960年代末の「provoke」が、私たちに提起する問題は、こうです。
意味にへばりつき、閉塞したイメージとしての言葉自体を、解き放つことにありました。
写真と現実をダイレクトに結合させるのではなく、
あたかも放物線を描くように、現実を遠くへ投げやるのです。
このことによって、現実を見る視座を拡大したように思われます。
イメージからイメージへと、連鎖のごとく世界を拡大していくのです。
カオス化した自己自身を逆照射し、よりカオス化した自分を発見していきます。
確かに「provoke」は、ムードとして社会状況を反映し、
ムードとして世界を獲得していきました。
写真は多くを語るように見えていますが、実は、そう多くは語りません。
いったん自分から離れてしまった写真は、見る側の状況によって、
あるいは見る側の価値軸によって、
つまり見る側の制度に従って見られてしまいます。
解読のコードを持ちえないレベルにおいて、
指示するイメージが何をも語らない危険をはらみます。
このような状況を踏まえてなお、新たなる意味を提示していかなければならないのです。
としたら、それは、自らの解体を意味したのです。
中平卓馬の自己批判は、そのことであったと解釈しています。
<見ること>6
写真家によって写された現場が、その固有の社会制度の内部で、
もっとも深くて深刻な場面であったとしても、ひとたび大衆という名の前に出たときには、
すべてが無意味なものと化してしまうのです。
未だ形を持たないイメージを、一定の価値軸に定着させるには、やはり現実の、
誰もが描きえるイメージの世界との接触点を、持たなければなりません。
写真行為は、時代の精神と無縁ではありません。
写真行為は、常にその時代の具現者として、時代を解明しようとする先見性が求められます。
時代と密着して生きること。これはその時代のシンボルを作り出す行為なのです。
写真は、構成される民族の精神、あるいは文明の質に立ち入ることによって成立します。
そうしてこの写真によって、精神や質が問われるのです。
写真行為とは、このことへの絶えざる闘いなのです。
時代の思想、言語的形態を、視覚、写真的形態に置き換え、提示する写真の中に、
写真家自身の意識の構図を読みとらせなければなりません。
この地平から、何が見えてくるか。
写真家は、現在の内部に存在します。
写真家の持つ視座は、この現在を構成する複眼的精神を、
具現化するものでなければなりません。
この時代に内在する精神を、写真家の主体によって組み換える。
こお作業をなくしては、時代の写真家たることには、ならないのです。
なぜなら、写真作業には、いま、まさにこの現在という、
時代精神の組み換えをこそ求められているからです。
(おわり)
Shigeo Nakagawa 1984.6