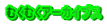
最新更新日 2012.5.26
現代写真の視座・1984
-ドキュメンタリー写真のゆくえ-
中川繁夫:著
私性の創出と解体(1)
<中平卓馬>
1960年代の終わり、写真同人誌「PROVOKE」にかかわった中平卓馬は、
総括として次のように述べています。
<当時われわれを支えていたのは、それまで支配的であり、
今もそうである、意味にべったりとへばりつき、意味から出発し、
意味に還る既製の言葉のイラストレーションとしての写真を否定する衝動であった。>
(なぜ、植物図鑑か)
ここで中平卓馬がいう「意味」という概念は、
同論文によると、次のようにとらえられています。
<カメラのもつ物理的性格に依拠して、写真を遠いものを近くへ、
まだ見ぬものを見えるものへとの移送する情報価値にだけ限定しようとする
写真誕生以来手を変え品を変え写真家につきまとっていた
薄められた自然主義リアリズム、
またそのほとんど正確な裏返しとしての社会主義リアリズムである。>
ここで少し説明を補足しつつ中平卓馬がいう<意味>の概念を読んでいくならば、
これは、写真そのものが指示するところの、見る側に対する写真家のアプローチの仕方が、
問題だというのではないでしょうか。
<中平卓馬>2
1960年代、それまで撮られてきた写真は、おおむね既存の価値体系を背景としており、
またそういった環境を基盤としていたのであり、そういった価値体系や環境のえうを、
イメージでもってなぞっていくことで、写真と写真家が成立する。
中平卓馬は、このような方法に基づいて撮られたのだと指摘します。
ここでいうのは、それ以前の写真の提示方法が持ちえていた内容のことごとくが、
それに該当すると指摘するのでした。
自然主義リアリズムとしての写真の主流が、
まだ見ぬものを見えるものへと移送するための手段として、
写真を介在し、そのなかで写真家の行為が、成立してきたというのは、
歴史的な事実であるといえます。
もともと自然主義とは、写実、
つまり写真家の目の前にあるものを、
ありのままに観察し、記録にとどめる。
この作業を軸とした、ありのままの姿を写し出す方法だといえます。
このありのままの姿を写し出すためには、
写真家の視点は、ありのままの姿の背後に隠されてしまう、
その手法のことでもあると、いえます。
実際に、写真史上において、
こういった視点からのみ写真が撮られたかどうかは別にしても、
ここで中平卓馬が提起したリアリズムの問題は、
写真家と被写体の間に横たわる距離。
写真家は<何処に視点を置くか>という
<私>と<私をとりまく環境>とのディスタンスの問題として
考察されるべき契機を持っていると思えます。
<中平卓馬>3
まだ見ぬものへの好奇心に支えられ、カメラが未開拓の奥地にまで入り込み、
そこから報告をもたらすことによって、写真が成立するという、
いわゆる情報の希少価値でもって写真の価値を計測するという潮流は、
いってみれば現在もなおかつ主流の位置にあると思われます。
これは、写真が持つ機能であるところの、<現実を模写する>という機能から、
派生している必然の帰結です。
たしかに写真がこういった機能を持ち、要素を持つことを否定しませんが、
ただ、写真家の主体性の問題として、
それをどのように内面化し、とらえなおすか、
ということが問われるべきなのです。
一方で、政治的止揚の手段として、
写真の機能を実践に寄与させるという要素を、色濃く持った社会主義リアリズムは、
写真が、写真たるべき本筋から、
離脱した方法論であったことも指摘されるでしょう。
<1960年代>1
1960年代は、写真にとって、最も価値の位相が転移してくる時期でした。
ドキュメンタリー的手法も再構築。
こうしたなかでの新しい世界観の獲得。
もちろんこういった動きが写真界にのみ現われたのではありません。
このムーブメントは、文化の諸相で突出してくるのであり、
写真もまたその時代のなかで、影響を受けるのです。
文学、映像、音楽、絵画、等あさまざまな芸術の位相で、
新たなる視覚が獲得されるのでした。
写真においていうならば、
セルフエージェンシーVIVO(1959年)と、
そこに集まった写真家たちの活動があります。
また写真同人誌PROVOKE(1968年)にかかわった
写真家たちの主張であるでしょう。
写真は記録である。
しかしこれはすでに中平卓馬によって否定されたように、
意味にべったりとへばりついた写真におけるところの、
写真による記録ではありません。
ドキュメンタリーの方法。
それは現実にせまる方法の問題として、
視覚を、すでに固定してしまった見方や固定してしまった意味から解き放つ方法として、
現実を凝視し、対象となる被写体を記録する方法です。
中平卓馬は、この解き放つ方法を、実践させようとしたようにも、思えます。
<1960年代>2
「それらに対して私は私の生きる生の記録を対置した」
中平卓馬は、その唯一の論拠として、
「一人一人の背負い込む総体の中で個別的な現実を構成するものだ」
といいます。
また次のようにもいいます。
「記録という言葉がわれわれに即座に連想させる客観的な私不在の視点に対して、
私の絶えざる世界との出遭い、
それだけを重視しようとする姿勢から
記録という言葉をもう一度捉え直そうということであった」
「私の絶えざる世界との出遭い」
私の見るものことごとくに、私存在は私をとりまく外状況と出会うのですが、
この「見た」という私の体験と、そこで写された一枚の写真の存在のギャップ。
世界は、私存在にとっては、重要なことではあっても、見る側の人々は、
私の生をまで背負ってはくれないのではないか。
ディス・コミュニケーションに対する苛立ちです。
1960年代は、政治の季節でもあり、日本の文化状況が、激しくゆさぶられます。
学生運動では、政党指導を乗り越えるムーブメントも、台頭してきます。
進歩的という冠詞はすでにその時代、
古い形式的色彩がつきまとう言葉でした。
芸術にあっての運動形態では、
それらはとりもなおさず内発的契機を重視する制作方法です。
一方で高度経済成長に拍車がかけられ、
全速力で社会資本が投入され、
成熟されていく社会状況です。
ズタズタに引き裂かれる個の内面の危機感から、
対政治認識が前面に押し出されてくる時代でした。
1950年代のような労働運動ではなく、
それは個の問題として、クローズアップされてくるのでした。
<東松照明>1
さきに1960年代末に突出してくる「PROVOKE」での、
中平卓馬のことばを引用しましたが、
それに先立つ10年前、1959年に活動を開始する「VIVO」の結成を、
記述しておかなければならないでしょう。
東松照明ら六人のメンバーで始まる「VIVO」は、1959年7月に始まり約3年間続きます。
(メンバーは、東松照明、奈良原一高、細江英公、川田喜久治、佐藤明、丹野章)
新進写真家の共同事務所として存在しますが、写真の新しい質の出現として注目されます。
1960年、東松照明は、アサヒカメラに「占領」シリーズを発表します。
また、フォト・アートに「家」シリーズを発表します。
1961年には、フォト・アートに「NAGASAKI」を発表します。
東松照明の手法は、ドキュメンタリーの色彩が濃い写真群ですが、
従来からの語り口調とは異質な、
写真を感性としてとらえていく、新しい境地を開拓します。
1960年といえば、安保闘争があり、連日デモ隊が国会周辺を取り巻いた年。
テレビが家庭に入りだし、白黒テレビのブラウン管に映しだされました。
いよいよテレビという映像群が、家庭で享受される日が、到来していたのです。
<東松照明>2
1960年の時代、はっきりと自己の、
自己のための視点を持って世界に打って出る写真と写真の方法を、
「VIVO」のメンバー、東松照明は持っていました。
それまでの写真による直接的な問題の提起の仕方とは明らかに違う点は、
作家主体たる自己を、外化させる方向に重心が置かれつつ、
社会性を持ちうる手段でした。
とはいえ、私性へのみ内向していく視点では、ありませんでした。
1960年代の中心的役割を果たしてなお、次の世代へ、
最前線写真家として渡ってくる写真家が、東松照明だと考えます。
東松照明の二つの立脚点は、
私性と社会性という作家主体の基盤を統合した位置で、
写真制作の作業をなしてきたことです。
ゆえに、唯一の方法論として、
現在にも有効なドキュメンタリーの手段と方法として、
みることができるのです。
「見せる」ことから、「見る」ことへ。
そういった写真家の視点の変換方法での最初の表現者が、東松照明でした。
「占領」シリーズといい、「家」シリーズといい、
そうして1960年代はじめの長崎通いは、
個人としてこだわり続ける「見る」ことへのロングラン。
これの始まりでした。
また東松照明は、ドキュメント写真に必要な、
「ある時」「ある場所」の根拠を自ら創り出していくのでした。
<東松照明>3
世の中は1960年の安保問題を中心にして動いている最中、
東松照明の視点によれば、その本質的な戦後社会の構造は、
日本とアメリカという二国間の関係に見られる占領関係です。
精神文化と物質文化、敗戦国日本と戦勝国アメリカ。
アメリカナイズされつつある日本風土に、日本人の一人として危機感を覚え、
その現象の突出した現場を「見る」という意思が生まれてきているようにも見えます。
東松照明は「見る」ために被爆地長崎へ通います。
そこには、原爆炸裂から15年が経過した長崎がありました。
モニュメントとして東松照明の意識にたちあらわれてくるモノたち。
「11時02分をさした時計」であり、
「溶解したビールビン」であり、
爆風により倒壊した「浦上天主堂」でした。
それらのモノを見た東松照明、そして写真に撮った。
その行為、写真家の目の前に存在したモノが写されたというその行為。
その行為そのものが、写真家そのものなのでありました。
<見ること、見せること>1
写真家が遭遇した事実を、撮るということ。
撮られた写真が、見る側にインパクトを与えるのは、
「見た」「撮った」写真家が、
インパクトを与えられたモノを、
インパクトあるモノとして、撮られたからです。
「見る」ことは「見せる」ことに結びつきます。
写真家内部においては、両者は共に存在するものです。
けれども、それは、「見せる」ことが優先されたスタイルではないのです。
「見る」という主体たる写真家の、問題意識が湧き出るのです。
ここに、新しい写真の質と、写真家の態度の新鮮さが、あったと思います。
世界の表面に突出する問題を、
すでに定着している価値概念で切り撮るのではなくて、
自づからの自立した史観の反映として、写真を創る。
撮ったそのものにまといつく旧態の観念を払いのけ、
裸の視点で「見た」という事実を、提示するのです。
1960年当時、その時代の写真の視座を持ちうる表現記録者は、
自づからの自立した史観によってのみ、表現記録をなしえたように思えます。
写真家が、生きる時代の視座を、持つということは、
写真家自づからの史観によって、ある場所を、
その行為の手段である写真において、定着させることなのです。
<見ること、見せること>2
写真において定着させる。
これは、その制度内部において制度自体を凝視し、
その制度の見えざる視野を探り当て、起立させる行為なのです。
しかし、この知的生産の行為、つまり自づからの史観を構築させることは、
写真家単独でなし得られるわけではありません。
そこでは、他のさまざまな意匠をつけたジャンルの、同時代の精神を共有する人々の、
起立させた脈絡の中でこそ営まれることなのです。
1960年代のはじめは、この意味では、まだジャンルを超えて、
各表現分野が連帯しあえる時代であったのでしょうか。
東松照明が「見る」ことから始まった最初の写真家であるとも言えるのは、
一貫して、常に既成の価値観に挑戦するという、
表現行為者としての表現そのものの本質を鋭く突いているからです。
あえていうならば、既成の価値観から出発し、新たなる価値観を生み出す主体であったことでしょう。
これは写真表現の現代的主要なテーマでもあるのです。
東松照明の写真の質を言い当てなら、従来の報道写真的脈絡にとらわれない、
独自の脈絡として写真をとらえることでした。
このことは、写真を新たな視覚記号として組みなおす作業です。
また写真家自身が、そのようにとらえることにあります。
東松照明のそこには、言語記号体系とは別の、写真の自立そのものがあるようにも見えます。