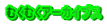
最新更新日 2012.5.26
現代写真の視座・1984
-ドキュメンタリー写真のゆくえ-
中川繁夫:著
私性の創出と解体(2)
<Provoke>1
1960年代末の政治状況、それに伴う写真の状況です。
時代状況は、1960年代初葉とは、相当な変化が見られます。
商業写真の分野では、視覚でコマーシャルの傾向で、需要が飛躍的に増大します。
高度経済成長も、地域格差を拡大させます。
日本は、農業国から工業国へ、農村の解体から高度な都市形成へ。
こうした政治経済の社会状況から、文化状況の閉塞化が顕著になってきたのです。
進歩的知識人や学生層を中心に危機感を抱かせ、マス・ヒステリー状況が出現してきます。
こういった状況が、1960年代末の社会状況であったように思います。
写真におけるこの突出が、写真同人誌「Provoke」の発刊と、その同人写真家の仕事です。
同人は、中平卓馬、高梨豊、森山大道、詩人の岡田隆彦、評論家の多木浩二です。
このメンバーが、閉塞したと感じられる政治的文化状況の中で、
強烈なアンチ・テーゼを提起して登場するのです。
この1960年代末まら1970年代初葉の作家の出版活動状況を羅列します。
1967年、森山大道「にっぽん劇場写真帖」
1968年11月、写真同人誌「Provoke」創刊。
1969年、東松照明「おお!新宿」
1970年、多木、中平「まず、たしからしさの世界を捨てろ」
1970年、中平卓馬「来たるべき言葉のために」
1972年、森山大道「写真よさようなら」
<Provoke>2
「Provoke」発刊の時期は、70年安保改定前の政治の季節に並行します。
写真のイメージは、アレブレ写真です。
それらの写真群が私に投げかけてくるものは、あの時の息吹です。
1968年から1969年は、学生たちによって大学が封鎖された時期です。
巷には連日デモが組織され、大学内では学生たちが議論しました。
「provoke」に参加した中平卓馬は、当時の学生を中心に読まれた雑誌の編集者でした。
写真が肉声を獲得し、自立し、外的条件に対して、風景論が展開できた時代です。
私がいま、写真家の資質と、カメラが向かうべき被写体への方向、
あるいはイメージの総体として何処へ向かえばよいのかと問うとき、
「Provoke」の写真家たちとその写真が陥った地点は、
私性への偏重でありすぎたように見えます。
東松照明を乗り越えようとする中平卓馬は、総括として、
写真が記録であるからには、どうであれそれを見る他者との間に、
不確定ながらも、あるコミュニケーションが成立する、と仮定していたのです。
同じ状況を共にする関係にある者同士であれば、
それはたぶん、感覚的で気分的な要素だけで了解できる、とうことは認めるとしても、
この了解できることと、論理的に納得することとは、意味が違うのです。
写真が撮られる場の共有ということがあります。
このことは、写真家が写真を撮る現場が、社会的認知されているか否か。
状況体験の共有関係を持たない外部世界の他者においては、
まったくコミュニケーションが欠落してしまうことに、気づかなければならないのです。
<Provoke>3
確かに私性の強烈な露呈は、受容する者にとっては、強烈なインパクトを与えられます。
しかし、これは本質的なコミュニケーションのすべてでは、ありません。
写真は、基本的性格として、より社会性を獲得していかなければ、ならないのではないか。
単に事物が写された写真そのもの、素材そのものが、
社会性をおびていなくてはならない、というのではありません。
それは撮る側、つまり作家の意識の問題として、写真家自体、その視点、
つまり私性そのものが、社会性をおびていなければならないのです。
あるいは、それは、提示方法の問題として。
中平卓馬は、<なぜ、植物図鑑か>のなかで、次のように総括します。
「そこには、写真がよって立つ社会的基盤、つまりマス・メディアを離れて
写真による個人的な表現などありえないということの
リアルな認識が欠落していたように思われる」
「Provoke」にかかわった中平卓馬が、自分自身をそのように総括するのです。
これは写真行為として、私性の全面展開という方法が、
破産してしまったことを、みてとっているのです。
この中平卓馬の自己批判は、
写真がよって立つ社会的基盤を離れての、
写真行為などありえない、ということの再認識でした。
写真表現の方法が、私性の内側に陥ってしまった迷路。
それは、意味の剥奪、形式の剥奪、既存の価値の転換、等々。
写真は「Provoke」の写真家たちによって、
この迷路に踏み込まされてしまったと、言えるのかもしれません。
<私性と社会性>1
1960年代の写真。
その初葉から終わりまでの約十年の時代。
短いといえばそのようにもいえるひとつの時代。
その十年は、過去の幾十年にも匹敵する変化に見舞われたのでした。
私たちはいま、その時代を駆け抜けたそれらの写真家たちと、
そこから放ち出された写真群から、何を学べばよいのでしょうか。
学ぶだけではなくて、彼らの中の何を乗り越え、何を切り捨てればよいのか。
そこから何を継承していかなければならないのか。
それらを見定める必要に迫られています。
時代は1960年代ですから、すでに半世紀が過ぎるいまです。
その後において、いくつもの潮流が起こり来たいま、2011年です。
にもかかわらず、いまだ、写真の世界において、話題となる1960年代です。
いま、そこから、なにを発展させていかなければならないのか。
いまもなお、巷の多くの写真が、「Provoke」が提示したイメージを内含しています。
この潮流が払拭されないのは、何故なのだろうか。
もちろん一見、カメラ性能が向上した等の理由もあって、ブレボケ手法は影をひそめました。
でも単なる手法上の問題ではなく、私性と社会性ということについて。
私性と社会的基盤という関係において見る限り、という問題設定においてです。
<私性と社会性>2
いま巷におびただしく現われてくる写真の群は、
様々な方法と方向をもったスタイルとして、
あるいはデコレーションとして、多様化しています。
この現状を踏まえてなお、現在の主要なテーマとされているのは、
私性への偏重であり、私性への逃避です。
写真が単独で写真独自の道を歩み始めた歴史を見る限り、
百年、あるいは五十年あまりが経過したところです。
ふりかえって、「VIVO」から「Provoke」の時代を総括すると、
新しい時代の新しい写真を、波打ち際に立たせた業績は高く評価すべきでしょう。
それから約半世紀、基本的に1960年代の質的変換は、
いま、私たちが引き受けるべき質を、その内に含んでいるからです。
はなしを私性と社会性に戻しましょう。
すでに自明のことですが、私は私をとりまく世界に規定され、世界は私を規定します。
私と外界。
写真に即していえば、撮影主体たる私と被写体との関係は、
相互に規定し規定される関係です。
規定し規定されるという、この関係の中で、
私のパーソナリティによって、視覚のフィルターをかけます。
<私性と社会性>3
私をとりまく世界とは、具体的には、まず国家という形態に遭遇します。
私がもつ国家とは、私の場合、日本国です。
その諸制度が、私をとりまく世界となって現れます。
法律や、それを施行する経済の体制、福祉の体制、政治の体制といったもの。
かならずしも政治的側面の諸制度だけではなく、文化状況もあります。
そのうえ、もっと根柢のそれを構成する人間精神の生成も含められます。
表現行為としての写真の現場は、この諸制度に制約されるのです。
表現行為は、単純には、この諸制度との対関係に置かれています。
対関係には、敵対関係の場面と融合関係の場面とが想定できます。
しかし、真の表現行為とは、筆者の考えでは、
敵対し対立する関係のなかにこそ成立すると考えています。
この関係のとらえかたは、
表面的な政治的関係というより、表現の方法の問題です。
写真を撮る現場にあっては、
そのような表現の方法として、
カメラの前に存在する事物を撮ります。
つまり、撮る事物の制度的な意味を、
どのように変質させるのか、の場として存在させます。
<私性と社会性>4
写真は、私性を不在させる客観的視点から、
私性に傾倒していく主観的視点までを包括します。
客観と主観の間、このゾーンのなかに写真表現がおこなわれます。
いずれの視点であれ、ある時、ある場所、で撮影した写真です。
つまり作家主体が、その目で見た領域を超えて、
より能動的な意志に支えられた行為として、
立ち現われてこなけらばならないのです。
客観的視点、主観的視点、これは写真に写された事物と作家の距離に集約されます。
記録の方法の問題として、客観と主観、それだけの幅を持っているわけです。
撮影者としての主体は、社会的諸制度から派生する観念を基盤とし、
この観念、あるいは精神の統合したものとして存在します。
現在問われているのは、
撮影者の意志を支える根柢を作っている視座を、
いかにして獲得するのか。
この問題こそ、問われているのです。