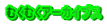
最新更新日 2012.8.29
写真ノート第一部
中川繁夫:著
写真ノート 第一部
第一部 1984〜1986 8〜15
19840811
今、自分は何をすべきか。これまでのルートではないところで、今後は、フォトハウス構想を実現していけるルートを模索していかなければならないのですが、構想の内容、つまり出版や講座や展覧会など、新しい秩序を構想し、これをやり遂げようとすれば、フリーになって、そのことだけに専念しなければならないでしょう。と云ってこれを職業としていくには、将来は別として現在では経済的基盤がとうてい確立しないでしょう。このへんのところが悩みなのです。
私の周辺に俗にいう写真のプロが沢山います。プロとはいっても写真活動そのもので食えているのか食えていないのかわからない人たちが多いのです。そんな自称プロのなかにあって、他に職業を持った私が出てくることに対してプロを自認する人から見れば、癪の種というところでしょう。
東松さんとの出会いが、私の立場を大きく変えていると云えるかも知れません。つまり周辺の人たちから見れば、俗にいう「権力を笠」にして発言している、あるいは行動しているということでしょう。私自身としては、決してそのように対処しているわけではないのですが、そのへんのところを明確にしておかなければならないのかも知れません。今更、旧態の写真の世界に戻れないとするなら、今後は何処へ行けばいいのでしょうか。
19840821
今年の夏も、すでに終わろうとしています。お盆には夏の京都を写そうと思っていましたが、結局、一度もカメラを持たないままに済んでしまった。いま、家の増築をやっています。暗室は使えませんし、読書もままならない状態です。こうした日々を過ごすことが、気持ちの上で弛緩してしまうことを、恐れるのです。
さりとてこの夏には、私に十分な取材態勢が出来ていなかったものですから、こういう結果になったのです。今、思うことは、ただ「秋になれば今一度、気持ちの上で態勢が構築できるようにコントロールしていかなければならないだろう」ということでしょう。そうでないと、このままズルズルと引きずりこまれてしまって、どうしようもなくなる、ということにはしたくないのです。
相変わらず写真雑誌は発行されています。「アサヒカメラ」、「カメラ毎日」、そして「写真時代」。単行本にしても次から次に発行されており、立ち止まっているのは、自分だけとも思うこの頃です。
九月号の「カメラ毎日」の関西写真情報は、畑祥雄さんの文章となています。太田順一さんはどうしたのだろうと思います。最近は彼らから離れているせいで、写真の動きそのものが解らなくなっています。情報が入ってこないのです。九月には野口さんが個展をやります。こんな情報も白々しく思ってしまいます。
19840908
九月に這入って、京都はもうすっかり秋の気配となりました。夏には家の増築に追われていて、自分の部屋が使えず、気持ちも落ち着かずで終わってしまいました。しばらくそのような日々が続きますと、気分の方もすっかり、緊張感がなくなってしまいました。まだ本格的な夏がやってくる前には、雑誌発行や講座開講と、いろいろやらなければならない事ばかりを考えていましたが、夏の暑さがそういった気持ちをなくさせてしまったようです。今もまだ増築工事が終わっていなくて、気ままに部屋が使えないのです。しかしこのことをもって、何もできないことの理由にしてはならないと思っています。
野口賢一郎さんが、渋谷のドイ・フォトスペースで「失楽園」の個展をやっているところです。畑祥雄さんが大阪で「閉鎖された紡績工場」の個展をやっているところです。いずれもすでに発表済みの作品とはいえ、みなさん頑張ってるなぁ、と思うところです。私自身はと云えば、ご覧のとおり、最近はこれといった動きをやっておりません。この秋には、雑誌出版の企画を立てていましたけれども、当面、事は運ばれそうにもありません。
春には映像情報が終刊になって、私には「写真&批評」という少しはまともな雑誌を、ということで目論んでいるのですが、何人かが共同で出版しないことには話にならない、ということで機を窺っているところですが、このままでは何もできないような気がしています。
もう十年前の話になりますが、その頃は小説を書こうと頑張っていたところでしたが、それは1974年頃でした。やはり、ひとつの時代が終わったな、という気持ちで日々を過ごしたものでした。ちょうど家を新築し、カメラを持ったころでした。70年前後から続いてきた緊張の糸がプツリと切れたかのように、後退してしまったものでした。
この一年ほど前から、再びそんな気持ちになっているような感じがして仕方がなかった。80年前後から続いてきた緊張の糸が、プツリと切れてしまったといえるでしょう。すべてが繰り返しのような気がしています。
78年秋、釜ヶ崎取材に這入る。79年夏、三角公園で青空写真展。その秋、「季刊釜ヶ崎」創刊。おなじく京都にフリースペース「聖家族」創出。80年夏、「映像情報」創刊。81年「東松照明の世界、いま展」に参加。「フォト・シンポジユウム」企画開催。82年「図書館に写真集を!」運動に参加。この間に新しい写真の運動を創出しようと試みる。
いろいろとやってきました。しかしあと一歩というところが決められなかった。あまりにも性急すぎたのでしょうか。それとも私自身に至らないところがあったのでしょうか。今、私にとっては、全てが反省の時期なのかも知れません。
19841002
最早、十月になりました。今年の夏から自宅の改築で九月いっぱいまで工事がかかり、やっと十月になって完成というところです。あと残すところは、本箱のペンキ塗りが残っているところです。これも明日には終わるので、ようやく落ちついて作業ができるようになります。
この二ヶ月の間、ちょうど夏で、いつもの年ならけっこう写真欲も湧いてきてハッスルするところでしたが、今年はすべてが何もできなかったのでした。人とも会わず、写真展にもいかず、撮影にもいかずで、ほんとうになにもありませんでした。そんなこんなで気持ちも緊張を保てなくなったようです。すべてが遠くなってしまった感じです。そんな気分の中で明日、野口さんと会うことになりました。彼は東京へ行ってから、京都にいたとこ以上に頑張っているようにみえます。
この10月号のカメラ毎日では、新人として掲載されているし、また展覧会の方も、東京、大阪、京都、と各地で開催しており、今が一番調子のいいときなのではないか、とさえ思われます。今後の活躍を期待します。野口賢一郎写真展「失楽園」10月4日〜10月14日まで、大阪のピクチャーにて行っています。内容は植物園を撮ったもの、5日にはオープニングパーティがあるという。
さて当方のフォトハウス構想だが、これも7月以降ストップしたままだ。せめて構想の原案だけでも残しておかなくてはいけないだろう、と思っている。また雑誌の発行についても、幾人かが集まってやっていくには、現在のところ望みがない。映像情報の続きでもやりはじめようか、と思うところだ。しかし東松照明さんと話した限りでは、一人でやっていってもそれだけのことだから、というようにやはり何人かでやっていける道を、模索していくべきであろう、と思っている。しかし、このままいっても結局何もできないままに終わってしまいそうなので。
19841002
ベートーベンのピアノソナタを聴いている。情熱的というか何というか。こう胸に迫ってくるものがある。シュナーベルというピアニストが、もう50年も前に録音したというソナタだ。このレコード全集は、ぼくが高校を卒業して十字屋に就職した当時に買ったものだ。もう20年も前のことだ。この当時、ぼくは19才だった。その当時から今まで、ぼくの手元に残されたレコードの、完全な形として残された唯一の全集だ。
ピアノにぼくは昔から魅せられている。その当時、ピアノを習いに行った。茨木市まで毎週一回、レッスンに通ったのだった。それから大学に入ってからは、もうピアノなんて関係ないよ、といったふうに文学にのめっていった。大学闘争があって、それから挫折した日々があって、静かに静かに、日常生活を送っていたころ。もう子供が少しばかり大きくなって、経済的余裕もなく、余裕より音楽鑑賞というごくありふれた趣味の形態に反発して、レコードを聴くなんて恥ずかしがっていたのだ。
プチブルな生活を排除しなければならないと、真剣に考えていたし、なによりもそんな趣味に明け暮れる時間的余裕がなかったのだった。写真を始めるようになって、釜ヶ崎へ行くようになって、釜ヶ崎で悩み、もうどうすることもなくなった精神を持って、もう釜ヶ崎へは行かないぞ、と決めた頃、無性に音楽が聴きたくなったのだった。ニューミュージックと同時に自宅にピアノを購入することになった。もう四年も前のことだ。
ピアノは子供のために購入したものであった。しかしぼくはもう20年も前に習ったという経験を生かして、、再び鍵盤に向かいだしたのだった。これも二年も熱中しなかったが、この頃から聴くことに愛着を持ちはじめたのだった。ボーカルでは、ニューミュージックで五輪真弓から中島みゆき、とりわけ中島みゆきには、その声質からファンになった。
一方でピアノの旋律に魅せられてしまった。その昔、理解できなかった感情の深みというか、音の連なりの中に、ぼくは精神を揺れ動かすのだ。
19841000
関西は燃えていたか。80年代関西写真考。
いま私は、この80年代の中盤にあたって、関西における写真の現状について考えている。本当は、特に関西にという地盤にこだわることもなく、写真の状況全般について、この時代の質ともいうべきところから、考察を加えていかなければならないところだろう。けれども状況を語っていくのに、そうとも言っていられないのだ。
現在写真を取りまく状況は、とくに写真そのものだけの問題ではなく、それを含んだところの経済の機構や流通の仕組みにまで言及していかなければ、もう何も語れないほどに複雑化しているのだ。写真を取りまくそれらの状況は、単に表現手段としての写真だけの問題ではない。とはいえ、そこを通してしか語りえないのもまた仕方がないことでもある。
関西は燃えているか、あるいは燃えていたか。私はいま、まじめにこういった質問を投げかけようと思う。なぜならば、つい先ごろまで私は、関西は燃えている、と解釈していたし、また、そのようにもあったと考えていた。これは何よりも、写真を撮り、自己の写真を作品として残していくという道筋とは違ったことであろう。私たちは作品を残すことによってのみ、写真家なのである。このことをふまえたうえで、まず論じていかなければならないのだ。
関西、とりわけ大阪において、80年代の初めから活発な動きが見られたのは、82年9月に行われた「東松照明の世界・大阪展」であった。関西の行動的な若手が集まり、関西における写真の現状を何とかしようと目論んだのだった。ここで私は関西と言ったが、本当は関西なんてどうでもよかった、要は写真の問題であり写真家の問題であったからだ。
この目論みは、70年代の残影であった、とも言えるのではないか、といまは思っている。時代が変わった、と思うのはここ最近のことではあるが、実際に、それらを動かしていた衝動はと言えば、やはり70年代に青春を送った、すでに30代の人間であった。
すでに時代の価値観は変わっていたか、もしくは変わろうとしていた時期で、本来ならばもっと若い世代が主導権を握るべきであったろう。にもかかわらず私たちのような世代が、夢をもう一度じゃあるまいが、いってみればそのような格好で動いたことが、そもそもの諸悪の根源であったようだ。
いったい関西に何があったと言うのだろうか。私は特に京都出身なものだから、とりわけ京都にこだわり、京都でなければ、と思う気持ちで発言してきたのだったが、結局、写真の世界において、京都ということは、何ら関係のないことであった。京都であれ、東京であれ、写真をやっていくことにおいては、関係のないことであって、要はその質のみが問われなければならないのだ。しかし、それらの事も上すべりであったようだと思っている。
19841000
日本写真史1840〜1945
日本写真家協会編/平凡社刊
写真の歴史を今一度見直してみようと思って、最近、この書籍を購入しました。日本に写真術が渡来してから、敗戦までの写真史です。この書籍の姉妹編として、現代日本写真史が発刊されており、こちらのほうは一カ月ほど前に買いました。こうして以前から読んでおかなければいけないなぁ、と思っていたのを実行に移すことになったのです。とはいっても、どこまで読み通せるか、やり通せるかが問題なのですが。写真を論じるにあたって、その歴史をまず知っておかなければ、と思ってのことです。
この春に、「写真の現在展」に参加して以来、何やかやとして当初の計画で、発刊しようと思っていた雑誌の方も、発行は思うにまかせず、そしてこの秋まで、至ってしまいました。何とかして自分の意志を持続させていかないと、このままいってしまうと、言葉すら忘れてしまうことになってしまうでしょう。最近、特に、こういった危機感を、持つに至っています。
生活を維持していく上での、日々の生活を支えていく為の仕事。日常性への埋没。毎日、忙しい忙しいと言いながら、あっけなく一日を過去にしていきます。本当は、実作家としてあるからには、写真を写し続けていかなければならないのです。しかし、今の、生活を支えるための私の時間の潰しようからいって、とてもそのように、実作家であり続けられる程の、時間的な余裕が見いだせないないのです。
これではいけないし、また忙しさを口実にした逃避であると思うのですが、しかし、こういった時間の差し繰りがつかないといったことも事実なのです。しかし、夜ならばなんとかして、少々の無理をすれば、少しばかり時間も取れるだろうし、で、これからはむしろ、評論を中心に、体系を組みなおしていこうと思っているところです。
それにしても日常性への埋没、ということ。やはり以前、ちょうどもう十年くらい前になるかと思いますが、やはり言葉を忘れ、為す術を知らず、数年間を過ごしたことがあったものです。小さな快楽を求めて、矮小化した自分をそこに見ていました。写真を始めたのは、ちょうどそんな時期でした。
今、それらの日々をふり返ってみると、写真のたわいない初歩の段階で、よくぞ熱中したものだったと思います。やはり一流を目指さなければならないと、私はそう思う。だからこそ、基礎的な事項については、ふまえておかなければならないのだと思うんです。
19841100
写真作家としての感性を私は持っていない。特に優れた感性を持っている訳ではない。特に優れた実技を持っている訳ではない。たまたま写真をやりはじめて、何年かが経って、けっこう上達したように思っていたし、結局そてが、いったい初歩的な段階のものであったことを実感して、私は私の実力を知ったわけです。そこで、私は今一度、勉強をやりなおさなければならない、と思っています。そこで、日本写真史という本を買ってきたという訳です。
10月31日、東松照明さんと会いました。久しぶりに会いました。まず7月に祇園祭りのころに会ったのが最後でした。この時は、野口賢一郎くんや建築家の松本健さんと一緒でした。その前はというと、もう4月の桜のころ。この時は写真壁で、たくさんの人と一緒でした。というところで、久しぶりに会ったわけです。六曜社で落ち合ったのが6時30分、その前にDOTで会ったのでした。
この日はぼくの休みで、11時すぎまで家におり、雑用を処理するために自転車で市内をぐるっと回るつもりでした。最初に中信へ振り込みに行き、そこから下の森の西陣ベッドセンターへカーペットの代金を支払いに行き、続いて四条大宮まで行き、堀内カラーへコダクローム3本、現像に出し、住友銀行に行って、通帳に記入を済ませました。そうして府庁前のアタリヤへ机の代金を支払いに行く途中で、建築家の松本健さんに偶然にも、会ったのでした。彼と昼食をとり、そして彼の事務所へ行ったのです。
松本健さんは今年の夏、ぼくが企画書を作りつつあった、フォト・ハウスの実現について、協力しても良いという意思表示をしてくれたのでした。この件については、この時が初めてではなく、今までにも事あるごとに、そのような話が出たものでした。10月の初めに、野口賢一郎くんを交えてあったときにも、今なら出来る、といった話をしたところでした。
ぼくにももちろん懸案になっているところの話ではあるのだ。しかし、忙しいと言うぼくは、やはり言い逃れをやっているのかも知れない。しかし、現実の問題として時間がないのだ。しかし、だから何もできないということは、ぼく自身にとっても実は、思い悩ませているところなのだ。
松本さんの建築事務所に一時間ばかりいて、ちょっとは勇気ずけられて、その足でDOTへ行った。DOTでは、ちょうど松本路子の写真展「肖像ニューヨークの女たち」をやっているのだ。ここには作者がいた。岡田悦子氏に紹介されて、彼女の作品の傾向が、有名アーティストが被写体であるけれど、ぼくの釜ヶ崎の無名碑の方法と似かよったところがあるのだ。ここで写真集を購入し、サインをしてもらい、そうしてしばらくして、そこに東松照明さんが現れたのだった。
19841100
鈴鹿芳康写真展「STONE IN THE STREET」
1984.11.20〜1984.12.9 Gallery DOT
鈴鹿芳康の写真展は、カラー45点で構成された一見テーマのない写真がアトランダムに並べられているように見える。それらの一点一点が綺麗な発色をもった感覚の世界だ。鈴鹿芳康の、ダンボール箱5杯分のカラースライドから、岡田悦子がセレクトして展示されたものである。
一枚一枚がキーポイントとなる原色をたくみに生かして、それぞれが鮮やかな色彩を奏でている。この展覧会のタイトルが示すように、街角の石。鈴鹿の行く先々でデートマチックカメラのシャッターが押されている。目に入るものは何でも撮っていくという、一見無謀な撮影態度であるが、しかしこれがひとつのスタイルとして、鈴鹿芳康独自の展開となっているのだ。
すでに発表された鈴鹿芳康の写真に見られたコンセプトは、ここでは希薄になってはいるが、これはアトランダムに岡田悦子の目によって、あえて解体され一枚一枚のタブローの面白さによって選択されているからである。街角をさまようようにして歩き、あるいはふと街の片隅で発見した事物の在り様に鈴鹿はカメラを向けるのだ。鈴鹿の手法は、足元の事物を写すことにより自分の足、それも爪先を同時に写し込むのである。
あるいは部屋の片隅、写真にしてしまえば同じ構図になるものを、まさにそこにあった色彩でまとめあげる。それらを何枚かの組にして、ひとつの額という縁取りをして作品とする。それは現代美術が到達した地点でのコンセプト以外の何ものでもないだろう。
またそこに現われてくるのは原色の現代の色彩感覚そのものである。レインコートの赤、あるいは黄色。真赤な花。現代建築の影。路上に放置されたポスター。それらひとつ一つが強烈な個性を持って、私たちに迫ってくるのだ。そして何よりも強烈なのは右下に刻印された黄色のデートだ。ここにこのデートが入ることによって、現代の写真を作る作家としての写真界に対する反逆を読みとるのは、私だけであろうか。
ここでこの写真展を構成するもうひとつのものがあった。それは音声による、この展覧会場の演出である。黄瀬郎夫の聴覚による場への展開は、通常のこの種の展覧会に流れる音楽のかわりとして、独自の場を創りあげている。いってみればこの写真展は鈴鹿芳康と黄瀬郎夫と岡田悦子の三者による合作である、と云える。鈴鹿芳康のコンセプトといい、黄瀬郎夫の音声といい、岡田悦子のディレクションといい、同時時代に生きる感性の共有の産物と云えるだろう。ショパンのピアノを聴きながら。