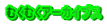
最新更新日 2012.7.21
写真への手紙 覚書
中川繁夫:著
写真への手紙 覚書
写真の意味/試論-1-
写真が心に触れるのは、その常套的な美辞麗句、<技法>、<現実>、<ルポルタージュ>、<芸術>等々から引き離されたときである。何も言わず、目を閉じて、ただ細部だけが感情的意識のうちに浮かび上がってくるようにすること。
ロラン・バルト「明るい部屋」
<カメラ・ルシダ>
「写真はその技術的起源のゆえに、暗い部屋(カメラ・オブスクラ)という考えと結びつけられるが、それは完全に誤りである。むしろカメラ・ルシダ(明るい部屋)を引き合いに出すべきであろう。」
「明るい部屋(LA CHAMBRE CLAIRE)みすず書房版P131」
「写真」とは何か、といった、この二十数年来、ずっと私が私自身に向けて問いかけてきたものについて、それらをめくるめく考えの行方は、いつも私自身の内にある螺旋階段をぐるぐると上がったり降りたりしていたようだ。
かって私は、この教養文化の枠組みの中で撮られてきた「写真」への問いかけに対して、ささやかではあったが、さまざまな意匠をまといつかせた言葉を繰り返しながら、「写真」について、またそれら「写真」をとり巻くさまざまなシュチエーションについて考えていた。
どうもこれまでの、「写真」をみてきた私自身のスタイルというのは、たとえばニエプスやダゲール、あるいはナダールといった写真草創期の写真家たちの業績やその時代の背景や動向、またアッジェやブラッサイといったパリの写真家たちの写真をとりまいた世界の意匠といったもの、また日本の現在にいたるさまざまな写真家たちが成してきた作業の累積を「いま」に引き寄せ、歴史的、技術的、芸術的価値からその意味を読みとろうとしてきたようだった。
私にとって、「写真」への興味の中味はいったい何だったのか。
それはずいぶんと以前からその兆候があったと思われたが、ちなみに最近になって、この疑問が私のなかに生じていた。
昨年秋ごろ私自身のなかで、私自身の生の在処は、やはり「写真」といったもののなかに求めているんだなということが、わかり始めてきた。
最初、針先でちょっと刺されたようなかろやかな痛みを、まどろみのなかの皮膚に感じた。おそらくこのときから、ほんの忍び足でそっと私に寄り添い、そうしてしだいに大きなうねりとなって押し寄せるようになっていった。
そのとき私は「アッ」と小さな声を漏らしたに違いなかった。それはほとんど意味不明の私の感情そのものの部類に属するものだった。
その日以降、私はいつになもなかったほどに精力的に、また自滅的ともいえる程に、私自身がかって撮り書きした私自身の記録をたんねんに読み返しはじめた。
そこには、自分の過去をふりかえったときに感じる、冷汗が出るような恥ずかしさと懐かしさの気分、つまり郷愁の感情が去来していった。と同時に私によって撮られ書かれた写真や文章の根底にあったものへの傾斜の仕方や思い方、また感情の生成といったものの回路を解きほぐし、いま一度、何も無かった地点から始めなければ何事も始まらないように感じた。
写真集を買い、評論集を買いあさった。そうして読むともなく見るともなくパラパラとページをめくっては書棚に放り込んだ。
一枚の写真が私にとって意味をもつとしたら、それはいったい何(どれ)だろう。私が撮った写真の群には、勿論、私にとってはそれぞれにかけがえのない思いが込められており、それなりの重量感をもって私に迫っていた。
「しかし」と私はそこに否定の疑問符をつけざるをえないのだった。
「写真を見ることはもっと愉しいものではないか。」
「写真を考えることはもっとリラックスしたものではないか。」
そう、記録性を拒もう。歴史的、社会的背景なんて拒もう。芸術の範疇が・・・・・・なんてどうでもいい。もっともっとプライベートな私に、感情がストレートに受けとめてくれる写真。写真は「明るい部屋」なのだ。
カメラ・ルシダというのは、「写真」以前にあった写生器の名前で、これは一方の目をモデルに向け、他方を画用紙に向けたまま、プリズムを通して対象を描くことができる装置であった。
<写真の在処>
「写真」の成立についてロラン・バルト(Roland Barthes 1915-1980)は、ストウデイウム(Studium)とプンクトウム(punktum)といった概念を晩年の著作「明るい部屋(LA CHAMBRE CLAIRE)」のなかで提起している。
ストウデイウム、プンクトウムはラテン語であるが、バルトはこれに次のような意味づけをおこなっている。
まず、ストウデイウムについて。
「あるものに心を傾けること、ある人に対する好み、ある種の一般的な思い入れを意味する。その思い入れには確かに熱意がこもっているが、しかし特別な激しさがあるわけではない。私が多くの写真に関心をいだき、それらを政治的証言として受け止めたり、見事な歴史的画面として味わったりするのは、そうしてストウディウム(一般的関心)による。というのも、私が人物像に、表情に、身振りに、背景に、行為に共感するのは、教養文化を通してだからである。」<明るい部屋、みすず書房版P38>
ここでバルトがいう、「ストウデイウム(Studium)」は、典型的な情報によって成り立ち、一般的関心をいだかせる写真ということで、写真の第一の要素としている。
また第二の要素として、このストウデイウム(Studium)の場をかき乱し破壊しにやって来るものを「プンクトウム(punktum)」と呼んでいる。
バルトの意味づけによればプンクトウムとは、「刺し傷、小さな穴、小さな斑点、小さな裂け目」であり「ある写真のプンクトウムとは、私を突き刺す(ばかりか、私にあざをつけ、私の胸をしめつける)偶然なのである。<明るい部屋P39>
こうしてバルトは、写真の在処についての論拠を、私に与えてくれているようだ。
写真は、写真家の目の前にかって実在したものが、写真家の感性により多かれ少なかれデフォルメーションされ、印画紙等のうえに二次元的に定着された一般的には銀粒子によるコピーとして存在している。あるいは、印刷物としてインキの濃淡として定着している。
写真において、印画紙上や印刷物上に現わされる対象(私にとっての客体)は、直接的な事象の外皮である。文字が、言葉が示すところの概念とはちがって、写真は直接的である。
ここ、一枚の写真により表出された内容(その写真が持つ対象の外皮)が私の目にふれる。私は、とっさにそこに示された事物を認知し写真の外皮に現われたかたちが何であるかを理解する。
私が興味を引かれるのは、そこに現わされた事物の在りように対する「私の興味」であった。
その事物が持つコードは、直接私のコードに殻りかけてくる。私はその語りかけに対し、その事物がそこに存在した意味、つまり背後にある概念の世界を嗅ぎとるのだ。
それはときには、戦争の悲惨であり、身体の美であり、風景の異端であり、そこに写真家がかくして撮った、撮らねばならなかった意味を嗅ぎとるのだった。おおむね写真を理解することとは、このような方法によっていた。
写真を理解するとは、提示された写真の被写体(写真にとっての主体)が指向させる共通のコードが持つ背後の意味を嗅ぎとっていくことだと思っていた。
写真の価値(在処)は、被写体(主体)が拘束されている制度的なるものを了解し、そこに意味を読み取り制約していくことだと思っていた。
写真を「見る」ことによる喜び、悲しみ、寂しさ、といったものは受け取る側にそれを理解する回路を持たなければいけないように思っていた。
確かに、そのように写真を理解しようと思えば、撮られた現場の状況と写真家の思い入れ(あるいは思想)が理解できなければ、意味をなさないものだと思われた。
しかし、はたして思考回路として、それがそのように導かれることだけが、「良い写真」であることの条件なのだろうか。
「人間」あるいは「ものたち」の糸が絡みつくような関係であって、こういった関係のなかで実際に影響をあたえ合うのは「あなたと私」「そのものと私」といった個別の関係をおいては、ありえない。
これらは、いずれも個別的であり、アノニマスなものではない。しいて言うなれば私と私の世界をとりまく他者との個別の愛憎関係(恋愛状態)とでもいったものに還元できるであろう。
私にとって、世にいう名作が名作として名を残さなければならないのは、私とのあいだでその写真がどういった位置にあるか、ということに他ならない。この位置関係は、感情の深淵(記憶との対話)であるように思われる。
私が「私の目でみた写真におけるプンクトウムは・・・・」というとき、それは、あたかも、不意打つように私の感情の淵深くをやわらかな刃物で傷つけてくるものだったといえる。
私の感情を深く傷つけるものは、決してその写真が提示する教養文化の歴史的背景ではない。あるいは、この制度のなかでの制度が規定するところの「美しい」ものでもない。これは美の解体による新たな美の発生、つまり自己の内に既成の美意識を解体し再構築すること。そしてイメージと感情の深淵(慟哭・狂気)の交差をみつめることの繰り返し。それは私にとって、最初は些細なことから始まった。
<ポートレイト>
私の手元に一冊の写真集がある。ステーグリッツ(ALFRED ATIEGITZ 1864-1946)が撮ったオキーフ(GEORGIA O・KEEFFE 1887-1986)の写真集である。
冒頭一枚、まだ若いオキーフの微笑みをもった上半身のポートレイト(1917年)がある。もう百年近くも前に撮られたポートレイトだ。撮影者ステーグリッツは私が生まれた年にこの世を去っており、いまやオキーフもこの世にはいない。
こういった歳月の経過にもかかわらず、私はここに撮影者ステーグリッツのオキーフにむける熱いまなざし(共有・共苦・水平理解・愛)を感じずにはいられない。と同時に、それはあたかも私への写真の在りようにとって感じとる何とも言いきれないイメージ。ほとんど無意識の深淵からほとばしりでる感情に由来するところの感性を噛むものなのだ。
黒い服に白い襟の上半身、オキーフの後ろには、オキーフがえがく絵があるのだろうか。アウトフォーカスになっている唯一の背景である。
正面を向き、ごくありふれたこのポートレイト。オキーフの充実した微笑み。これは新しい世界を自由奔放に生みだしていく知的な微笑みなのであろう。私は、暗箱のガラスに写された逆さのオキーフ像を前にしたステーグリッツのまなざしとオキーフへの共生を感じ取らずにはいられない。
このポートレイト一枚に向かっていると、私は柔らかい刃物でこころの薄皮をはぎとられるような気持ちにさせられる。
まだ雪が舞っているのに陽光はすでに春のきざし。晩冬の気配が爪で引っ掻くような足音をともなって去っていくあの気分、あるいはこころの解放が近づいたことを感じとるあの気分、とでも表現すればよいか。オキーフの初々しさが、幸福いっぱいとでも言いたげに私にむかってきている。冬ざれた感性が透明な大気に解放される。私はこのオキーフの私への向かい方にあたらしい写真(愛の記述)の在処を感じる。
私のこの向かい方は、もう一世紀も前にステーグリッツがオキーフに向かったのと同じまなざしでありたいと思う。ステーグリッツが暗箱のフレームにオキーフを独占したとき、それは時間としてはもうはるかかなたのむこうにあるのだが、私にはその一世紀前という時間差を少しも感じさせないのだ。
私は撮影者ステーグリッツが若いアメリカに青春から晩年を送ったひとであることを知っている。その時代と現代、私が生きる日本のいまとは、時代あるいは社会的背景が異質であり、ひとをみつめるカテゴリー(愛や憎しみといったものの感情)そのものが異質なものとなっているだろう。あるいは直感的には人間関係そのものが複雑化し硬質なものとなり、拠って起つところのひとをみつめるイメージが拡散してしまっているようにも感じられる。
ステーグリッツの時代から現在へ、かれこれ、それからすでに一世紀以上が経過しようとしているにもかかわらず、オキーフは新鮮だ。
この写真集は、私がこの写真をみるまなざし、つまりこの写真の歴史的背景や二人の関係、またそれぞれの個人史を、説明する知識をふくめて、私の前に存在している。ステーグリッツの内面の世界に思いを巡らすとき、一方で時代を背負った社会的存在としての個人史があり、一方では感情の流れというか、あるいは言葉では表現しえない内面史があったことに気づく。
たしかにステーグリッツは二十世紀初葉のアメリカで、写真というメディアを通じてアメリカを見てきたし「ギャラリー291」の成果や「カメラワークス」の成果を語ることができるだろう。あるいは近代写真の在処を示した、と。しかし、私がステーグリッツに対して持つこういった種の知識がどれだけこの写真、オキーフの私に向かうポートレイトを、私に価値あるものとさせるのだろうか。
いま、私がこの写真に向けるまなざしは、もっともっと私の個人的反応のなかで感動しているのだ。なおかつ、あえて私のステーグリッツへの興味をというならば、それは、彼の内面史あるいは肉声史と呼ぶもの、彼の内面の劇<オキーフとの位相・位置関係・干渉し合う関係>が体制からどれだけ自由でいられるか、を共有できるか否かだ。
この写真集を最初に見たのは、もうはるかに以前のことだったろう(注:1980年頃)。写真ギャラリーのカウンターに置かれたシンプルでいて上品な装丁の写真集を・・・・・・。
そのままついに最近まで私の記憶の奥深くにしまい込まれたまま、時折、記憶の像(イメージ)となって、ふっと立ち現われてはいたが、それはすぐに消えていた。
近ごろになって、その写真集をどうしてももう一度見てみたいという衝動にかられてしまった。なぜだったのだろう。この衝撃がどこから突き上げてきたのか私にはわからない。私自身がかられてしまった欲望の変種としての衝動を彷彿させてきた未定形のパルスについて、それがどういった質のものであるかを。おそらく私の記憶深くの原形質、内面の根底をとりまき構成しているところの疼きなのだろう。
いま、ストーブを炊いた部屋の机にむかって、この写真集との出会いの記憶をたどりながら、カーテンを開けると、暖気でくもったガラスの外は雪。しんしんと雪が降っている。しかしもう春が窓辺ちかくまでやってきている。軽やかに。
オキーフがはじめてステーグリッツに出会ったニューヨークにも、このように雪が舞っていたのだろうか。女学生だった彼女をとらえたステーグリッツのまなざし。そしてオキーフが私にむけるまなざしは、私を突き刺すばかりか、私にあざをつけ、私の胸をしめつけるのである。