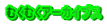
最新更新日 2012.7.21
写真への手紙 覚書
中川繁夫:著
写真への手紙 覚書
写真の意味/試論-2-
<未生のとき>
いま、私のまえに数枚のオリジナルプリントがある。タイトルはまだ無い。被写体は数個の「桃」である。撮影者はまだ学生気質を残したような若い女性だ。
プリント上の白から黒への諧調のなかには、数個の桃が草むらに転がされていることが判読できる。あるいは籠にに盛られている。自然な形といえばこれほど自然な姿はない。また、作為的といえばこれほど作為的な姿はない。
そのうえ、モノクロームフィルムで撮られたモノクローム印画紙で焼かれたものなのだが、桃の部分だけに一見では見落とす程度に色鉛筆で桃いろが施されている。
撮影者はこれによりあきらかになにかを指し示すことを意図しているように読み取れる。
目の前に差し出された写真には撮影者があり、写されている被写体「桃」は<かって、そこに、あった>もの「物」である。撮影者がどういう意図によって、そこにあった、あるいは置いた「桃」を撮ったのかといったことは、写真をみる側の主体、つまり現在の私にとっては、ある意味では、もうどうでもよいことである。しかし、私のこだわりに固守すれば、興味深いことなのである。
プリントの上に存在するものは「桃」のコピーである。日常の生活のなかで食卓でその季節になるとよく見かけるくだものだ。私にとっても桃という果物のイメージは、古くから日常の生活に根ざした季節の果物としてあった。最近になって外国産の果物(フルーツと呼ぶにふさわしいイメージの果物たち)をよく見かけ、また口にすることも多いが、桃は遠くから私たちの生活に密着してきた果物としてあった。
撮られた「もの」つまり桃そのものは視る者それぞれに意味を与え探らせてくれる。見る者それぞれに視たものへの思い入れがある。それは不明確だけれども遠い記憶の像に結びついているようだ。この不明確な記憶の像を呼び起こすときに湧き起ってくるそれぞれの固有の叙情性(無意識下における感情の流れ)とでも言おうか、愉しくさせる、寂しくさせる、等々のその源泉とするものに、私は注目している。
このように、私が興味をいだくのは、この「桃」のプリントが私に与えるクオリティあるいはインパクトについてである。このクオリティあるいはインパクトとは、撮影者における静物「桃」をカメラによってスケッチしたという行為とか、撮影以前にあった表現意図といったような、撮られた現場周辺での撮影者の在りようへの興味というよりも、私自身の受けとめかた、受け入れかたといった私自身の「所有する構図」にかかる部分である。
自分のものとする、あるいは所有したいという欲求は社会的につくられたものであると考えられる。このつくられてきた「所有したい」欲求の在処を探すこと。そして所有できてしまう社会構造の在処を探すことであるように思われる。
私が最初にlこのプリントを見かけたのは、徹夜に近い状態で議論を交わしたあとの昼下がりのことだった。さだかでない意識のなかで同じ撮影者のプリントの束を見ていた中の一枚がそれだった。
そこには街角のスナップ、晩夏のひまわりを撮ったプリント、石ころばかりの山のプリント、といったように類型的でなんの変哲もない(私にとっては興味のない)ものばかりがあった。「桃」はそのなかの一枚、記録の範疇から飛翔したと認知されるたった一枚だったが、異様な迫力をもって私に語りかけていた。
コメントの付けようがようがなかった。それらの写真を前にして言葉でもって批評することが目的の一つだったが、私は執拗にもこの時代のステロタイプ的な批評を、あたかもお茶をにごすという比喩があるそのようなスタイルで、与えていた。私は、私を突き崩す「桃」にはいっさいの言葉もふれずにいた。語ることの畏れを直感的に感じ取っていたのかも知れなかった。
そう、第一の直感的な印象といえば、おおむね少女の戯れにすぎないような感じであり、あえて批評の場に登場させるに及ばないもの、とでもいった様子だった。私が感じる「少女の戯れ」という感じ方は、あまりにも巷にあふれる雑誌記事や広告のセンスそのもの。なんら毒気のないステロタイプな感じ方であっただろう。その場では言葉にならなかったし他愛ないものだったのだ。
しかし、それは私のまどろっこしい神経を針先で突ついた。
本来、表現者(写真家)の姿勢は、他者(おおむね享受者あるいは鑑賞者)の持っている世界を視る観察方法と内面世界(ほとんど感情そのものが湧き出る源泉)を、根底から揺るがしてくるものでなければならないものだ。
その一枚のプリントが、私の目の前から消えてしまったあと、私は、記憶のあるいはイメージのなかで、その「桃」と対面することとなる。
撮影者はそのとき多くは語らなかった。ひとは自ら表現者であろうとするとき、寡黙であるより、おおむね饒舌になるもののようだ。また、表現し呈示したものへの批評に対しては、自己の正当なる由縁を主張するかのように身構え攻撃的に、自己弁護をしようとするものだ。だが、その撮影者は多くを語らなかった。
ひとは、生まれたときからたったひとつだけ固有の環境を持っている。そして、それぞれに異なる関係をそれぞれの環境のなかで結んでいくものだ。こういった自己を形成し取り囲んできた環境の集積を、私は「風土」と呼んでいるが、おおむねこの風土のなかにあって、普通は既成の枠組みをみずからの枠組みとして築きあげていくものだ。
カメラを持っての表現といったときにおいても、表現することを意図することは、おおむね既成の枠組みのなかでの価値観の構築といったスタイルに落ちつくようだ。
この作業はおおむね移り世の表層をとらえることしかできないが、としても多くに見かける巷の類型あるいは類似形としての外界の認識作業(風俗の表層をなぞっていくことによる制作)は、自分を見つめることのない偽表現者にはまさしく安住の場所なのだろう。
それらは鑑賞者自身の価値観が既成概念によって固められていることによって、あたかもその時代の中では熱烈な支持を受けることもありうる。
「桃」の撮影者が当初、そういった関係においてカメラを持ち、表現されたものの価値を模索するスタイルが、巷の類型あるいは類似形としての外界認識であったことは想像にかたくない。無意識のうちにカメラが向けられた「桃」の撮影者における「桃」の写真は、そのような類型あるいは類似形の範疇からはみ出した行為としてあった。
かってあった「論」あるは「読む行為」としての写真は、つねに社会表層の現象をとらえてくることに向かってきた。そして写真自体の輪廻作用によってイメージを増幅させ、そこに写真が拠って起つ社会的基盤を築きあげようとしてきた。この方法論から派生する行為により写真を撮ることは、おおむね事故の内面を洞察しない、つまり表現者の不在と不毛のなかでの「記録」だ。この「記録」という幻影こそ、「写真」を写真から遠ざける何者でもなかった。
「記録」という概念を根底としたこれまでの写真。この在りようとしての写真が認めてきた写真の範疇で、いまや写真とその行為は循環する袋小路の迷路に入ってしまった。このような視点あるいは方法からの「写真」の不毛が現在の状況であると認知するなら、現在は沈滞の時であると同時に、まったく新しい範疇からその表現領域を確保していく未生の時でもある。
私の感性をいちじるしい感動にまで高めてくれた「桃」の写真。私を突き刺すばかりか、私にあざをつけ、私の胸をしめつける。「桃」撮影者における気分のはみ出し行為(記録という概念から外れた制作方法)こそ、未生のときの固有の表現行為となるべき質そのものではないだろうか。
<まなざし>
私は生きている。その証として歓び、哀しみ、苦しみ、重くまた軽やかに時を過ごす。過ごしてきた時間が膨大になればなるほど、いくつもの場所でそのつど思い出をつくってきたようだ。ひとと私との関わりは、常に直接的なものだった。目のまえにひとがいて私がいた。いつも私が関わるひとへの興味の周辺から派生してくる事が、直接的に私に関心を抱かせてきた。事物に対する私のまなざしのとっかかりは、いつもそうだった。
およそ二十数年ぶりに訪れてみた大学近くの朝の珈琲店、私は記憶・思い出のまなざしてそれを見る。その後、幾たびかの改装をかさねて現在の店舗となっており、当時の面影は何もない。しかし、朝の珈琲をのむ私の目の前には、過ぎし日々に出会った人々の顔が、通り過ぎていくのだった。またそれらの人々を取り囲んでいたひとのいる光景として、その時代への感情がよみがえってくるのだった。
訪れた珈琲店は、私たちがまだ青春だったころ、毎週一回、日曜日の午後に集まっては何時間も一冊の本を手にして議論しあった場所だった。当時、よく夜行列車で金沢へ発った。凍てついた早朝の金沢駅から三十分ほどで内灘に着いた。内灘にはかって弾薬庫として使われていたコンクリートの塊がいくともあった。私の半生の生き方を決定づけた現代史についての興味は、そこから始まったのだったが、ここにもひとと私との直接的な関わりがあった。
それから十年が経って私は釜ヶ崎で写真を撮っていた。写真行為とは何かを考えていくなかでの結論は、写真行為を生活レベルで日常のものとすること。そうしてビデオカメラをもった若い感性のSとの出会い。
私のまなざしは、いつもプライベートな視点から始まっている。もし、私が今後も興味を示すものがあるとすれば、そのとっかかりはやはり非常にプライベートな興味からしか始まらないだろうと予測される。
かってわたしの興味は、このようにプライベートな源泉により生じていたが、それらの光景はいつも既成の枠組みによろ思想に収斂されていった。
価値の概容は、直感的に、既成の枠組みの中でしか生成されえないかのように、私は対応していたのだ。
類型あるいは類似形として外界を認識していくことが、価値を創造していくことの基本であるように感じていたのだ。
しかし、いま、このことは私によって否定される。私における視点(まなざし)の変遷をたどってきて、ここに大きな屈折点を見きわめる。
ステーグリッツがオキーフに向けたまなざし、若いひとが桃をとらえたまなざし。私はプンクトウムを得る。写真が私にとってかけがえのないものとなるとき、私のまなざしは木漏れ陽のように森の内部に這入り込む。
写真を覆い尽くしてきた一切の言葉を反故にしよう。私が語ってきたことばを反故にしよう。
私はいま、ここち良いまどろみのなかにいるようだ。この感覚は、私の、私だけが知る細部の感情が、私をこれまであった枠組みから引き離してくれる予感のようだ。
未生のとき、いま、私はこれから起こり来たる苦悩を引き受けよう。
ようやく春が訪れる解放感は、いまはない。しかし戸を開けよう。私のまなざし。私の解放。ほのかに、かすかな予兆を感じる。