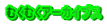
最新更新日 2012.8.11
写真への手紙 覚書
中川繁夫:著
写真への手紙 覚書
まどろみの中/試論-1-
時間の流れの中で、私はたえず心的な状態として感性の流出の中にあった。ときにはこの状態にある私を内省し「空しい」とつぶやき、あるいは「うれしい」とつぶやくのだが、感性は決して、こうした形容のなかに収まるものではなかった。(中川繁夫「私風景論」より)
<感性の淵で>
創作意欲というかすかな予兆の足音は、ちょうど昨年の晩秋の頃から」、私の感性の内ではじまり、日々とともに次第に大きなうねりとなって訪れてきていた。
最初、このうねりの波形についての「意味」そのもの、あるものごとが理解できる、あるいは解釈できるといったものは定かでなく、なにか疼いているなと感じる程度の得体の知れないものだった。
まだ態度として行動に結実していかない感性の淵で「何か」が始まって行こうとする、ほのかに、かすかな予兆を感じさせるものだった。
その気分は、夜明け前、不意に夢から醒めたときにのぞきこむ闇の深淵のような、こころを掻きむしられ宙ぶらりん感覚と同種のもののようだった。
「言葉」とはおおむね、形あるもの、あるいは自分が内在するこの文化総体が生成してきた形なきものの概念を指示するものだが、その気分といったものはまだ「言葉」として意味を生成しえないもの。
あえて言うなら感情の初源のものであり肉体が奮えるときに自然発生的に生じる叫びとしてあった。
私の感性は、つねに私の存在の外部からの衝撃により押し流されている。あるいは、流れる。この感性(感情)の流れのなかで、つねに生成されては風化していくものとしての行為があった。私はこうして感性の成りゆきのままに身を委ねている。
私にとっての表現行為の成立とは、おそらく感性(感情)を思想化するものであり、あるいは思想としてあるものを感性(感情)に還元するものの総体としてあるのだろう。
いま、私の感性は海あるいは生の表面をスイスイと滑っていく。それは根無し草のごとく、あるいは水草のごとく、あるいは雲の上のごとく、ふわふわっとした気分のなかにいるようにだ。
この気分のなかにあって、私はとても憂鬱だ。雑踏した世界のなかで流れのままに身をまかせている私の内面に立脚し、私の内に向かう思想の根拠地としての感触を持ちえないこと。
おそらく私を憂鬱にさせる原因は、この根拠地を喪失してしまった感覚のなかに含まれそうだ。しかしその憂鬱ゆえに、私は、私の感性にとって新しい領域が得られる予兆を感じているのだ。
<春>
初春の風の中で私の感性は憂鬱と孤独感に襲われる。これは突き詰めるところひらひらと、風に舞うように感性の自由を獲得しつつある証のように思われる。
自転車に乗ってふらっと外に出る。三月の風。私はゆっくりこぐ自転車のスピードが好きだ。新芽を吹きだした道端や川沿いの土手に群生する木立や草々を観察するともなく観ながら、私はひそかに決意する。
風化する感性をいま一度起立しなおすこと。
私は春の訪れとともに、弛緩する私の感性に竿を差そう。もう何をも畏れることはない。何にも拘束されなくてもよいのだ。私の内に向かって流れる感情の領域の限りにおいて、私は自由の翼を得ているのだ。
私は写真との新しい関係を求めている。自由!フリーダム!なんと快い響きをもって私に向かってくることだろう。歴史において常に詩人は自由を得ようとしてきた。しかしはたして自由とは、何からの自由だったのであろうか。
私の目の前に現れる社会・世間、つまり私には第二人称のあなた、との接点を求めて、なにからの自由になれるというのであろうか。写真を介在する私とあなたとの関係は、私の感性とあなたの感性の関係であらねばならない。
これまであった写真、つまり「写真は記録」からの自由を得ること。こうした断定のなかで一枚の写真が指し示す社会性とは、あなたとの関係の中に水平感覚として写真を見ること。あなたとの関係そのものなのであろう。感性の自由とは禁制・禁句(タブー)から脱却すること。あるいは自己を脱却させること。
<悲の時計>
記憶をたどってみれば1985年8月以降、私は写真制作を根底とする創造行為を休止している。カメラを持っての撮影は、盛夏の京都にあっては精霊を迎える盆の夜、六道の辻界隈での地獄絵複写が最後だった。
これも漸くカメラを持ちながら地獄絵複写をおこなったものだった。おそらく不特定多数の人たちを前にした形では永遠に公表しないであろうことを前提とした撮影だった。
それ以降、もうすっかりカメラを持って写真を撮るという方法を忘れてしまっていた。忘れてしまっていたことはそればかりではない。忘れてしまったなかには、次のようなこともあげられる。すなわち「もの」を作ること、ものを読む、ものを書く、ものを語る、そしてものを写す、といったような「知」を形成させるための行為の結果としてのことごとくだ。それから、かれこれ千日以上の日々が経った。
こうした日々、歳月が連続してきた結果としての今日(1988.3.21)、私は、私のとってきた態度と行動様式についてひとつの結論を下した。
「カメラとペンを持っていた一時期はすでに水平線の彼方に行ってしまった」
こう断定を下した今日、私は、私が書きとめ不特定多数の人々に充て、発信した最後の文章を読み返した。それには「釜ヶ崎物語」(季刊「釜ヶ崎」第9号及び第10号に掲載)と名付けられていた。
この私の「釜ヶ崎物語」へ凝縮されてくる意識の流れは、非日常の行為としてあった写真制作の方法を、日常生活そのものとすること、という命題に始まる。私の日常における表現行為がそのまま現代史としての歴史となること。病んでしまった国の病んでしまった人々。一人ひとりを訪ねて歩き、その個人史を記録していくこと。一人ひとりの生活記録の集積がこの国の歴史そのものとなること。写真シリーズ「無名碑」の発想はここからはじまった。
病み傷ついた人と向き合うことは、自分の病み傷ついている感性を、その照り返しとして観ることに他ならない。自己崩壊していく目の前の人にカメラを向けシャッターを切ることは、直接に私自身の崩壊につながる。当時、私のまなざしは「記録」という作業を根底においた表現の試みとして、またこれまであった「論」あるいは「写真の方法論」から「作品」への昇華として、私の内面を記録しようとしたものだった、と記しておこう。
ベランダ越しにやわらかい光が差しこむ昼下がりの自室で、私がなしてきた一連の作業「釜ヶ崎の写真記録と文章」の群をパラパラとページをめくり読み進めていくなかで、私は不覚にも涙してしまった。
最後の一節。「あんたがたが手に入れたと思っている素敵な生活の、根底をゆるぶるようなイメージを投げつけてあげよう。それも写真をもってだ。」
いま、私はここから出発する。自立のとき。1988年3月。
私は、新たなる私の日々の感情の流れを残していこうと思う。
いま、私は表現者としての感性(感情)流出の定着を試みようとしている。
日々の生の在処を問う連続の場として。
しかし私の感性(感情)の流出を受けとめる側、つまり鑑賞者(読者)として想定するところに不特定多数の人々といった概念はない。かりに相手を想定しうるとすれば、それは日々の感情の流れそのものを共有できるひととの間でのみ可能となるものだ。
私はこのようにして個別に結ばれる愛。感性の欲望を「悲の時計」と呼ぶ。そして私はひとつの決定を下す。表現行為(感性の欲望)における暗黙裡の希求は、冷めたこころを暖めあい、私を解体し、あなたと私が相互に理解しあえるところの究極のものとしてあらねばならないものだ、と。
表現者と鑑賞者の関係、表現者と被写体との関係は本質的にコミュニケーションを結ぶことが不能な関係であるのだろうか。カメラを持つこと。言葉を持つこと。この持つことを放棄したときのみ、私とあなたは同化することが出来るのだろうか。表現行為の宿命としてそれはあるのだろうか。表現者は常に持つことと捨てることとの紙一重の限界で行為を選ばなければならないのだろうか。
文章を、書き連ねる。写真を撮り、呈示する。な何故この行為がありうるのかと問いかけたとき、その答えとして、私には、表現行為を通しての相互理解、イメージとイメージの交換から究極の愛の姿、へと突き進むのだ。ここで位置関係として一方がカメラを持ったなかでの相互理解、究極の愛、を持ち出したとき、この内には表現者、たとえ愛の告白者としても、は非ざる心をもってしか成しえない人と人との関係の連なりだという悲観的要素が目に浮かぶ、あるいは脳裏をよぎるのだ。
「知」の形成と「生活の根底をゆさぶる(ゆすぶられる)イメージ」の創出。私がいま表現行為、あなたへのメッセージあるいは愛のコールサインについて、明確に答えられる言葉は、これをおいてない。
<終焉から>
私の写真行為において、なぜ、最後の被写体が「地獄絵図」だったのか。また、なぜ、そこにまで漂流して行かなければならなかったのだろうか。
いま私は、「過ぎし日々」を水平線の彼方に葬ろうとしている<私>が辿ってきた総体としての「私」を、様々な角度から、着付けた衣裳をはぎとり、こころの襞をひらけ、「それは何だったのか」とあらためて問いなおさなければならないのだろう。
私が外に向けてきたカメラで、被写体となったひと。ひとは生まれながらに病み傷つくメンタルを内在させているのだろうか。生存していくための諸制度(国・会社・家庭・夫婦・親子・・・・)からはじき出されてしまったひと。あなたと私。なま身のからだとそのこころ。あなたの病んでしまった内面に遭遇したときから、私は私の内側を見つめはじめたのだった。
私は私の生活周辺が無性に気がかりになった。無名碑と名付けたあなたの碑は、つまり私の碑そのものとして照り返されてきた。私は私の存在理由を問いはじめた。
私は、私の根拠地、私を培ってきた風土そのものである生活周辺を撮りはじめた。そうしてカメラで、私自身が病んでしまった経過と、病みついていった記憶をたどっていった。肉体と精神の構図を見つめながら、病むことの意味を問いはじめた。つまり肉体の在処を・・・・。
その最後の行為、つまり地獄絵図の撮影は、それまであった私の行動(釜ヶ崎や映像情報との関わり)のリアクションの終焉としてあった。
すでにそのとき、1985年8月ごろにおいては、かってあった「写真の方法」でカメラを持って街角にたつこと自体が、生きることの本質、美を創造することとは相容れない要素であるようにも感じられていた。
そしてそれまで私が考え辿ってきた「写真」の方法が、つまり生き方そのもの、美を創造する方法論、が解体し終焉を迎えていることを実感していた。と同時に急速に弛緩していく私の感性を見てしまっていた。
<狂気へ>
1977年秋から冬にかけて、私は「街へ」をメインテーマに大阪に立った。梅田界隈で、その数か月を経た。そして翌年の春から夏には原稿用紙に向かって「私風景論」の定着を試みた。
再度、カメラを持って大阪に通いだしたのは1978年9月2日。と同時に「大阪日記」と題した取材メモをつけ始めていた。天王寺から飛田界隈を経て釜ヶ崎の地へと足を延ばしていくのにそう時間はかからなかった。
三角公園に佇み途方に暮れてしまったという記憶、そこからそこで写真を撮っていこうとする私自身がどうなっていくのか不安でしかたがなかったといった記憶。
当時の取材態度は、まだ明確にはなっていなかったけれども私自身の内面の問題だけが主体であった。またそのころはまだ、写真は既成の価値軸を明確にするための美の属性として捉えており、一方で社会性を追求(非条理を告発)するといった写真の方法、つまりそのころまで継承されてきた記録(ドキュメント)の実践として捉えていた。
翌年の冬には、世間では薄められているが釜ヶ崎の地に集約的に表出するカオスとしての側面、あるいは政治性、あるいは精神性、あるいは「生のありかた」そのもの、と正面から向き合う姿勢を意識しはじめていた。自分は本質として虚弱な精神しか持たないと考えていた私自身が、自分に対する挑戦として自己を起立させていくこと。自己の弱点を克服していくこと。
私が自ら課せた主題は、荒々しい風雨に自己の精神を晒すことであった。なぜこのような思考が自分自身の内面に生成されてきたのか定かではないが、かってむさぼり読んだ小説からの感化。また二十歳の頃に私をとりまいた外的状況の中での自分の挫折と、挫折と認定するがゆえに終わらなかった青春のよみがえりに心が疼いたのかも知れなかった。
カメラを持つ私の目の前に立ち現われた被写体となった人々。その一人ひとりのこころの優しさと、優しさゆえに病んでしまう精神。彼らの内面へ向けるまなざしは、私自身へ向けるまなざしとなった。肉体を超えて透過していく感性の、ともに滅びようとする肉体に向かう感性。私の手には、唯一カメラがあった。
私の前に現われた労働者のいまの姿と過去をたどる聞き語り。無名の人々との出会いは、私に、私自身の存在理由を突きつけた。私の前にある裸の現実への照射として私の内面への裸のまなざし。私は論理でもって、このまなざしを解明しようと試みた。理論書を読み文筆を重ねた。そして、写真を撮るという接点での双方向のまなざしから、この体制を突き崩すための理論を模索した。私の感性は現世がタブーとする悪への価値軸へ飛翔しはじめた。
私は写真家であろうとした。移り世のドキュメンタリストであろうとした。世俗の表層をかすめとってくる「ミイラ取り」になろうとした。
私は写真の現場としての「釜ヶ崎」で足を踏み外しつつ、唯一、ムーブメントの現場としての「写真界」との接点に身を置いていた。
それまであった白々しい写真の世界と縁を切ること。独自の外化方法を見いだし展開すること。私の自立。そこから見えてくる光景は全て虚ろな人々の流れ。人は何をめざして生きているのだろうか。私は何をめざしているのだろうか。ゴールのない疾走は結局、身体を屍と化すこと以外にないように思われた。
そうした思考の一方で、「ミイラ」にならなかった私は、私自身の感性の崩壊を見ていた。ずたずたに切られた回路は、もうそのままでは恢復の余地がなかった。私は必死の思いでこの恢復の回路を模索した。雑誌「映像情報」や「季刊釜ヶ崎」の創刊、巡回写真展企画。もうだめ。はりつめすぎた糸が切れそうだった。