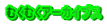
最新更新日 2012.8.25
写真への手紙 覚書
中川繁夫:著
写真への手紙 覚書
透明な写真/試論-1-
アーバスの作品でもっとも心を打つ面は、彼女が芸術写真の一番迫力のある計画のひとつ<犠牲者や不運なものに眼を向けること、しかしこういう計画につきものの同情を惹く目的ではなくて>に参入したらしいということである。(スーザン・ソンタグ「写真論」)
<谷間の風(シュールリアリストの死)>
漸く暑い日々が訪れた。それらの夏の日々、私は、世の中の全ては分類できる文脈あるいは文節によって成立する、と考えていた。歴史はそれ自体、絶対的な価値を有しており私が歴史を記述し創りうるその人であろうとした。しかし私のロマンが悲惨だったのは、私とあなたとの関係の在り方そのものに由来していた。
当時、私の思考の中心は、歴史への定着あるいは歴史の創造、つまりその時々に起きた事件の記録者であろうとすることにあった。事件を事件として認定すること。その認定するというそのことが、どこに由来しているのかを探ろうとしていた。
遠くて永い年月を経て培われてきた風土の感性をいまに受けた私。この感性に相克する知性。知の昇華によるロマン。この乖離からくる谷間の深淵を覗き込んだとき、ひとは一体どうするのだろうか。人間には感性があり、官能がある。いつも抑圧されたロマンの内部でしか生きられない文明人である私たち。私の精神は常に抑圧とタブーの狭間を逸脱する。
まだ青いススキの生い茂る草原に汗を流す。ときおり谷間をわたってくる風が頬を撫ぜていく。ちょっと高台になった山間のその土地は、私とあなたが手に入れた最初の楽園となるだろう。抑圧もタブーもない土そのものと、そこに根ざした植物群。雑草ひとつ一つの静かな生命は、ねじれた感性の私に、みずみずしくも迫ってくるのだった。
私は視る。この高台の土地に生成する全てのものと私の内部を・・・・・・。視ることの自由を得た私は、視るものひとつ一つが、かって現れたことのない新たな意味を持ち、私の知覚に迫ってくるのだった。私は私の内部の唯一点を覗き込む。私は体感熱くなってくるのを覚える。身体全体が溶けていくような感覚。まさに恍惚感覚。ひとはそれぞれにひとつの恍惚とする場面を持っているのだろう。
写真によって自分の恍惚を写したピエール・モリニエ(PIERR MOLINIER)は、自分に恋した典型だったのだろうか。閉ざされた部屋。愛の抱擁は恋愛を物語る。視ること(表現)の自由とは、体制内からの離脱を意味する。
<夏の夢>
私の恍惚感覚は夏の終わり、晩夏の物語。私の感覚は自死の直前に恍惚状態(自己陶酔)の自分を残した芸術家の感覚と同化するように向かっているようだ。みずからの肉体の衰えとともに、肉体と精神の極みに挑戦し、肉体のタブーに挑むこと。あるいはこのイメージは、あの厳しい冬の物語に連なっていくのだった。
釜ヶ崎で青カンする労働者の群れ。凍える肉体が朽ち果てていく地獄絵図を見る。肉体は蝕まれ土と化していくが精神の解放は春へと向かう。
これまであった膨大に撮られた「写真」の数々と、これからあるべく「写真」を、どのようにつなげて見ていけばよいのか、と想い巡らす。この思いは思想のレベルではなく、ほとんど幻。感情と同質のもの。感情:センチメンタルそのものだ。私にとっては「いま」を介して「写真」の在り方が歴然と異質なものになる筈だ。
ずいぶん以前からの解放すべき課題を持ち越したまま再々度、私は盛夏を迎えた。最近のいくつもの夏はあまり活動的でなかったので、おそらく今年の夏も怠惰な日々を過ごしそうだが、微かに官能的な興奮を知覚しているので、私はシュールリアリストになったようだ。
写真固有の価値と写真表現の領域は、発明の頃から記録(ドキュメント)としてあった。撮影された一枚の写真は、被写体となった事物、人々や風景の前にカメラがあったことを証明していると捉えられてきた。写真のリアリティは常にこうした信憑性にもとづいて解釈されてきた。
写真はかって存在した「もの」のコピーであり、かってあった存在の疑似存在としてあるとされてきた。このようにして写真の第一義的な形式は、カメラの前にあった「もの」が印画紙に定着されたものである。写真が記録であるという認定は、このように存在した事物のコピーであると認定する知識のうえに立っているのだ。そして写真の価値は、その内容にあるのだと。
写真の記録性は、このように見る限り、あたかも永久不変の真理のようにもみえる。確かにそのとうり、写真は限定つきではあるが記録そのものである。しかし私はいま、写真は本当に記録だったのか、という写真の本質に迫る疑念をいだいてしまったのだ。形式としての写真の存在と、撮られた事物のなかの価値の間に、そのとき不意に、何処からともなく風が立った。
はるか昔のこととなったが私は大学生になった。十代には日記から詩へと移行した私の表現方法は、その頃からいっそう文学に魅せられて行動派文学青年となった。政治参加という言葉が流行していた。そういったなかでの私の青春。外化する自分と内なる自分の葛藤。肉体と精神の乖離を意識しはじめるのが、そういった時代だった。
週に一回の読書会で議論しあった記憶。内灘は基地闘争の最初であったし、赤軍は私の世代の突出部分であった。突出できなかった私たちは、仲間どうしで同人誌の編集に携わった記念碑である。その後いくつかの小説家の死を経過させるなかで、写真におけるダイアン・アーバス(DIANE ARBUS)の死は、次第に「死と生」の重さを私に教えてくれることになった。
<涙の谷>
肉体的には大きく病んだこともなく、ここまでやって来たが、起伏する精神の連なりとしては、そのつど病んでいたようにも思われる。文学、音楽、また視覚芸術で、読み聞き見るだけにとどまらず、みずから創作していこうとする気持ちが沸いてきたときから、私は病に犯されつつあった。私にとって芸術とは間の淵に立つことであった。
この春が訪れる少し前、私は私自身によって私の生のあり方を問い直しはじめたのだった。いつの場面も外世界と私の感情との相克として、一生懸命に生きた。生きるということが衣食するだけのことでなくなったその時から始まった私のエンドレスゲームが延々と続き今に至っている。
春の訪れとともに、密かに自由を手に入れたいと思った。そして、私の内面において手に入れた自由。そのときに見えた感情の深淵は、十分に生きること、身体を維持していくといった生活レベルでの生命、の意味を問わせるものであった。
1971年にみずから死してしまった写真家ダイアン・アーバス(DIANE ARBUS)。最近の私の生きざまの中で、ひとの死に対するいくつかのこだわりがあるが、これは、どうも私がこれまでに生きてきた中で育まれてきた社会性(風土に根ざした視覚)とは裏腹な、プリミティブな私の感性のよりプライベートな部分からくるこだわりのようなのだ。
自殺してしまったアーバスの写真は、以前から雑誌の特集などでよくみかけていた。しかしそれらは断片的で、特に深い興味があったわけでもなかったので、これまで深く私のこころを掻きむしることもなかった。
白い部屋にぽつねんと座した私の胸に夏の夕暮れが迫ってくる。遠くから日暮らしのミンミンと鳴くのが聴こえる。女生徒の喋り声が流れていく。まだ写真撮影に精出していたころの記憶が甦ってくる。場末の踏切で赤子を抱いた若い母親がいた。西日が母親を照らして何か物悲しくも見えた。写真に撮られた生活風景を思い起こしながら、こうして黄昏に近づく時刻を過ごすことは、私を不安の淵に追いやる。
なにが直接のきっかけでアーバスの写真行為に興味を持ち出したのか定かではない。しかしこの感覚は千日以上の日々をかけて私に浸透してきたものだ。そのころよく訪ねたギャラリーで、アーバスの写真集を手に入れて欲しい依頼をしてから数か月後に手元に届いた。眠られない真夜中に書架から取り出して数分間、印刷されたアーバスの写真を眺めたものだった。
写真家における写真行為が、意識の深層において「覗き見習癖」から解放されて被写体と共有(共犯)関係を結ぶとき、写真は迫力をもって飛翔していく。アーバスはソーシャルなランドスケープ(社会風景)として、彼女が生きた時代の外側を撮り続けた。次第に歴史とか文化であるとか写真が持った時代のテーマを超えた人々の存在と向き合っていった(向き合ってしまった)。
私の感性が捉えるところによると、これは来たり来る世界と、その時代の限界(タブーとされる世界)に挑んだ内面で、時代を生きたように感じられる。なぜ彼女がその地点に至ってしまったのか。私の興味と興奮は、そこへ至らなければならなかった必然性、つまり彼女のメンタルの構造解析に向かうのだ。
固有の文化内において思想化されえない部分、疎外され隔離されているがしかし、その固有の文化内に共存する部分。隔てた壁を通過してあらゆる理論の以前にあった空白の世界。白い閃光をプリントした写真のように、それはアーバスを襲った。そして彼女は自分を見た。
アーバスがアパートの風呂場で自殺したのは1971年、ベトナムとかかわったアメリカがいちばん不幸だった時代。翌年1972年にはニューヨーク近代美術館で112枚の展示による回顧展が催された。私が彼女に興味を示すのは、こうしたアメリカの時代状況を背景としたなかで、彼女とその作品をどのように捉えるかといったことではない。
もちろん人間が生きていく行為そのものが、その時代の産物であり、彼女の場合は写真行為そのものが、彼女の時代を構成していた。また作品を理解することは、より大なる光景や背景をぬきにしては語れないことも、私がこれまで学習してきた範疇から考えて、承知のことである。しかしいま、あえて私はそのような切り取り方で人間アーバス(その時代を生きたその人)を捉えたくはないのだ。
私が興味を抱くのは、彼女が共有した被写体との関係と、関係をもったときの彼女自身の精神のありようなのだ。写真家アーバスの内に社会から疎外された被写体を撮り込んだとき、彼女にとって時代のプンクトウムは、題名のつけようのない異端者としてあることだった。
それは非常にパーソナルな部分での彼女の内面の劇について、どのような軌跡を描きながら放心状態あるいは恍惚状態となっていったのか、ということである。異端者としての感性が自分の中に存在する自覚を、アーバス自身、まどろみのなかで気づいたのにちがいない。その気づき方に私は注目するのである。
写真は魔である。あるいはこの「写真」を「芸術」と置き換えてもよい。芸術は魔である。カメラを携えた芸術家アーバスの前に現われたのは、文明・文化を捉えるという写真の文脈を超えた被写体であった。目の前にあるものが、まさにそのものであるということ。それらが撮られて現わされたものは<かって、あった、もの>それ自体であったが、それ以外のなにものでもない。この「なにものでもない」ことが重要なのだと思われる。
アーバスの写真が、いかにして撮られてきたかを論じたとしても、ことの外容をなぞっていくだけである。もっと透過した、深い森に這入り込むかすかな木漏れ陽のように、ほとんど透明に輝く光である。
芸術が知性と本能との葛藤あるいは結合の中から生成されてくることは事実であろう。そして作家が示す興味の対象へ深く傾斜していくことによって制度の枠を踏み外すことにつながっていく。
アーバスによって撮られた被写体への同情の気落ちはない。たしかに人間社会の犠牲者や不運な人々には違いないのだが、撮られた人々は同情されることを拒否している。むしろそれらの人々がもつ魔力の金縛りに会う。それまで写真家が持ち得た思想や文化内においては理解不能、あるいは理解を拒むものとしてある。つまり内容の明白な意味を問うことは、ほとんど価値がなさそうなのである。
人間には尊厳として固有に与えられているものがある。私たちはこの固有に与えられたものを取り巻くさまざまな意匠を身に着けているが、この意匠のひとつ一つを剥ぎ取ってしまったとき、私たちには何が残るか、あるいは私たちは何を根拠に生を営むか。
私に突きつけられたアーバスの写真から受けるプンクトウムを理解する感覚とは<このこと>であり、この感覚を思想化しない<できない>ことのなかにあるようだ。
彼女は撮影するということが、理論の以前にあるもの、撮影そのものを正当化する必要を知らない透明な文脈を、外部世界との遭遇のなかに獲得した<参入していった>のだった。そして、被写体がそれ自体としてあったものが<そのもの>であるということへの直感的な経験が、アーバスを解放したのだと思われる。