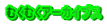
最新更新日 2012.8.25
写真への手紙 覚書
中川繁夫:著
写真への手紙 覚書
透明な写真/試論-2-
<無垢>
かって自死した若いビデオ作家Sの足跡をたどってみる。彼女は共に生きる時代の中にあって、人間の幸福とはどのようなものだろう。あるいは人間が幸福な状態とはどういう場面なのだろう、と必死になって考えていた(イメージを喚起し想像の中に生きていた)ように感じられる。
Sとの最初の出会いは、私の初個展を見に来てくれて、その頃はまだ二十歳前で、感性豊かな少女、といったように見えた。Sらはその頃、時代に先駆けビデオ制作グループを結成していた。数年後には会社組織にまで発展させていたけれども、おおむねSが夜に稼ぎ出す資金でグループを維持していた。
Sは釜ヶ崎に生活を営む人々に興味を示し、同化しようとするほどに深く傾斜していた。当時放送局取材で使う本格的なビデオカメラを回しはじめていた。Sの内面のなにが共鳴したのか、取材の現場では、理屈というよりその最初から感性のおもむくままに、明朗に立ち振る舞った。若い世代のSは、かってあった既成の枠組み、釜ヶ崎を政治問題としてとらえること、の外から記録を執拗に試みることによって、そこから排除されるのだった。
「わたしアホやからようわからへん」と私の前で幾度か洩らすことがあったが、執拗にビデオカメラを回し続けた。政治の理論武装でもって事に対処しようとする運動勢力から、その都度、肘鉄を食らわされながら、S自身が共鳴する場面と対決していた。
延々と続く組織の乱闘シーンが無秩序に記録され続ける。
公園に佇んだ初老の女性の独り物語る生活シーンが記録され続ける。
ゴミ箱の残飯を犬のように物色する労働者の光景が・・・・・・。
暮れる夕焼け空を見てなにを感じるか。
聡明なブルーの空を見てなにを感じるか。
たんたんと流れる雲をながめてなにを感じるか。
病み傷ついていく感性を、感性のままに受容し向き合う。
出会いから数年経っていた頃、何処かで、ほんのしばらく、ふたりだけになったときのこと、何とはなしに「最近、美しいものがようやく、本当に美しく見えるようになった、と言わはったね」とだけ、ぽつりとSが私に言った。共に釜ヶ崎取材を経験し、現場での苦悩したことに裏打ちされたなかで、Sも苦しんだのだなと私は思った。
その冬、私は東京へ研修で三カ月間不在。春に帰ってきてしばらくすると、Sがちょっと変だ、という噂を耳にしたが、冬以降再度会うことはなかった。私の個展開催中にひとり京都へきて、私は会場に不在で会えなかった。
その数日後自死した。直前にテープを回し、残されたホームビデオには、自宅でおばあさんと一緒に、風呂に入って会話する。おばあさんの背中を洗う・・・・・・。そして自分の姿の一部始終が記録されていた。
Sのシンガーソングライターとして歌う声がどのような音色をもっていたのかを聴く機会を逃してしまったが、私の手元にはレコードジャケット用にと撮ったポートレイトが唯一残された。
Sもまた、自死の直前に恍惚状態(自己陶酔)の自分を残した。ドキュメントが自分の内側を見つめることから始まり、みづからの視点を被写体と共有する。同じ地平に置く。みづからの内面に取り込んでいく。このことによって表現者となっていく。この時代の要請とスタイルを体得してしまったのだった。
時代は春へと飛翔していく。Sはみづからが育まされたこの世の美を解体しつつ、みづからの美をその精神の流れの中に育んでしまった。それはあたかもビルの屋上から可憐な花が咲き乱れる地へ舞い降りたかのようだった。
私はいま、それらの日々の出来事を語っておかないと、このまま消えていってしまうという、そのような幻覚に襲われている。人が病み傷ついた人と向き合うことは、自分の病み傷ついている精神を、その照り返しとして視ることに他ならない。
崩壊していく目の前の人にカメラを向けシャッターを切ることは、直接に私自身の崩壊につながる。新しい感性の発見は、歓びとともに「生」の理由を根底から問わせるものだ。生の希望と同時に死の誘惑が、荒涼たる部屋に忍び寄ってくる。季節は再び冬へ、冬の旅。
カメラを持つ手の前に立ち現われた被写体となった人々。そのひとり一人のこころの優しさと、優しさゆえに病んでしまった精神。彼らの内面へのまなざしは、自分自身へ向けるまなざしであった。肉体を超えて透過していく精神の、ともに滅びようとする肉体に向かう精神。私の手には、唯一カメラがあった。
<透過する行為>
写真が向き合う現実は、いつも自分に向かう鏡としてある。パガニーニのバイオリンの音が私に迫ってくるのと同じように、ベートーベンのソナタが射る和音の一つひとつ、あるいは連なりが、私の胸に突き刺してくるのと同じように、一枚の写真が私の感情の深淵を掻きむしる。
そのような写真の在処を探してきて、私はとても遠いところまで来てしまった。青い鳥を探してきてこの夏。それにしても透明なブルー色に、私は出会ってしまった。夏になるといつも気になる光景がよみがえる今年の夏は、ようやく青い鳥を探しあてた感情にこころがふるえた。
小谷泰子が採った鮮やかなブルーの色調を満たした写真は、私の感性に、ようやく来たるべき処まで来させてしまったようだ。セルフポートレイトを撮る。カメラを扱う作家の誰もが一度や二度は、自分の身体に向けてレンズを向けるものであるようだとしても、これほどに透明なイメージを私に与えてくれた写真はなかった。
小谷泰子にとって、その撮り始めの最初から、被写体としての興味は自分であったという。彼女のこの写真行為の在り方を知ったとき、私は幻惑の目眩を覚えた。写真がこれまで持ち得たテーマは、常に時代に内在する権力の構図を背景に撮られてきた。
一枚の写真に表される被写体の構図は、こうした時代の文化が内在させる位置関係。この関係は写真家が立脚する被写体との位置関係とその視点が、存在した。しかし小谷泰子が示す<写真の構図>は、イメージそのものである。
作家と作品と鑑賞者の位置関係は、あたかも磁場のようでもあり、また水面に広がっていく波紋のような関係とでも名付けられるだろうか。私にはそのようなイメージが沸き起こってくるのだった。
私は、この小谷泰子の透明なブルーのイメージから受けたインパクトについて、振り返って見るとき、私はそこに私の遠い記憶のタブローを甦らせるのだった。屍朽ちて風化し土に還る。恐らく私の死者たちがそのタブローに甦っている。
私の解体された美は、ここに新たなる美となって、甦っているように感じられるのだ。透明な視線。透明な肉体。透過する光は、私に、写真の新しい関係を示唆する。
(Shigeo Nakagawa 1993.11.29)