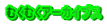
最新更新日 2014.8.9
釜ヶ崎物語 1979~
中川繁夫:著
季刊釜ヶ崎第一号に掲載

釜ヶ崎物語-01-
釜ヶ崎(’79・夏)
写真展とその空間
’79・夏
夏の夜の釜ヶ崎は、男たちの汗にまみれた熱気でむせかえった。酔って踊って陶酔する?ように喜び楽しむ夏祭りだ。
ステージで熱演する「のど自慢」参加者のエネルギー。それを受けて声援を送り、ヤジを飛ばす観客。その熱気を込めた観客は「盆踊り大会」へと引きつがれていくのだった。
この夏祭りの熱気を監視する警察のテレビカメラ。会場となった三角公園の周辺には、制服私服の夥しい数の警察官。何と悲しむべきことだろうか。そして腹立たしいことか。彼らは何を心配して祭りの一員ともならず、公園の外で隊列を組んでいるのだろうか。
公園に集まってくる労働者たちは、この日々の夜を待ちかまえていたのだろう。その顔は明るく、楽しく、まるで子供のように浮き浮きとしている。
第八回目を迎えた「釜ヶ崎夏祭り」は、労働者の巨大なエネルギー発散の場だ。そしてあらゆる場での抑圧、差別をはね返す連帯のシンボルだ。
しかし、何の苦もなく何の淋しさもなく何の悲しさもなく、本当の人間としての楽天性だけで無我夢中で喜び楽しめるなら、どんなに幸福だろう。
常日頃、労働の現場で、行政の窓口で、そして歓楽の巷で、抑圧される屈辱を、せめて夏の夜の夢ごとから、ひとときでものがれられる手段として、熱狂するのだとすれば、どんなに苦しく淋しく悲しいことであろうか。
休むことなく続けられている”炊き出し”は、この期間中もなお、釜ヶ崎にあっては日常のこと。食べる、という人間としての最低条件すら自らのちからで満たすことができない人々の群れがある。
この夏に、病院のベッドで過ごさねばならぬ人々の群れがある。結核。肝機能障害。その人々には、夏祭りの熱気が届いているだろうか。そして夏祭りに参加できた人々の中にも、即入院という重病患者もいる筈だ。
世間では信じられないことが釜ヶ崎には山ほどある。いったいどういうことなのだろう。結核患者の数は年々増加の一途だという。行路病死は日常のことだ。
夏祭りが熱狂的であればあるほど、いつも死と生との間で生を保っている人々の切実な、そして刹那の熱狂であるように思えてならない。
スキャンダラスな映像
この夏祭りを取材したテレビ番組を見た。肉迫ドキュメントというふれこみの、映像効果を駆使して構成されたものである。自然光での夜間撮影のためバランスの崩れた色彩。ハンディカメラによる画面の揺れ。説明はテロップで流す。同時録音。ぶっつけ本番。スキャンダラスな映像、とぼくは呼ぶ。そしてテーマは「望郷」。
現実をみすえる視点をさけ、見る人の情緒にいちばん同化しやすい部分で、釜ヶ崎を映像としてとらえている。スキャンダラスな映像は、世間の釜ヶ崎に対する視線に反論していくものでは、全くなかった。視聴者に向けてすでに持ちえている固定された認識を確認させるだけのものでしかなかった。何よりも重要なことは、ちまたに氾濫している映像と同様の、大衆の購読欲をそそらせるための、イメージ操作の域を一歩も出ていないということである。
釜ヶ崎がかかえている様々な問題は、ぼくたち全般にもおおいかぶさっているものと同質の問題でもある。その釜ヶ崎地域に集約的におおいかぶさっている問題に対して、それらの問題点そのものを全面的に捨ててしまったところから、映像を構成し処理している点に原因があるのではないか。
路上にたむろして酒をのむ労働者。パトロールする警察官。路上で寝こんでしまった労働者。ここは天国でも地獄でもないが、世間とは地が他tところ、というイメージ。公園に張りめぐらされたフェンス。炊き出しの現場。路上にならぶ露店。早朝のセンター風景。それらの光景を見慣れた目には、ごくありふれた日常の光景にすぎないものを、あたかも奇妙な光景のように、夜遅くの土曜日の茶の間に流れていく。
それらの光景はたしかに、奇妙なイメージを伴なって人々の目に映る筈だ。なぜなら、この辺境からの報告は、人々の深層のイメージを呼び覚まし、視覚でもって確認させる作用を伴なっているからだ。スキャンダラスな映像の効果は、人々がすでに沈澱させている深層のイメージと合致するのだ。
「あいりん」と呼ぶ呼び名が、当地釜ヶ崎では全く労働者のひんしゅくをかっているという事実を知らず、労働者自身の自主性はおろか人権そのものを認めていない世間一般の視点には、まるで別の人種が住んでいるようにも、不定形ながらイメージ化しているのではないか。事実が歪曲されたまま、映像がその歪曲を助長している、と思われてならない。
今やすでに、貧しさなどこれっぽっちもないというようなイメージをふりまくわが国の中に、その大都市のド真ん中に、釜ヶ崎の現実がある。そして、豊かな都市のイメージをつくりあげるために、その都市を築いた労働力そのものが釜ヶ崎であったという事実を見るとき、ぼくたちは、余りにも大きな誤った認識を持ってしまっているのではないか、と思う。
釜ヶ崎は決して特殊な場所ではなく、生活の場としてぼくたちと同じ地平にあるのである。ただ、釜ヶ崎の持つ問題点が、他の地域においては拡散してしまっているにすぎないだけなのだ。にもかかわらず、釜ヶ崎地域だけが、あたかも特殊なところであるようにイメージ化し、人々の深層に沈澱させていく体制のコントロールが、ぼくたちは見きわめなければならないだろう。
映像そのもののジレンマを、そしてその担い手である作家のジレンマを、解消していく方法として、もし視点の変換が可能であるなら、まさにこの視点の確立と独立が唯一の道であるといえるだろう。
イメージとしての釜ヶ崎
ぼくはこの夏、京都で”炊き出し”風景を含む釜ヶ崎の現実を撮った写真を展示する機会があった。展示空間が美術館である、という多分に気取った場であり、現実証言からの視点というより、従来からの芸術的視点から鑑賞されるという、写真にとって今、疑問に思い、いずれ是非を問わねばならないと思う場ではあったが、釜ヶ崎の存在すら知らないという若い人に写真を見てもらった後、次のような感想を聞かせてくれたのであった。
「最初見たとき、むかしの写真だと思いました。そして説明を読むと、今年の冬のことでしょう。信じられない気持ちです」と。
つまり、イメージとして現在の釜ヶ崎の情況を何の説明もなしに見たときは、それがその若い人が生まれるずっと以前の、敗戦当時の記録写真のイメージと酷似しているというのである。イメージあるいは虚像としての写真の、敗戦当時のものと現在の釜ヶ崎の情況と、いずれも、この若者にあっては自らの目で見た訳ではなく、映像から受ける疑似体験として、あたかも実際に体験したかのように知識として、そのひとのものとなってしまうのだ。
ぼくたちの知識の恐らく大部分がこのような疑似体験によっていることは、言うまでもないことだが、だからこそ作家の視点、セレクトする視点そのものが、固有の価値観を確立しなければならないのであろう。
また、中年の男性は次の様に発言をする。
「戦後の混乱期が今なお続いている。もはやその痕跡など残っている筈がないのき。実に考えさせられるなぁ」と。
実際にところ、ぼくはその時代の状況は何も知らない世代だ。だから、たとえば”炊き出し”や”青カン”という現実の釜ヶ崎の情況が、その当時の光景と質的に同等のものであるのか、異質のものなのかは解らない。しかし、都市の再開発にともなう構図から、今なお釜ヶ崎においてはそれらの光景が日常のことであるなど信じられなかったのに違いない。
写真を発表する場として、ぼくは以上のように展覧会というハレの場で、作家と鑑賞者という図式の中で発表したのであった。おおむね写真発表の場というものはそうであり、写真が写真としてのパブリックな場というのは、そのことであろう。だが一方、プライベートな関わりの中で、写す側と写される側が対決してつくり出される写真が、いつの間にか写される側が置き忘れられてしまうという図式そのものに疑問を持ち、何か別のところに写真が存在しなければならないように感じはじめて、そこからぼくの被写体としてとらえているプライベートな部分での写真を放出していくという試みにつながっていくのだった。
写真展とその空間
カメラマンは、みずから運動あるいは事件の主体となることはありえない、という。ただその側面からシャッターを押し続けるだけだ。目の前に起こる事件について記録し続ける行為があるだけだ、という。だが、本当に記録者としてあるだけなのだろうか。
この釜ヶ崎夏祭りへの協賛として行った写真展の持った意味は、写真を展示する、という行為をもカメラマンの行為の一部分として、ひとつの空間をつくり出し、作用したのではなかったか。
翌日展示するために写真を撮る。単なる記録者としての視点をこえて、写す側と写される側が、祭りというエネルギーの発散の場で、ひとつの空間を創出し、共有したのであった。その空間とは、いったい何だったのか。
八月十二日の初日、昼前からベニヤ板三枚のスペースに写真を貼り出したのであったが、すでにこのスペースを労働者たちがとり囲みはじめていた。何事が起ったのだろう。写真じゃないか。もちつき大会だ。この前の市会選挙じゃないか。誰々が写っているぞ。こちら側にも記録してあったのか。等々、これから繰りひろげられる前段として、すでに貼り出された写真の一枚一枚に、被写体となっている労働者たち自身が、熱心なまなざしを注ぎはじめていた。
夕方には、パネル上部空白部分に「写真展」との名称もはいり、「写っている写真があれば無料でさしあげます」との説明もはいった。そしてその夜までに、展示写真は約三分の一がなくなっていた。翌朝には三十枚程度が残されていただけだという。
翌日、昼過ぎから展示をはじめる。まもなく労働者たちが集まりはじめた。昨日の出来事が、今日写真となって貼り出されているという驚きの声をあげはじめた。展示された写真の中で、記念写真風のものはまだ数少ない。それでも、群衆の中に写っている自分の姿を発見し、ここに自分が写っているから、といって持ち去っていく。夕方になって、一段と写真展は盛況だ。入れ替わり立ち替わり、夏祭りに参加してきた労働者は、熱心に見いっていく。日替りとして昨日撮影したものが今、展示されているという時間的親近感が、恐らく熱心に見入らせる要因なのかも知れない。
午後八時から、のど自慢大会がはじまった。ぼくは参加者全員の熱演をフィルムに収めるべく、ロングとアップで撮っていく。会場の熱気に圧倒されながら、熱演に声援を送りヤジをとばす労働者たちと一緒になってシャッターを切っていく。
夏祭り三日目の十四日。出来あがったプリントを持って三角公園へ到着すると、すでに労働者や子供が待ち構えてい、これから展示しようとするプリントの束を手にとって見はじめたのであった。もう一枚一枚、展示されていく速度で見ていくのでは遅いのだ。そして、展示そのものを手伝ってくれるのだった。
この写真展の反響の一端として記しておくが、その場の雰囲気をどのように表現すればいいのだろうか。この写真展が成功しはじめている、と感じる。当初、この写真展という全く初めての試みに、労働者たちがどんな反応を示してくれるか、というよりも祭りそのものへの圧殺勢力のイヤガラセに会うのではないか、といったたぐいの危惧もなくはなかった。それが、この反響の大きさに、ぼく自身が恐れをなす程の、予期せぬ事態となっている。とりあえず貼れるだけ貼り、手元に残ったものは順次補充していくこととした。べニアのパネルを前にして、労働者たちは自分の姿を探し出し、パネルから外し自分の所有とする。
昨夜の「のど自慢大会」で熱演する自分の写真を持って「これが自分だ。自分の姿だ!」と片っ端しに他人に見せ歩く労働者。貼り出された友達の格好や表情を、写された当人をも含めて批評しあい、全く好意的に、写真を前にして論議に花が咲いた。このような写真展の盛況を背景に、労働者たちはまた、カメラの前に立った。一人だけで、あるいは友達同士で、起立し背筋を張った無表情の記念写真から、ふざけあった姿を、あえて写してくれという労働者まで、思い思いにカメラの前に立った。
最終日の展示は、そのほとんどが、こうして頼まれて写した写真で埋まった。プリント枚数250枚。次から次へと取り外されていく。この光景を見守りながら、ぼくは一枚の写真の重みを考えずにはいられなかった。たとえ一日でもよい、こうして自分の写真を手にして喜んでくれる人々。つごうで亡失してしまったとしても、今ある自分の姿の写真を自らが持ったという記憶を残しておいてもらえるなら、あるいは自分にはこんな時もあったのだ、と自らの記録として一枚の写真がその痕跡を残してくれるなら。この一枚の写真の重みは、計り知れないだろう。
こうして、公園の一隅にて展開された写真展と釜ヶ崎夏祭りは終った。
プライベート写真から
あの写真展を熱心に支持してくれた労働者たち。そして熱気の夏を踊った労働者たち。また日常の中へ埋没し、仕事にはげみ釜ヶ崎へ帰ってきては酒を飲み、そして明日への活力としているだろうか。
あの写真展の空間が持ちえた意味は、いったい何だったのか。
最初の頃は、ただ被写体となりえた当地で展示された写真展というだけの意味があって、それは写す側の一方的な展示であった。ところが三日目の展示から、その内容が変わった。それは、写真展が写真展としてあることそのものより、労働者がカメラの前に立つことによって写真展が成立するようになったことであった。
名前もドヤ名すらもわからない労働者の、ポートレートを引き渡す告知板として、展示板が存在したこと。このベニヤ板の前に来れば、前日写された写真が手にはいるシステムとなって機能したこと。そして、この目に見える告知板が存在することによって、写真展への興味もさることながら、自分の写真が欲しいと思う労働者は、カメラの前に立つことによって翌日、写真を手に入れることができたこと。つまり写真展示という空間を介在して、写す側と写される側がダイレクトに結合し、合意しあい、感情の交流を持ち、展示そのものは、単に空間として存在したにすぎなかったことであろう。
こうして写す側と写される側とが、ダイレクトに結合したところから生まれるプライベートな写真が、展示される、という行為の中で労働者みずからが鑑賞者となりえたことであろうか。仲間同士で、あるいは見知らぬ者同士で、展示された写真をめぐって批評に花が咲いたこと。こうして限定された空間ではあったが、写真そのものがパブリックな位置をしめたのである。そしてカメラマン自身がこの写真展を演出したこと。会場となった三角公園で、カメラを下げて労働者たちとともに存在し、ともに写真展を鑑賞し、ともに批評しあい、結果としての写真技術の上手下手の論議を越えて、写す側と写される側が、人間対人間としてふれあえたのである。
写し写される関係。展示され鑑賞するという展示空間と第三者の視点。ここでは写真が機能する全ての実験がなされたといえるだろう。同時空間的にはプライベートな写真群が、時の重みをくぐったあとには、この時代の記録として、それはひとつの価値の体系に組み込まれるであろう。
今、ぼくには、写真とは何か、という問いかけに対して、ひとつの見解が導き出されそうにも思える。そして何よりも感動するのは、主役は全く写される側にあった、ということだ。このこと、つまり写真の原型へ逆流していくことから、これからの写真は、はじまっていくのではないか、と思う。
一枚の写真
現代写真術において、釜ヶ崎の労働者が一方的に撮られ、単なる被写体としてしかとらえられなかったという事実が、ここに居住する労働者自身がカメラを拒んできた大きな理由であったと思われる。労働者たちは、カメラそのものは拒んだが、一枚の写真そのものを拒んできたのではなかったのだ。
ただ、今ある写真の方法、写真論そのものがつくりあげてきた理論そのものが、手痛くしっぺ返しをくらっていただけなのだ。
この写真展の最中、自分の姿の写った一枚の写真を手にした労働者が、誇らしげに、「これが、わしの写った写真だ」と、まわりにいる人々に見せてまわった光景。すれ違う見知らぬ人を呼びとめて、手に持った一枚の写真を指して、「よく見てくれ、これが自分だ」と見せまわっていた光景。写真展開催期間中、街のあちこちで、そんな光景に出くわしながら、「一体、写真とは何だ!」と、つぶやくより外、ぼくは術をもたなかった。
この期間中も、一方ではひきつづき”炊き出し”は休みなく続けられ、”青カン”を余儀なくされている人々の群れが、釜ヶ崎にはあった。
越冬のセンター前で、「もうだめなんだ」と言った結核を病んだ労働者と、夏祭りの雑踏の中でめぐり会って、「まだ生きています」とつぶやいたあの苦渋にみちた顔、耐えて冬から夏を迎えた彼の苦悩を共有することはできないとしても、決してこの現実を忘れてはならないのだ。
夏祭りの熱狂は、死と生との間に生を保っている人々の刹那の熱狂であってはならないのだ。
一枚の写真は、巷のものであらねばなるまい。
一枚の写真は、街角の人々に夢を与えるものであらねばなるまい。
写真は今、まさに裸形の現実に向かって、証言しなければなるまい。
この時代の認識の手段として、そしてぼく自身の自己史の形成として。
1979・8