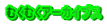
最新更新日 2015.3.16
釜ヶ崎物語 1979~
中川繁夫:著
季刊釜ヶ崎に掲載

釜ヶ崎物語-08-
あるいは写真行為論・2
(1)
釜ヶ崎の近くに阿倍野墓地がある。夏の終わり、ぼくは何年かぶりでそこを訪れた。強い日差しをさえぎるものもあく、額に、背中に、流れ落ちる汗を気にしながら広い墓地の一角にある合葬の碑を撮るためにだった。
墓地の外れに並んでいるこの碑には、裏に合葬された人々の数が刻み込まれている。現在においてもなお年間何百人という人々が路上で行き倒れ命果てている。様々な理由で、たったひとりで死んでいくのである。そうして引き取り手のない命果てた人々は無縁仏として毎年一度法要が営まれ、合葬される習わしとなっている。「合葬之碑」と刻まれた石柱には、こうして亡くなり果てた人々の数が無慈悲に刻まれているのだ。
ぼくは数年前から、無名碑という標題で釜ヶ崎で生活を営んでいる人々のポートレートを撮る作業を進めている。一人ひとりと生活の場を訪ねていって、話を交わしながら写真を撮る。言ってみればぼくのプライベートなアルバムとなる写真集だ。
<私は、これから、無名の人々の記録を、ひとつ一つと残していこうと思う。それは、私をとりまく、様々な生きざま、人にはそれぞれ、たった一回だけの「生」が許されている。それぞれの「生」には、かけがえのない日々があり、人はおおむね、その「生」をせいいっぱい、必死になって生きているのである。ひとり一人が、それぞれ無名であったとしても、その人にはかけがえのない母があった。父がいた。そして、その生の長さと同じだけの生活があった。私はそっと目を閉じてみる。私にも私が生まれ、「生」を営んだだけの生活があるのだ。私の、無名の人々の記録は、私との共有のきずなを見い出していく、私自身の記録に外ならない。(1981.2.9)>「無名碑に寄せて」と題した文章である。
写真行為って何なのだろう。たえずこう言った問いを設定して、釜ヶ崎の人々の生活の現場に足を踏み入れるのだけど、その問いに明快に答えるてだてをぼくは持ちえない。被写体となる人々と言葉を交わしていて、話題は酒のこと。酒を飲み、自分の身上を崩していくようにも見える人々の内面に、どんな感情が流れているのだろう。ぼくはふと立ちどまり、耳を傾ける。合葬の碑に刻まれた数と同じ数の生があって、楽しみも苦しみも寂しさもあって、それぞれに精一杯生きて、碑に刻みこまれる人々。
ぼくは写真行為において、こうした人々の側に立つ視座というものを獲得したいと思っている。写真は、現実に存在するものしか写らない。カメラを持って時間を共有すること。そのことによって、ぼくの目の前にあったものが写されて残される。写真は唯一の、ぼくとぼくの前にあったものとの関係のあかしだ。たとえ十束ひとからげの数字を構成するひとつとなろうとも、生ある間はそれぞれに独立した存在なのだ。
釜ヶ崎を撮るようになって、ぼくはもちろん、カメラマンとして行動しているのだけれど、この中で様々に考えをめぐらせてきた。そのひとつとして、無縁仏の合葬の碑を知ったときから、ぼくの無名の人々の記録行為が始まったのだ。
(2)
暑さでうだる夏の夕暮れ、ぼくは梅沢幸隆さんのアパートを訪ねる。彼はじん肺結核ということで病院に入院していたが、いまは西成区梅南のアパートに入居している。木造の三階建、アパートが密集する地域の一角にあった。その最上階の一室が梅沢さんの部屋だ。
鍵がかかっていた。聞くところによれば、最近、また酒びたりになっているというのだ。内側から施錠し、部屋の中でひとりぽつねんと座って酒をあおっているのだろう。
「梅沢さん!」
ドアをドンドンとたたきながら彼の名前を呼んだ。そうして何度か読んでいるうちに、内側から鍵を外す音がして、ドアが少し開いた。
「オレだよ、入れてよ。」
ぼくは少し開いたドアから中をのぞき込むようにして声をかけ、そしてドアを開けた。ぷん、と酒のにおいが部屋中に充満している。つい先日まで、酒をやめたと言っていた彼が、三日三晩、ほとんど外出もせずに酒をあびるように飲んでいるのだ。
汗でべとべとになった浅黒い顔に無精ヒゲが目立った。ぼくは部屋に入っても声をかける言葉もなくとまどう。四畳半の部屋にはフトンが敷きっぱなしになっており、テーブルにはワンカップが並んでいる。電球をつけない部屋はもう暗くなりかけていた。夕暮れの薄明かりは、ひとの心をむしょうに淋しくさせる。こんな生活。ささくれた心をなごませる何ものもない。感性がどっと崩れていく。淋しいのだろう。
半年前に訪れた冬の日にも、彼はやはり酒をのんでいた。酒をのむ。人間にとって、ごく日常のありふれた出来事だ。けれどもこの梅沢さんに限らず、ぼくの知る限りの人々が、結核を患い、飲んだらダメだというのに飲みだすと止まらなくなって自制心を失っていくのだ。
梅沢さんは、ぼくが部屋に入るなり酒をのむ自分が恥ずかしい、とでもいうように照れ笑いをしながら、ごめんごめん、といった仕草をした。酒をのむことの切羽詰った気持ちは、いまぼくにはない。けれどもぼくは無性に淋しい気分に襲われるのだ。酒をのむ。酒をのまずにはいられない気持ちが、おぼろげにもわかるからだ。ぼくがやはりむかし、デモの隊列に加わって別れたあと、あおるようにのんだ酒。どうにもやるせない冷えきった心を少しでも暖めようとしていたあの気持ち。その内側の崩れまいとして日々に崩れていってしまう精神の弱さを、ぼくには責める気持ちはない。
人はおおむね、精神を支えあって生きていかねば生きられない。ぼくにだってそういう気分のゆれ動きは、常にある。ただ少しだけ自制できる意志があり、その意志とは、この労働者たちより若干、世間というしがらみに拘束されていることによっている。
ぼくは無情にもカメラを取り出す。ストロボをセットし、フィルムをつめる。こうして梅沢さんの目の前でカメラを取り出すのは、もう何度目だろう。病院のベッドの上で、釜ヶ崎の公園で、そしてアパートの自室で。それらはいつもシラフの時ばかりだった。酒にのまれた彼の前でカメラを持って、ぼくはシャッターを切る。
「そのぶざまな姿を写しておくよ。」
とは言いながらぼくだって、手先はふるえているのだ。ひとのぶざまな姿を、平気でかすめとるほどぼくは強くない。
(3)
ある朝、ひとりの労働者が死んだ。
だれに見とられるのでもなく、静かに息とだえる。
からだをむしばまれて、生への葛藤に破れて死にゆく無名の人々。
この人々と同じ地平に、私もいる。
私の「生」における、生きざまとの葛藤が、だれとも共有できないように。
死にゆく人々の内を、私は共有できない。
ひとりの労働者の死と、それをとりまく空間を思うとき、その死は私の感性をかむ。
死は残された者への告発である。
不本意の死は、残された者への鎮魂歌でってはならない。
哀悼は残された者が共有する戦士のきずなであらねばならない。
その空間において、戦士は連帯し、凍える魂を暖めあうのだ。
傷ついた労働者の死は、私の感性をかむ。
いつのころからだったろうか、私は、私の写真作業において、こうした無名の人々のポートレイトを、撮らなければならない、と思った。このことによってのみ、私の写真作業が可能であると考えた。「人間とは何だろう」という、私の疑問は恐らく解答を見出せないだろう。私の「生きざま」が、試行錯誤の連続であり、「人間とは何だろう」という問いかけも、その中へおちいってしまうのではないか、と思うのだ。写真作業が、絶えず、この問題と交差しながらの作業であり、また、そこからしか写真の肉声は、聞こえてこないだろう、とさえ思う。しかし、私が、写真と言う手段を持つ限り、この記録作業は、私に課せられた仕事であるはずだ。
(4)
梅沢幸隆さんについてのメモ。
梅沢さんは現在53歳、長崎県天草の出身である。職歴。昭和20年、関釜連絡船の乗組員。敗戦によりこれを失職。昭和24年まで百姓をやったが、その後、北九州は八幡製鉄所の下請けで働く。現在の「じん肺」を患うこととなる事業所だ。その後、神戸に出てきて、港湾荷役作業に就くがゆえあって職を幾度か変えた。大阪の西成に住み、日雇労働に就くようになったのは昭和52年頃からで、54年に結核で倒れ病院生活が続いた。現在「じん肺」による労災保険を受給し、西成区梅南のアパートにて自活している。
ぼくが梅沢さんに初めて会ったのは、広崎病院糾弾が釜ヶ崎結核患者の会によってなされた頃、1980年3月だった。釜ヶ崎から入院した人々で大半を占める広崎病院に対して、待遇改善要求闘争の入院患者の当事者として、そして病院から脱出してきた患者の一人としてであった。しかし、この一連の糾弾闘争の取材に当たっていたぼくが、当事者の一人として梅沢さんがいたことを知ったのは、後になってからだった。
その年の夏、取材のために病院を何軒か訪ねた。そして阪奈病院の結核病棟で、白衣姿の彼と出会い、話を交わしはじめたのであった。この夏には、ぼくは釜ヶ崎の三角公園で第二回目の青空写真展を開催しており、これを見てくれた印象を語ってもらったのを覚えている。梅沢さんとの交流は、その後断続的に続いた。そしてこの日のアパート訪問となった。ぼくはいつもカメラを持っており、彼はいつも取材される側という関係において、その関係は成立している。
彼もまた釜ヶ崎で生活する単身労働者の一人だ。現在は病身であり労災保険を受給し、実際には労働に就いてはいないが、単身労働者二万人の一人だ。ひと口に二万人とは言うけれど、ひとそれぞれ二万個の固有の過去を持ち現在に至っている時代の証人たちだ。ぼくは、釜ヶ崎で生活する人々をじっと見つめるとき、戦後日本が生みだしてきた難民とでもいったようなイメージを描いてしまうのだ。
土木や建徳、あるいは港湾荷役。高度経済成長期に出稼ぎ、住み家を奪われ家族と離散し、都市生活者の底辺を形づくらなければならなかった人々の群。数万人を単位とした現代的団地が点在する都市にあって、中流意識を持った人々が圧倒的だという現在。それらの人々は釜ヶ崎労働者を分断し、別の世界のことのように無意識にながめている。世間では釜ヶ崎の生活を、自由だとか気ままな風来だとか言うけれど、現実は決してそんなものではない。ありうべからざる労働の形態の中で、この労働の形態、日雇労働、が容認されていることによって生み出される戦後日本の難民のように、ぼくはイメージ化してしまうのだ。
現実に存在する釜ヶ崎を、政治問題としてではなく、人間の内面の問題としてとらえていくこと。ぼく自身が生身の人間としてどうあるべきかと問うこと。ありうべき姿をイメージとして構築し、そのありうべき姿の人間として解放していくこと。写真に何ができるか。酒をのみ、みずからを崩していく人々の内側には一体、何があるのだろう。ぼくはふと立ちどまって考える。もちろん一人ひとりには個別の感情の流れがあり、想念があり、それらの表現として生きざまがある。ぼく自身の内部にも、おそらく同質のメンタルを見つけ出すとき、ぼくは彼らの生活、彼らの崩していくメンタルに、ぼく自身の根拠地を見つけ出してしまうのだ。
「釜ヶ崎」という言葉を聞いたとき、人々は定まらぬ様々なイメージを抱いてしまう。人々はおぼろげな過去の記憶をたどってみて、断片的に自分が得たことのある情報を思い浮かべる。たとえば新聞記事やテレビや写真の類だ。どことなく吹きっさらしの路上で、酒に酔って寝転んでいる。家なく金なく地位もなく、風来のごとく気ままな浮草のような生活。人々の気持ちは、そんな生活をうらやむと同時にけいべつする。しかし本当は、釜ヶ崎で生きることは、世間でうわさされる程、気楽なものではない。
ぼくの知りえる、酒をのみ、ぐでんぐでんに酔っぱらって体調を崩していく人々とぼくとは、その位置は少しも変わらない。彼らと自分は違うのだと思っている人々、自分たちとは違う世界に住んでいるのだと思っている人々がいたら、ぼくはその人たtにこう言ってやろう。あんたが手に入れたと思っている素敵な生活の、根底をゆすぶるようなイメージを投げつけてあげよう。それも写真をもってだ。(1985.1.19)