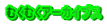
最新更新日 2013.11.7
中川繁夫の書簡集 2001~
中川繁夫:著
中川繁夫の書簡集

書簡003 shigeo nakagawa 2001.10.28~
絵画・音楽・19世紀末
ダスタフ・クリムト論へ
メモ(1):
ウインを舞台とした19世紀末から20世紀の初め、絵画、工芸、音楽の状況はどのようなものであったのか、を舞台に、文学、心理学などの要も加えながら、クリムトに焦点をあわせて、芸術のこれまでのあり方をさぐっていきたいと思う。ベルメール論につなげるための章として設定だ。20世紀を狂気の時代とするなかでの、ベルメールの逸脱論していくための準備として、近代科学の枠組み、写真の枠組み、ステーグリッツ291ギャラリーなど、近代化の諸相と芸術の諸相をとらえる。
メモ(2):
わたしの体験はトランスパーソナルを知る以前のわたしの閉塞状況。世界が閉塞しているという前提に立って、そこからの開放を考える。その道筋としての方法論。
ウインの音楽、ベートーベン、シューベルト、ワーグナー、モーツアルト。
音楽は世界観の安定のために・・・・の治療薬としての役割。
魂の調和、神の抱擁、人間の安定を求めての調和。
メモ(3):
ウインの喫茶店でもらったカップ2個とエピソードについての彼女とわたし。わたしの「芸術とは何か」の前提としての、これまでの世界の捉え方<調和>。19世紀から20世紀に至るウインとはなにか。宇宙観、宗教観、自然観、当時の芸術潮流、芸術としての絵画、音楽、ウイーン工房の工芸品。(パリの動向、19世紀中葉の写真の発明以降のパリ、印象派の動向、等)人間の調和を求めて、近代化、科学化に向ける近代に対して、芸術の近代化過程について、人間調和が基調ではないか。ベルメールの反抗の流れとは反対の。
メモ(4):
1789年、フランス革命後のパリ、写真の発明、科学の時代、新しい世界、希望ある世界、革命と解放、西欧科学、心理学のフロイト、マルクスの経済学、等々。19世紀初めのウイーン、1816年、ベートーベンの第九交響曲と荘厳ミサ曲の成功。音楽中心として、世紀末には分離派の運動、アメリカにおけるステーグリッツ。20世紀、第一次世界大戦と第二次世界大戦のヨーロッパ戦線、暗い時代、抑圧の時代<神が死んだ>ニヒリズムの時代。ベルメールの芸術について<破壊、魂の深淵の不安と崩壊、絶望する人間、社会の抑圧に対する<私>。21世紀は、宗教と科学と芸術が融合する時代だろう。
(1)
わたしの部屋に<接吻>と題されたダスタフ・クリムトの油彩のコピーがある。1907年頃の作品である。19世紀末のセセッションムーブメントは、ハンガリー帝国ウイーンにおいて、1897年に分離派が結成され、クリムトが総裁となった。
伝統と進歩という制度の表面を塗り変えていくムーブメントは、近代社会への移行期として、市民層の戸惑いを孕みながらも、社会的名誉を形成いていく結果となった。いつの時代にもみられる芸術家の行為として、このクリムトが織り成す一連の作品に表象されるイメージは、わたしが朦朧としていたそのころ、わたしの体内の美的感覚に埋め込まれてきたことを知覚している。
クリムトが創出するイメージに、戸惑いの議論を引き起こしながらも、市民としての人々の感性を、揺り動かしていくようだった。宇宙のなかへ、人間が吸い込まれていくイメージ。魂と身体が生成しはじめて、一個の存在となり、やがては消滅していく永遠への連鎖が、想起されてくる。そのきらびやかな愛と夢が現実と交じりあうとき、そこは存在と非存在の、生命と非生命の、ある種の欲望を掻き立ててくるようなのだ。
確かに神のイメージが秘める美の極みが、そこにはあるように思われ、わたしのエロス・欲情をかろやかに刺激する。そこには美の調和が高らかに奏でられているようにも思える。
100年後の1997年、写真家荒木経惟が分離派100周年記念展としてジャポニズム大股開陳吊りの緊縛写真を含む大展覧会が展開されたとき、観客はその直接的な構図に度肝を抜かれながら賛否の渦を作り出したという。こうして一般に公開される作品たちが、美徳や道徳の縁を拡大していくとしても、作家としての営みは戦略的公開の立場であるようだ。
写真に現代社会の混沌とした川底の欲望にエロスの意味を付与し、たしかに存在した都会の異端的風景として価値を創造し、現代社会の権力機構と商品流通の構図をそのままに、男の視線で女体を扱うのである。それは、見せる・見せられる関係の他者を、他者として認知する策略として、作家の内面の悲しみを交換するそれらの位置関係は、すでに制度に保護された場所でしかないようだ。
(2)
たしかにクリムトにおける油彩<接吻>(1907年)は、エロスを根元とする美の創生であったと思われる。<哲学>(1900年)<医学>(1901年)<法学>(1903年)シリーズ。また壁画のなかに描きあらわされる楽園のイメージ<ベートーベン・フリーズ>(1902年)は、愛のエロスが究極に行き着く場所として描かれているようにも思われる。
このようにわたしの記憶と出会うそのイメージが、わたしの官能を刺激する方法として、わたしの感覚を恍惚の彼方へと導いていくようなのである。としてもその恍惚の彼方にあるものとしての、一方の極みである恐れ怖さをともなうような、常にわたしがわたしの深淵を覗き見ようとしたときに感じる、宇宙空間での孤独感のような寂寞を、感じさせるものではないようだ。
鉛筆の線で描かれるデッサン<両手を頬にあてる裸婦><横たわる婦人>等々を見るわたしのまなざしは、女体への官能の解放そのものを内に秘めているようにも思われる。それらがわたしの生そのものへ優しさを与えてくれるとしても、意識の根元を踏みにじってくる怖さは、感じないのだった。
芸術作品とは、詰まるところひとの魂の深淵に秩序と安らぎを贈与するレベルで完結すればよいのかも知れないと思う。しかしわたしは、はたして、そのことをもって完結するとは思えないのである。
芸術が生み出す作品とは、もっと意味を解体し、存在を超えるものとして、彷彿とさせるものである筈ではないか。男と女の同化または異化、あるいは性そのものが溶解していく感覚を湧き立たせるもの、心身ともに滅びるような怖さ感覚、境界のないわたしとあなたの場所、そしてそれらの意識の解体と融合の繰り返しとしての空間が成立すること。恍惚感覚を創造し持続させること。その極みとしての解体と解放。
(3)
クリントが好んだという音楽におけるシューベルトのピアノや歌曲が、その魂を透明に純化させながら、わたしはそのリリシズムに心が洗われるのだが、純化される美しさを感じるとしても、それは宇宙の秩序を織り成していう。
こうした記憶の層が、元始のひとの記憶とともに、確かに羊水のなかに生成しているわたしに、性を贈与してきた。わたしが男として生まれてきた身体は、現実の存在として生きだしたのだった。
わたしにとっては、宇宙の生成と身体の誕生について<いまkに在る>こと自体が意味を持ってくるような、未来に向けたメッセージが必要とされる。すでわたしは生命の大半を生きた。すでに身体的には欲望が消滅しつつあるが、意識は無限に拡張していくように思われている。
これからわたしが試みようとしているのは、シュールリアリスト、ハンス・ベルメールが残した関節人形についての考察である。これはわたしの幼年時代の記憶の探求を含めて、わたしにおけるベルメールとの交感の質を探る作業になるようだと予測している。
ベルメールの関節人形とは、もう15年ほど前、偶然にも出会ってしまったといってもよいと思う出会い方で始まった。ちょうどわたしが写真集を買いあっていた時期、1985年前後のことだった。そのころの私自身の状況といったものの記憶を辿ってみると、その写真集を介在として、いくつもの物語へとさかのぼっていくことになる。
わたしたちの物語が、いつも悲惨な結末を予期してしまうのは、なにもわたしの習性だけに起因しているのではないようだ。というのも、これまであったいくつかの関係の、始まりから終わりまでの道筋を重ね合せていくと、そこにはよく似た分岐で、結局のところ選ばれた道筋の結果が悲惨だったからである。
※悲惨をとおりすぎれば信仰がある(変性意識)宇宙、神秘、信じるものとしてのシャーマン。
(4)
聴覚における感情の生成について。
ここではベートーベンのピアノソナタ29番を取り上げてみる。ぼくがこだわるのは、このソナタの特に第三楽章においてである。確かにピアノの音に対しての、ぼくの感覚の反応は、通常を超えていたのかも知れない。その音色への執着とでもいえばよいのだろうか。小学生の頃から、ピアノの音色と弦を打つ音には、特別な執着があったようだった。
みずから稼いだ労働の対価としての賃金は、ベートーベンピアノソナタ全集を購入するための資金に使ってしまったのだから、おそらく魅了されていたのだと思う。18才の終わりのことだ。シュナーベルのピアノでエンジェルの赤盤といっていた全集。一ヶ月の賃金15000円では足らなくて、それの倍の値段だったかも知れない。
しかしベートーベンのピアノ曲を聴きだすのは、その後10年ほど経ってからである。すでに30才をこえていたと思う。ここで取り上げる第29番第三楽章に何かしら不思議な感触を得るのは、30代の後半になっていた。何が不思議かといえば、聴くたびに、ぼくのなかに生成されてくる感情が違う、と気づいたことだった。
それよりもなによりも、このピアノの音の連なりを聴いていて感じることは、感性が崩壊していく感覚と、救済される感覚が、入り乱れることである。不思議な楽章である。終わりそうで終わらない、怠惰で退屈でイライラさせるかと思えば、徹底的にセンチメンタルを誘発する。奈落にある精神が、よりおおきな見上げる存在にひざまずく、あるいは祈る(信仰、・・・・この先に人間の解放、エクスタシー、真の信仰、聞き入れること、受容すること、解放すること・・・・)といった感覚を誘発するのである。
これはぼくだけが感じる感じ方なのかも知れないと思う。音楽を超えた音の連なりである。この音の空間は、きっと秩序を逸脱していく場所である。きっと音はカオスの闇からやってくるようなのだ。人間の知覚の根源の縁から生じてくる音である。その先は人間の意識を超えた領域であろう。音とぼくという身体の交差する場所がここにはあるようだ。