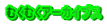
最新更新日 2014.1.1
中川繁夫の書簡集 2001~
中川繁夫:著
中川繁夫の書簡集

書簡004 shigeo nakagawa 2001.9.24~
写真への手紙・覚書
不器用な天使/ハンス・ベルメール論
1:
夢をみているのだろうか。わたしとあなたの波長が交感する場所に、なにか新しい得体の知れないイメージのオブジェが、出来てきそうな感触を得てしまったようだった。わたしのなかに何かが始まろうとしている。その感触を皮膚で感じながら、わたしは心地よいまどろみのなかにいようだ。
どうもこの感触というのは、わたしが母の胎内にいたころ、羊水のなかに生命を培っていたころの感覚のようにも思える。闇の向こうから淡い光がさしこんできている様子が、おぼろげながら知覚している。
わたしは太古の昔にあった<前世のわたしの存在>に支えられているような気分になっている。わたしのいまいる場所は、言葉という言葉を駆使して、意味づけようとすることが、できるようでもあり、できないような意味と無意味の間の領域のようだ。
わたしの感覚には、母の被膜をとおして確かに聴こえている。新しい世界が来ているのだよ。新しいわたしが来ているのだよ。幻聴なのかも知れないとも思う。幻覚なのかも知れないと思う。わたしも存在しているのかどうか確認できないのだが、あらゆる生命が起源のままで存在している。
すでに世界は滅亡しており、在るのはただ<浮遊してくる像>だけであった。わたしはこの浮遊してくる像のことを<イメージ>と呼んでいる。明確ではないが明らかに浮遊してくるイメージとして、次第に焦点が合わされてくるものの存在を知覚する。記憶と呼ばれる領域の存在でる。
2:
現像液のなかで、かって露光された潜像がたち現われてくる印画紙の面のように、わたしの記憶は表出されてくる。写真の現像は記憶の現像とよく似ていると思う。物質としては非存在の記憶と存在の写真である。かってそこにあったものが定着されること。わたしには見えるが、あなたには見えないもの。わたしの記憶の像は、そういう類のものだ。
言葉の交換によって、あなたにはあなたの記憶が想起される、と同時に類似の情感が場を満たすようなのだ。<共有すること>とは、場を満たす情感のかさなり容態をいうのではないか。磁場が発生しているのだとすれば、磁場をつくりだすエネルギーの交換そのものであろう。
3:
わたしのいる部屋に、もう弾き手がいなくなったピアノが置いてある。その上に架けられた絵は、グスタフ・クリムトの<接吻>。傍らのスピーカーから、シューベルトの即興曲が流れてきている。午後の陽が差しこむ部屋に、わたしは寝そべり庭を見ている。庭には色づきはじめた沙羅双樹があった。普請後、庭となったその場所には、もう何十年もひとが住まなくなった三帖の部屋があった。
わたしの記憶はさすらいさまよっていた。祖母の死の光景がよみがえっていた。このイメージはわたしの記憶として存在している。記憶のよみがえりと同時に、やるせない悔恨の感情が奥深くを揺さぶってきた。まどろみのなかのわたしは、母の胎内で、まだ性別が未分化のようなところにいるようにも思われた。
わたしを構成する細胞は、薄い皮膚と内臓を形成しはじめている。何かしら巨大なものなのか、極小のものなのか、分別がつかない闇と明の境目が、おぼろげに知覚されている。宇宙という空間なのか量子という空間なのか、わたしのいる空間が認知できないのだ。わたしは生まれ変わりなのだと感じた。記憶は前世のわたしの残影のようであった。
4:
書架からハンス・ベルメールの写真集を取り出してみる。<Die Puppe-人形->と題されたそれは、わたしの愛玩具が詰め込まれた秘密だった。いまわたしは、ベルメールの心の痕跡といったものを辿ろうとしている。あるいはベルメールの内世界と外世界との相関関係を見つめようとしている。それは情動の源泉のものであり、わたしがここにいることの根拠についての謎と、わたしは一体何者なのか、わたしは一体どこへいくのか、といったような根源的な謎につきまとわれるのだ。
わたしが見つめようとしている領域は、ひとが一個の人格を形成していく過程としての社会的存在から、その内面を構成している情感・情欲といったもの、その極私的無意識までの振り幅といったような領域である。その見つけ方は、そのひとの人格固有の世界観・宇宙観への探求である。そして、その根元を形成する感覚の発露としての情欲の考察とでも云える。
衝動は母なるものの源泉であるのかも知れないと思う。神=父性原理を基底としているならば、神を超える何かである母の存在であるかも知れない。社会は父性原理で動いている。近代社会は家庭の構造までも父性原理に従って醸成されてきたのだとしたら、それ以外への価値を見つけていくことは、困難な作業となるかも知れない。
5:
ひとの生のおける時々の行為を振り子にたとえて云うならば、振り幅の一方の頂点が、社会での振る舞いの極みとすれば、もう一方の極みは、無意識の層を含む極私的領域と云える。極私的領域は、本能領域を具現化することを含め、見つめていくことは、恍惚とする感覚を呼び覚まし、表層化していくことは、羞恥感をともなうものであろう。誕生し、生きている間、その人の振り子は、いつも振り続けられている。
振り幅は、生命のエネルギーである。自然界と社会制度のあいだをたえまなく振られ続けている。振られた振り子の両極は、いずれも制度を逸脱してしまう。
クリムトにおける極私的領域の極みは、エロスを宇宙空間に解き放つことだった。ベルメールにおける極私的領域の極みは、ウニカとの生活のなかで生じさせる緊縛という欲望を、内なる宇宙の恍惚感覚と交歓することだった。そういう視点で云うならば、わたしの極私的領域の極みは、1995年前後の究極未公開とする<プライベートルーム>と名づけられる映像群であろうか。
6:
ここで試論するわたしのディスクールは、言葉によって極私的領域に至っていたときの情欲とでもいえる感情を呼び起こさせるかどうかの試みだと云える。わたしは、わたしによって恣意的に選択される言葉を連ならせながら、これらの表出されたものを、文学領域に位置させたいとの思いがある。
無謀にもわたしの想念は、わたしの言葉自体を溶解させていこうとしている。意味と無意味、存在と不在、男性と女性、身体と魂、自己と他者、それらがすでに獲得している意味内容を、解体していくこと。そしてそれらを融合させていく道行として、あらたな意味を形成させる神話的な空間が、成立するかどうかの試みなのである。想像力における空間としての神話的空間、それはわたしを逸脱させにくる内発だ。
このディスクールにおける主な登場人物は、ダスタフ・クリムト、ハンス・ベルメール、およびわたし自身である。それぞれに生きられてきた年月と、作品が残されてきた年月は、社会性とアンモラルが戦いながら、魂のうちに向かう時代だった。それぞれの時代と地域性が持った制度と力の背景が異なることをも考慮しながら、わたし性の転移・変節・崩壊のその向こうに、自らを開いていこうとする過程を、辿っていこうとする。これは「イメージ発生論」あるいは「イメージ過程説」の実証なのである。
(2)
視覚におけるイメージ認識と感情の発生について。
ハンス・ベルメールの人形の写真を、偶然に見たのは1988年ころだったと思う。シュールリアリズムがブームとしてよみがえってきていたのかも知れなかった。人形の写真、それは女性体の部分としての脚、股間、関節といった部分。また胴体といった部分。虚ろで泣き出しそうな虐待された天使の表情を持った顔の部分。といったオブジェ化した女性体であった。および一連の実写の写真群があった。
次に手に入れたのは線描画集であった。それら一連の作品、女性体の交錯するイメージは、ぼくの感性を深く噛んできた。なぜぼくが、そのイメージに深く傾倒していくのかは、わからないままに今に至っている。たぶんベルメールの生い立ちや、彼が発表した地域と時代の背景を考察したところで、明確な答えは返ってこないようにも思う。
ではいったい、なにが直感として感じさせるものがあったのだろう。かなり確証的に言えることは、性的欲情の抑圧にたいするリアクションとして、ぼくの内面をとらえた、といえるのではないかと想起している。そしていま、この欲情の抑圧といったものとしてぼくが認知するとしたとき、ぼくの身体と感性の生成の関係におよばなければ解決しないように思いだしているのだ。
ぼくはこれらの認知の過程において、ぼく自身がとらえる領域といったものの範囲を知る必要があった。ここには開かれた身体と感性の関係は存在しなかった。現実の社会生活における日々の怠惰からやってくる、閉ざされた出口付近にベルメールの写真と遭遇して感じる感じ方があった。
その場所は、カオスの縁としてあるのだろうか。その一歩先の領域は、混沌とした感性の崩壊する場所、といったイメージである。感性の崩壊は、そのまま身体の解放につながり、そして自我と肉体が重なることそのものである。おそらくその場所は、そのことによってエクスタシー状態に入ることの入り口領域である。
ぼくの身体へのこだわりは自虐的である。崩壊感覚である。これはナルシストとの裏返しの衝動だと思うが、それはぼくの青春の頃からの傾向といえばよいのだろうか。身体を持つことの重さ。身体を維持することの嫌悪感。身体の消滅を欲した日々の苦悶。こういった記憶の光景から導き出される言葉は、美しい光景を夢見ると同時に、暗い深部の欲望を虐めることで、解消しようとしていたのではなかろうか。
異常と正常の境界があるとすれば、ぼくは異常の領域に棲んでいたのだろうと思う。小学校上級のころのぼくの最大の恐怖は、ぼくの心に写しだされたイメージが映し出されるテレビが発明されることだった。その頃のぼくの異常な領域とは、女体を想像することと自慰することのふたつであったと思う。それはイメージとぼくの身体が、交差する場所としてあるようだった。
(3)
写真に、現代社会の混沌とした河底の欲望にエロスの意味を付与し、たしかに存在した都会の異端的風景として価値を創造し、現代社会の権力構造と商品流通の構図をそのままに、男の視線で女体を扱う。それは見せる・見せられる関係の他者を、他者として認知する策略として、作家の内面の悲しみを交換するそれらの位置関係は、すでに制度に保護された場所でしかないようだ。
芸術作品とは、詰まるところ、ひとの魂の深淵に秩序と安らぎを贈与するレベルで完結すればよいのかも知れないと思う。しかしわたしは、はたしてそのことをっもって完結するとは思われないのえある。
芸術が生み出す作品とは、もっと意味を解体し、存在を超えるものとして、彷彿とさせるものである筈ではないか。男と女の同化、または異化、あるいは性そのものが溶解していく感覚を湧き立たせるもの。心身ともに滅びるような怖れ感覚。境界のないわたしとあなたの場所。そしてそれらの意識の解体と融合の繰り返しとしての空間が成立すること。恍惚感覚を創造し、持続させること。その極みとしてのわたしの解体と解放。
こうした記憶の層が、元始のひとの記憶とともに、確かに羊水のなかに生成しているわたしに、性を贈与してきた。わたしが男として生まれてきた身体は、現実の存在として生きだしたのだった。
わたしにとっては、宇宙の生成と身体の誕生について<いまここに在る>こと自体が意味をもってくるような、未来に向けたメッセージが必要とされる。すでにわたしは生命の大半を生きた。そでに身体的には欲望が消滅しつつあるが、意識は無限に拡張していくように思われている。
これからわたしが試みようとしているのは、シュールリアリスト、ハンス・ベルメールが残した関節人形についての考察である。これはわたしの幼年時代の記憶の探求を含めて、わたしにおけるベルメールとの交感の質を探る作業になるようだと予測している。
ベルメールの関節人形とは、もう15年ほど前、偶然にも出会ってしまったといってもよいと思う出会い方で始まった。ちょうどわたしが写真集を買いあさっていた時期、1985年前後のことだった。そのころのわたし自身の状況といったものの記憶を辿ってみると、その写真集を介在として、いくつもの物語へと遡っていくことになる。
わたしたちの物語が、いつも悲惨な結末を予期してしまうのは、なにもわたしの習性だけに起因しているのではないようだ。というのも、これまであったいくつかの関係の、始まりから終わりまでの道筋を重ね合せていくと、そこにはよく似た分岐で、結局のところ選ばれた道筋の結果が悲惨だったからである。悲惨をとおりすぎれば信仰があるとは、いわれているけれど・・・・。
ベルメールが生まれた1902年は、19世紀の終わりと同時に20世紀の幕開けの時代であった。神が不在になりつついあった時代の到来、とでも云えばよいのだろうか。わたしの時代イメージには大戦前夜の重くて暗い足音が聴こえてくるような感じである。魂の根元を癒し包み込んでくれる神が、どこかへいってしまった時代。
厳格な体制に対してデカダンな生活。戦争の時代の生産活動からみて、無意味なものの追及は、自分の幼年期の延長線上にたわむれることであった。オブジェとして人形の部分を造り組み合わせる。母の渇望として、時代の流れに編熱狂であった時代の始まりのとき。
1934年「人形」自費出版に撮られた写真。1945年に撮られた写真。1958年に撮られた写真、ウニ・チェルンの緊縛写真。
1933年ナチ政権の誕生、抗議のため国策につながる職業の放棄、無用性にむけて弟と人形を作る作業に入る。線描画によるエッチング。
ウニカ1916年生まれ、ウニカとの生活ウニカ35歳、ベルメール51歳。
1953年ウニカ・チュルンとの出逢い。
1957年「イマージュの解剖学」
1965年「道徳小論」(10枚の二色刷り銅版画集)
1967年ウニカ「神託とスペクタクル」
※1918年、第一次世界大戦の終結、ハンガリー帝国の崩壊とオーストリアの成立、ロシア革命、バウハウスの開校。ベルメール16歳、「人形」の発表1936年と「イマージュの解剖学」論文。そのインパクト、人間の深層・基底にあるもの。
・西欧文化の中の人間と神
・私の人間観、深層の心理、肉体的感動
・その底に、古代の信仰、人間と樹木・植物・動物
・異化作用することで私の日常が異化される
・構造分析
人間の求めるもの、抑圧(ナチズム)からの精神の解放。
・どこへ到るのか、行先の見えない出口。
・オブジェとしての解剖学、イメージの昇華。
・無用のものを作ること、芸術と宗教。
・深い欲望、人形への偏愛、異端は絶望。
・エロティシズム、エロスとは何か、浪漫主義、耽美主義。
・マルキシズム(中央思想)と全体主義の人間論。
・生と死、戦争と人間、
ねじれた感性、無神論のベルメール。
抑圧されるエロス、神の冒涜、神への怖れ。
神への反抗、実存主義。
文明・文化・風習の限界・・・・文化装置としての危機に遭遇するのを減らすことにある。
人間の奥底にある魂がもっている何か(男性女性を超えたもの)にふれる。これの自己実験する行為が芸術行為である。
メモ:
※(ダダ)第一次世界大戦中とその直後の虚無と幻滅の気分を反映し、非合理、幻想、などを武器とし社会的、美学的に因習や権威を嘲笑、破壊しようとしたもの。
1916年スイスに集まった詩人ツアラを中心に、ビカビア、デュシャン、エルンストら。
シュールリアリズム、1924年アンドレ・ブルトンの超現実主義宣言。ダダの発展とみてよいが、ダダの非合理に対し、超合理を特質とし、フロイト学派の影響を受けた。超現実的の概念は、1917年詩人アポリネールが初めて用いた。
不器用であることの意味を解析する哲学的考察。
現代の表層と自分の精神、精神の洞察が深いほど違和感を感じる。
交わらない自分。自分の内へ。自分のイメージに。
自然論と文化論など、精神の解放へ・・・・・のプロセス。
※原罪の根源、男を誘惑し堕落させる肉体を持つ女は、直接神に近づくことも許されないので、自らの肉体を神の器、神と直接交流することのできるものへと変容させる。
神に憑かれる能力を自己統制する女たち、職業的な巫女になる女、自分自身が救済する神であるという自覚・・・・・・<霊力>を実体化する過程は、女の生殖能力・性的能力は神秘化される。これらは男と女に不均衡に配分、構造化された権力関係・力学のなかで進行してきた。
近代国家の知の権力を掌握する<男>集団として、女という<性>を自然化してきた。「エクスタシーの人類学」、個々人が被る苦悩や困難は、当該社会の構造と深く関わっているとして、女が男に比べて、より頻繁に神や霊に憑かれるような社会は、男が社会の優位を占め、女性が劣位にあって服従を強いられるような状況がある。
社会的な弱者である女性が、神の権威を帯び、シャーマン化することによって、権力関係の位置、社会的な地位を変更する。彼女らは救われるべき存在から、人々を<救う><癒す>力を持つものとなった。しかし、女が神になるという事態を、国家の秩序維持機構としては認めない。
(4)
わたしの生きた証としての芸術とのかかわりのなかで<美術>という概念は、わたしの一番遠くにあった概念であった。音楽や文学の領域への興味は、ずっと昔から、何回も入れ替わりながら、比較的身近に感じていたし、政治や経済という領域についても、理解できないことはない、と思っていた。しかし、美術という概念は、わたしの一番遠くにあったものであった。
芸術とはなにか。芸術はどこまで社会制度から逸脱することができるか。芸術は文明・文化・風習が作り出す装置を壊すこと・・・・信仰心へ-祈る行為-。
「情動」というわたしの根底のところで突き動かしているのは、わたしの「印象」である。おそらく、この印象の質と深みの度合いによって、情動の餌というのが問題である。感動も情動の餌になるというような根本的なものである。
生き方の不器用さについて、社会にそむく、聖なる生き方は、社会からは不器用な生となる。天が授けたわたしへの贈り物として、ベルメールの人形がある。しかしその贈り物は、わたしを混乱させる。わたしの人生とベルメールの人生を重ね合せてみる。31歳、ベルメールはナチに反逆、わたしは釜ヶ崎へ、50歳のウニカ緊縛写真、わたしはスイートルーム。信仰という魂の状態があるとすれば、それは何かにすがって信じて祈ることである。
いつの頃からか、わたしの最大の関心事の対象は、身体そのものに向けられてきたといえるだろう。とくに女体については、性に目覚める頃からいままで続いていることだ。時代の中で、文化の中で、人が生きていくには技術がいる。おそらくいつの時代にも、その中で生きる人々があり、その人が生きた長さだけの滞在がある。この世での滞在者たちが培ってきた領域は「文化」と呼ばれまた、風土の一角をなしているのだ。人はおおむね外界と関係を結びながら、日々を経過させていくものだが、その時々の関係の結びかたが様々にあるといえる。
何かに対して、有用なもの無用なものといった分類の仕方があるとすれば、社会を構成する単位として「無用なもの」にこそ意味を見いだす類の感性を、露呈させてしまう場合があるようだ。生きるということは、この無用の領域においてこそ、実感としての生を感じるのかも知れない。1933年にナチズムに反抗する行為は、生きる技術の裏返しは、社会のなかでの生産、勤労、体制協力といったことにつながっており、みずからのアイデンティティを放棄することであろう。
生きることの不器用さは、生活を営むことに対しての、不調和感であるようにも見受けられる。ベルメールが自分のイメージを、具体的な<人形>に仕上げていくとき、その物はベルメールにおいて、どのような意味をもったのだろうか。わたしの興味はそのことである。ベルメールの記憶のなかの何がそのように仕向けていったのか、その情動について論じなければならないだろう。
情動が立ち起こる場においては、世界を構成する「概念」は不要である。感動そのものの原点は、情が感じて動くことである。その状態が現われるのは、すでに動く準備ができていたからである。知の領域で成しえられることは、些細なことでしかない。
(5)
スイートルームについて、なぜプライベートなのかの考察。
意味の解体と生成・変容・・・・解体。思い出したかのように、1978年の夏に、私によって書かれた<私風景論>を読み返した。なぜ、今、私風景論なのかと問い直してみる。ずっと私のなかで気にかかっていたものだった。私のとらえ方それ自体、その当時の私の意識、感情、そして表層としての行動。意識の構造。感性の生成。等々、私自身のなかに限っていた考えそのもの。それらが今、あらためて記述していこうとする文章に、流れ着くような気がしてきたのだった。
その当時の私に、明らかにならなかったもの「叙情」と呼んだもの。意味の生成と感情の生成について。そのことが新たなる切り口から論じられそうな気がしているからである。何をしているんだ、と自分に言い聞かせる。何をしているんだ、無駄なこと、無意味なことを、とぴう思いが立ち起こってくる。このことは人間にとって必要なことなのか、との問いかけが起こる。そしてベルメールの生き方論につながっていくようなのだ。意味の解体と意味の生成は、根元のところでつながるのだろう。その場所から磁場を生成させるイメージとしてのベルメールなのである。
時間の解体と時間の生成・時間の意味変容・・・・解体と輪廻のように繰り返される全てを根元から見直すこと。これが私とあなたの人生について、あるその方向について、私とあなたのかかわり方について、何故なのか、どんな意味があるのか、と問いかける。
なぜあの時なのか、と問う。初めて会った図書館で、どの書籍の扉を開こうかと選択した結果として「ステーグリッツが撮ったオキーフのポートレート」であったが、もう一つの扉として「ベルメールの人形」という選択があった。そのとき、いま一枚、写真をあげるとしたら、といって初対面の最初はオキーフであり、そして二番手にべりメールだったのだ。
あのときの私自身の内的状況を話そう、それが私への探求のはじめだろうと思う。宗教というものは信仰の心を根元にもつものだ。女性的発想である。信仰心とは何なのか。どこから芽生えてくるのだろうか。その原点はどこにあるのだろうか。
何かにすがって、信じて祈る、という行為が自然と出てくること。命の危機に追い詰められていたときに、出てくるものなのか。文化文明風習の限界は、文化装置として危機に遭遇することを減らすことにある。私は求めている。人間の奥底にある魂のもっている何か。男性女性を越えたものにふれること。これの自己実験していくことが芸術であろう。母なる大地に根ざすもの。