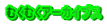
最新更新日 2014.6.24
中川繁夫の書簡集 2001~
中川繁夫:著
中川繁夫の書簡集

書簡009 shigeo nakagawa 2001.10.3~
写真への手紙・覚書
<マクロとミクロ>
天体望遠鏡と顕微鏡、精神宇宙と人体のはなし。
-1-
わたしが小学生のころの話しをしてあげましょう。これは自分の在処を探しているわたし自身のための記憶の掘り起しです。この先のわたし自身の生きかたのスタイルを模索していくためのトレーニングとでも云いましょうか。わたしが少年だったころの、こころの中に何があったのかを、イメージしていきたいと思っています。
こうしてわたしは初めて小学生の年代の自分の記憶を辿り始めていくのですが、立ち現われてくる記憶の光景は、非常に特異なもののように思わざるを得ないようです。人間の内面の世界が意味不明の衝動に突き動かされて、意味不明の行動を選んでしまうとすれば、この意味不明の部分が、実は記憶を辿っていくことで、意味を解明できるようにも思われるのです。
自分を分析し検証すること。これは恐怖の分野であると思います。それぞれ内面において秘密にしておかなければならない一線があるとすれば、その一線を超えて露出させることは、今のわたしのなかでは、非常に重要な意味を持っていると思われます。それが何故なのかは、明確にはわからないけれども、おそらく自己自立のための作業であり、悟りを得ていくための煩悩を払いのけるための儀式であるように思うのです。その儀式をふまえながら、わたしは次の預言者になりうるのだろうと、思いはじめています。
まだ小学校の3年生か4年生のころの記憶。ジャンバーを着ていたから冬。冬空だったと思います。星がいっぱいありました。それを見上げているのが好きだったようです。なにかの雑誌で、天体に散らばっている星のことを読んでいたのかも知れないと思いますが、とにかくいつまでも見上げていた記憶があります。たぶん学校のクラスのなかでも星座のことや星のことを、話題として一番多く持っていたのかも知れません。
担任の先生は草田美智子先生といいました。旧姓小峰先生。いろんなことを知り始めるころ、特に科学に興味を持っていたのだと思います。学校でクラスのだれだったか覚えていませんが、先生に星のことだったか星座のことだったかを聞いている男の子がいました。ひょっとしたら理科のカリキュラムに、星のことがあったのかも知れません。草田先生は、そのとき、わたしに聞くように、夜になったら一緒に空を見て教えてもらいなさい、というようなことを言ったのだと思います。
何人かの男の子が夜に訪ねてきました。そして一緒に空を見上げていました。何をどのように教えてあげたのかは記憶にありません。オリオン座のアンドロメダ星雲のことをすでにその当時知っていたのかどうかはわかりません。きっと火星や北極星や何かの話しを、少年が知っている知識をもって処していたのだと思います。そのときの気持ちを覚えています。
ちっとも知らないのに教えられない、と思っていたのです。はずかしい気持ちがありました。わたしの好きな領域は、そんなのじゃなかったんです。きっと、ね、織姫と彦星の一年に一回七夕を悲恋物語として感情に仕舞い込んでいたと思うんです。淋しい気持ちになること、胸がきゅっと締めつけられるような感覚、そのまま天空へ召されていく「地上よさようなら」の恐怖というより別れの感覚とでも云えるでしょうか。
そんな気持ちはありましたが、星や星座の知識なんて、そんなになかったのです。いや、星座の名前はよく知っていたかも知れませんが、その星座が天空のどの星なのかがわからなかったのです。オリオン座は知っていたと思います。北斗七星なんかも、しかしこれってだれでも知っている星座だと思います。この程度のことしか知らないのに教えられない、との思いだったのです。これは恥ずかしい気持ちの記憶です。
-2-
マクロとミクロの世界。空想の世界だったと思います。現実に見上げる空の星の写真が、きっと雑誌に掲載されていたのだと思います。土星に輪があることは知っていましたから・・・・。宇宙人ってどんな姿をしているのだろうと思っていました。そのころ映画館で、宇宙人の襲撃みたいに地球へ攻めてくる映画を見た記憶があります。宇宙には地球と同じような環境、つまり生物が住んでいる星が4千個あるとあったかな、その生物は時間を自由に操ることができて、過去にも未来にも行ける乗り物をすでに保有していて、一瞬のうちに自由に移動できる・・・・。ほんとに存在すると思っていました。なに食べて生きてるいるんやろか、とか、やっぱり便所ってあるんやろか、とかですね。だれにも聞かずに空想で考えていました。
小学校の5年生か6年生の頃になっていたと思いますが、天体望遠鏡がどうしても欲しくてたまりませんでした。自分で天体を覗いて見たい欲求なのでしょうね。未知への興味といえばよいのかも知れないですが、模型のお店で組み立て式のキットを買いました。500倍の倍率のはずのものでした。レンズを組み込み、長さ1メートル、口径10センチ程度の望遠鏡、組み立てましたが、倍率は2倍くらい以上にはあがりませんでした。
その頃には、一方でミクロの世界といえばよいのでしょうか。顕微鏡下の世界にも興味を持っていました。生活のレベルで、わたしは家業といってもいいのかな、夏になると、かき氷の店をやっていました。その労力にかりだされていたのです。お手伝いをしていました。一杯5円のかき氷は評判で、とっても忙しかったように記憶しています。すでにモーターで、四角い氷をのせて下で受けて、茶碗に富士山のように盛って、蜜をかけるのです。その手伝いというよりも祖母と一緒にやっていたのですが、祖母はむしろ接客の係で、わたしが製造担当のような役割でした。
その夏になる前に、父と約束をしたのでした。夏の氷の時期が終わったら、手伝い料として顕微鏡を買ってもらう、というものでした。目的の顕微鏡はもう決まっていて、千本中立売近くの眼鏡店のショーウインドウに置かれていたものです。500円の値札がついていたと思います。けっこう高額だったのでしょう。今の金額でいえば1万円くらいはするのではないでしょうか。父は約束をしてくれました。それでその夏は顕微鏡が手元にはいることを夢見て、お手伝いに励みました。
こうして記憶を辿っていくと、これがわたしの初めての交渉ごとです。夏の季節が終わって、父に買ってくれるように言いましたが、なかなか買ってくれませんでした。何度も何度も買って欲しいと言ったのだと思います。根負けしたのでしょう。もう秋もかなり深まっていた頃に、顕微鏡が手に入った。父に対して要求したのは、わたしのこれまでの生涯にたった一度、このときだけです。このようにして手に入れた顕微鏡で、いろんなものを観察したという記憶はないです。蝶の羽根の模様を拡大して見たとか、木の葉の葉脈を拡大して見たとか、の記憶はありますが、すぐに熱が冷めてしまったように思います。
-3-
中二階の、母が嫁入り道具で持ってきた箪笥の引き出しに、雑誌が何冊かしまってあるのを発見しました。この雑誌は昭和27年頃に売り出された雑誌で、風俗草子と奇譚クラブでした。それとは別に、もう使わなくなった陳列棚のなかに、人体にまつわる解説書のような本がありました。わたしの家では、ちょうどわたしが生まれるころから小学校にあがるまでの間、壬生で漢方薬を売る店をやっていました。
漢方薬の店は、母方の祖父が始めた商売で、烏丸六条に本店がありました。井上漢方薬店と看板があげられた店は、その後もずっとありましたが、その二階に医務室のような部屋がありました。そこには人体の全身模型で、腹部が開かれており、心臓だの肺だの胃だのといった内臓が露出していてえぐった回りの皮膚が赤い色に塗られていた人形がありました。二階のその部屋は、診察室だったのでしょうか。あるいはカウンセラー室だったのでしょうか、その部屋に入ると、不気味で異様な雰囲気で、怖くて身震いがした、というような記憶があります。
壬生のわたしたちの家が、井上漢方薬店の支店というか、当時そのように呼んでいたかどうかはわかりませんが、父の商売はその店を経営することだったのでしょうか。当時、正式にはなんと云うのかわかりませんが、産児調整の指導所というようなことだったのでしょうか。つまり避妊の解説書、学術書だったと思われる本がありました。それらの本をみて、非常に興味を持ちました。性教育は母親から中学三年生のときに、雑誌の付録だったでしょうか、これを読んどき、といって渡されたペーパーブックを読みましたが、それ以前の小学生の高学年で見たのは専門書だったのかどうかわかりませんが、この指導書の図版と解説を読みました。
男女人体局部の構造図がありました。そして受精の仕組みの解説や制限の方法の解説といった内容のものだったと、記憶がよみがえってきます。もちろんまだそのこと自体の意味はわからない年齢でしたし、欲情もまだ湧いてこない年齢です。ある意味では、生物科学を生物科学として素直に読んだのかも知れません。肺の働きとか、胃の働きとか、血液の話とかいった類の一連の知識として、記憶の層にしまい込まれたのかも知れません。
原子記号やその仕組みなどに興味を持っていました。高校生の参考書を本屋さんで立ち読みしていた記憶があります。日々のイメージのなかに、物体を見るとき、たとえば金槌をみて鉄の原子記号を想定するとか、水や空気の原子のつまった空間のようにイメージしたりです。なにか驚異の世界に、日々住んでいるような幸福に、満たされた時間がそこにはあったような気がします。ひとりだけの世界でした。このようなことはだれにも言いませんでした。秘密だったのでしょう。
風俗草子や奇譚クラブは挿画つきの読み物が結構ありました。見たり読んだりの内容は怪人二十面相の恐怖感よりやわらかい感じでした。しかしこの世界は不思議な世界でした。いまも手元に何冊か保存してありますが、ミクロの世界への探索は昂奮を伴いながらの体験でした。天体へ向けたまなざしとは違ったまなざしを、わたし自身の内部にしまい込みました。
-4-
金閣寺の裏の衣笠山北端に狸谷不動尊と呼ばれる祠がありました。そこに、俗称で拝みやさんと呼ばれているおばさんがいました。ぼくが小学校のころの話です。ぼくの家には何の神さんだったのか分かりませんが、その神さんの祭壇がありました。四畳半の部屋一室が食事と寝室を兼ねる長屋のなかの一軒でした。その部屋の天井近くの一角を祭壇が占めていました。毎日、父がろうそくをあげていたようです。
年に一度、祭礼の日がありました。祭壇の下にしつらえた素焼きの器に護摩木を積んで火をつけるのです。ぼくが3年生か4年生のときの護摩焚きのときでした。白い着物を着たおばさんは手の平を合わせて人差し指を突き出し上へあげたり下げたりしながら、一心不乱に、というのでしょうか、なにやら、ふにゃふにゃエイヤー、の繰り返しをやっていました。
火の手は1メートルくらいの高さまで燃え上がっていました。異様な雰囲気がおばさんの身体から昇っていくようでした。エイヤー、エイヤー、エイヤー、とやっているとき、ぼくには聞こえたのです。言葉の内容は忘れてしまいましたが、女性の明るい声だった記憶があります。ほんの1秒間ほどの言葉でしたが「安心しなさい」といったような内容ではなかったかと思います。ぼくの心を安心させるものだった、と記憶しているからです。今でも神の声として時たま思い出します。明るく高い声だった。この拝みやさんにまつわる記憶は、けっこう沢山あります。その記憶を抜きだしてみたいと思います。
氷室の池は、火葬場へいく道の傍らにありました。金閣寺の裏手にあたるその池の奥に、狸谷不動尊はありました。池の淵を通って、山際のほそい道をいく途中に、湧き水が出る崖がありました。そこが不動尊の入り口だったと思います。湧き水のそばに真っ赤な目の白蛇がいるのを見ました。白蛇の子供だったのでしょうか、かなり小さかったように思います。白蛇の物語がなんだったか忘れてしまいましたが、そこに神さんの使いだという認識があったように思います。
鬱蒼と茂った木の葉の下の湧き水場の光景と、白蛇の真っ赤な目がぼくの方を見ている光景が、重なって見えてきます。ぼくは風景に怖さを感じたのではなくて、その場が漂わせる霊気とでもいうのでしょうか、その雰囲気に恐怖という感覚ではなくて、なにか恐れる気持ちを醸造させていました。この光景に出合ったのが何回あったのか、一回限りだったのか、はっきりしませんが、吸い込まれていくような感覚でした。その小道の向こうには、ブンブンやカブトムシが捕れる雑木林がありました。自転車で池のそばまで来て、そこへはいっていくのでした。しかしぼくは虫取りが上手ではなかったようです。収穫の記憶はありません。
夏の日の午後でしょうか。近所の子供が一緒だったから、年寄り連中がその祠に集まっていたのだと思います。そこで夕立にあいました。すごい豪雨のような夕立でした。雷が真近で鳴りました。ゴロゴロという音ではなくて、ドッカン、ドッスンというような感じでした。光った瞬間には炸裂する音が全身を包みました。雷が真近くに感じたのはこのときが初めてのことでした。最初の一発はかなりきつくうろたえましたが、二発目以降は快感のなかの放心状態とでもいえるのでしょうか。異様な不思議な感覚だったように思います。なにか自然の中の空気とぼくの身体が、交感していたのかも知れません。
こんな記憶もあります、鎌鼬。その付近の草むらで、なにをしていたのか思い出しませんが、半ズボンで露出していた膝に裂け目を見つけました。1センチ以上の傷で開いた傷口は、白く見えました。ぽっかり空いていた、という感じです。痛みは感じませんでした。血も出てきません。その光景がよみがえってきます。祖母が、鎌鼬にやられたんや、と言いました。
-5-
小学校の2年生頃から、ぼくは叔母さんと一緒に寝るようになりました。中二階の四畳半の部屋。大人が立ち上がるとと頭が天井につかえてしまう部屋。この中二階は西陣の織屋の造りなのです。そこで叔母さんとぼくは親子のように生活をしました。今もって確認していませんが、叔母さんは夫を戦死かなにかで別れて、ひとりでした。母親と同い年だったか一年下だったかで、子供がいればぼくくらいの年齢だったのではないかと思います。
叔母さんは織機の織子として近くの工場へ行っていました。一緒に寝だした当時は30才過ぎくらいだったと思います。厄年の話しをしていたのが記憶にあります。女の厄年は数えで33才だからそのくらいの年齢だったと思います。週末には、よく映画を観に連れて行ってくれました。東映、大映、松竹と、毎週上映作品が変わっていったように思います。
東映は毎週変わる連続映画、中村錦之助、東千代之助、片岡千恵蔵、いましたね、銀幕のスターたちが勢ぞろいしてぼくの前にいました。現代のテレビドラマのようなシリーズ形式でした。松竹の映画は、たぶん文芸物だったのかな、と思います。金色夜叉、湯島の白梅、女系図といったような男と女の物語だったと思います。子供心に一生懸命見て感動していた記憶があります。胸を締め付けられるような痛みを伴うような感動でした。別れの悲しみ、といったものが伝わって、子供の心にも理解できたのかも知れません。
間借りしている親子の生活そのものだったように思います。自分の母親が他人のような錯覚があったように思います。お風呂へ一緒に行きました。ひとつの布団で寝ていました。クッキーだとかケーキだとかアイスクリームだとかのお菓子を、よく買ってもらって二人で食べました。この蜜月の生活がある日、ぼくにとっては突然でしたが無くなってしまいまいた。小学校5年生のころです。佐々木さんという男の人と再婚したのです。
ぼくには何の前ぶれもなく、さようならもなく突然でした。別にそのことで悲しんだ訳ではなかったけれど、寂しさを感じたのは確かなようです。その日以来ぼくは、その二階の部屋でひとり寝をしたのではなかったかと記憶しています。その頃からぼくは、夜にはひとりで自転車に乗って家を出てさまよったようです。繁華街へ出て行った記憶はありませんが、暗い道を自転車に乗ってゆるゆると走っていたのを覚えています。
やっぱり寂しかったのだったと思います。何を考えていたのか記憶も定かではありませんが、その前後の昼間の記憶からすると、天体に関することや、物理学のことや、人体のことなどを考えていたのではなかったでしょうか。悪魔の空間とでも云えるでしょうか。映画で観た場面からの次のシーンを、カストリ雑誌の内容に重ね合せて想像していたように思います。
時代劇ではお姫様がでてきました。そのお姫様が誘拐されて監禁されるという場面が、映画の中にはけっこうありました。逃げられないように縛られて猿轡をかませられる、といったような場面です。ぼくの空想領域では、そのお姫様が次々にいたずらされていくのです。その光景を想像して恍惚としたものを内側に感じ始めていたようです。12才のころ、性に目覚める頃だったのかも知れません。
漢方薬店の二階にあった内蔵の露出した人体像や図版が登場してきました。箪笥の奥にしまい込まれた雑誌や、陳列棚の医学書のような本の文章からイメージした人体像が登場してきました。今、この記憶を辿りながらぼくは、ぼくの経験を特異なものとして得てしまったのではなかったか、と思いはじめています。
ぼくが幼年の頃からの記憶を丹念に辿り始めている目的は、なぜ異端者のような、今にいたる感性を持ってしまったのかという道筋を、特定していきたいとの思いがあるからです。その先に見え隠れしている涅槃の世界といいますか悟りの世界といいますか、を得るための作業としてあるように予測しています。またぼくの宇宙観や世界観や人間観といったものの根底を形成している感性の出自を、先天的な領域とその後の領域との中で、どのように変節しながら、今にいたっているのかということの論証を、自分自身をモデルにして解明していきたいと思うからです。